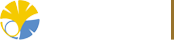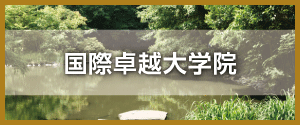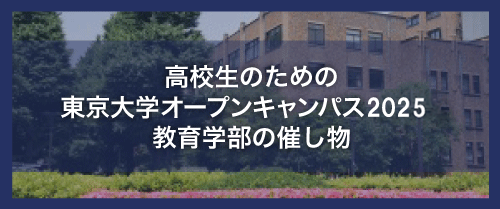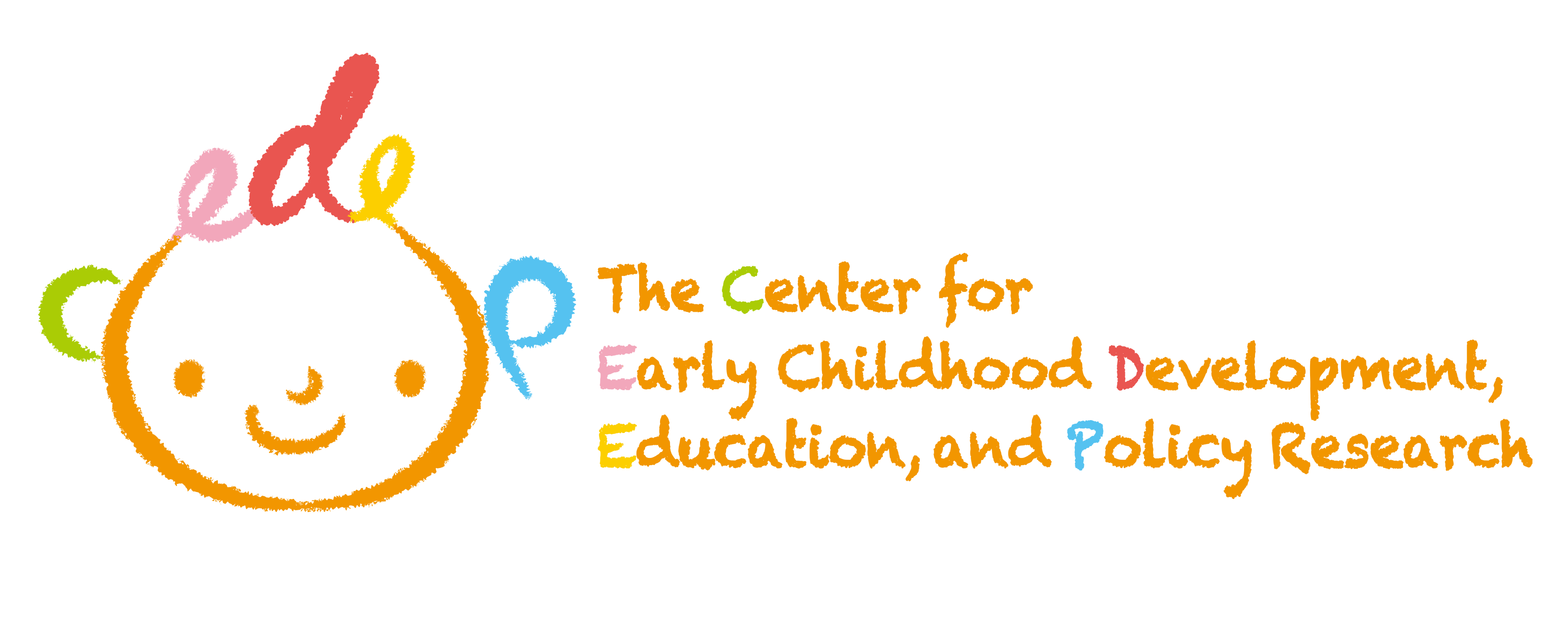生涯学習基盤経営コース スタッフ紹介 コースのWEBサイト
李先生_2018.jpg)
李 正連(い じょんよん) 教授
社会教育学
社会教育とは何か,という問いにすぐ答えられる人は,研究者の中でもそれほど多くないと思います。社会教育はよく「ごった煮」といわれているように,その対象及び教育(活動)の内容や方法,場所なども非常に多様で,広いです。では,このような「社会教育」という言葉はいつから使われ始めたのか。その用語の起源をはじめ,近代社会教育の成立と展開について研究をしています。そして,最近は日韓の社会教育・生涯学習の政策や教育福祉問題,草の根教育・学習運動などにも視野を広げて検討しています。
代表著書:
- 『日本の社会教育・生涯学習-新しい時代に向けて-』(共編著,大学教育出版,2013)
- 『社会教育福祉の諸相と課題―欧米とアジアの比較研究―』(共著,大学教育出版,2015)
- 『国家主義を超える日韓の共生と交流』(共編著,明石書店,2016)
- 『躍動する韓国の社会教育・生涯学習―市民・地域・学び―』(共編著,エイデル研究所,2017)
- 『植民地朝鮮における不就学者の学び―夜学経験者のオーラル・ヒストリーをもとに―』(博英社,2022)

新藤 浩伸(しんどう ひろのぶ) 准教授
生涯学習論
人間の生涯にわたる成長・発達における多様な学びの意味を、表現・文化活動、芸術活動を中心に研究しています。さらにそのための環境をどう支援し創造していくか、イギリスなどとの比較も視野に入れつつ、日本の公共ホールや博物館などの文化施設、教育・文化政策、文化産業の歴史に即して調査しています。人が暮らしの中で楽しみ、学び、変わり続けることで創造されていく社会や文化の形を、フィールドの中で恊働的に、また歴史的にも探求したいと考えています。
代表著書:
- 『表現・文化活動の社会教育学』(共著、学文社、2007)
- 『公会堂と民衆の近代―歴史が演出された舞台空間』(単著、東京大学出版会、2014)
- 『地域学習の創造―地域再生への学びを拓く』(共著、東京大学出版会、2015)
- 『成人教育と文化の発展』(監訳,東洋館出版社,2016)
- 『触発するミュージアム―文化的公共空間の新たな可能性を求めて』(編著,あいり出版,2016)
- 『地域に根ざす民衆文化の創造―「常民大学」の総合的研究』(編集委員,藤原書店,2016)
- 『文化政策の現在』(全3 巻,共著,東京大学出版会,2018)

影浦 峡(かげうら きょう) 教授
図書館情報学
そもそも言語において考えることとは何かを研究しています。その大枠の中で,メディア/言語の分布構造を分析し,近代の図書館が実現しようとしてきた理念とはどのようなものだったのか,それはどのようなメディアと言語の配置を前提としていて,その前提はこれからどのようになっていくのか,といった問題を考えつつ,メディアや言語の理論からリテラシーの実践・工学的応用まで,いろいろやっています。オンラインの翻訳教育システム「みんなの翻訳実習」(http://mnh-tt.org)も運用・公開しています。
代表著書:
- The Dynamics of Terminology(John Benjamins, 2002)
- The Quantitative Analysis of the Dynamics and Structure of Terminologies(John Benjamins, 2012)
- 『信頼の条件ー原発事故をめぐる言葉』(岩波,2013)
- Metalanguages for Dissecting Translation Processes (Routledge,
2022, 共編著) - “The mishandling of scientifically flawed articles about radiation exposure, retracted for ethical reasons, impedes understanding of the scientific issues pointed out by Letters to the Editor” JoSPI(2022, 共著)

河村 俊太郎(かわむら しゅんたろう) 准教授
図書館情報学
図書を中心とするメディアを通じて、学問などの知識が近代以降どのように形成されてきたのかについて、図書館という組織の視点から見ていくことに関心があります。具体的には、図書館の蔵書が歴史的にどのように構築され、学問や教育に対してどのような役割を果たしてきたのか、図書館がどのように他の図書館や社会などから影響を受けつつ独自の組織を構築し機能してきたのか、さらには図書館間でどのようなネットワークが構築されているのかについて研究しています。
代表著書:
- 『図書館情報学教育の戦後史―資料が語る専門職養成制度の展開』(分担執筆,ミネルヴァ書房,2015)
- 『東京帝国大学図書館』(東京大学出版会,2016)

宮田 玲(みやた れい)講師
図書館情報学
一定のまとまりを持った知識の社会的な伝達を可能にする図書や文書といったメディアに注目し,その生産・編成・流通・提供のプロセスを高い解像度でモデル化することを目指しています。これまで「できる」けれども「説明できない」形で専門家の暗黙知に留まっていた文書デザイン,執筆,翻訳に関する知識を,科学的な認識の対象として明確化し,共有可能にすることが中心的な課題です。また,機械翻訳等の言語処理技術を活用した行政文書や産業文書の多言語展開に関する応用研究にも取り組んでいます。
代表著書:
- Controlled Document Authoring in a Machine Translation Age(Routledge,2020)
- Metalanguages for Dissecting Translation Processes(共編著, Routledge,2022)