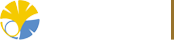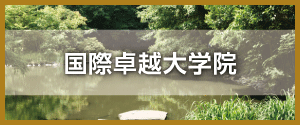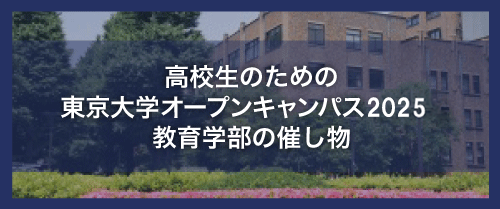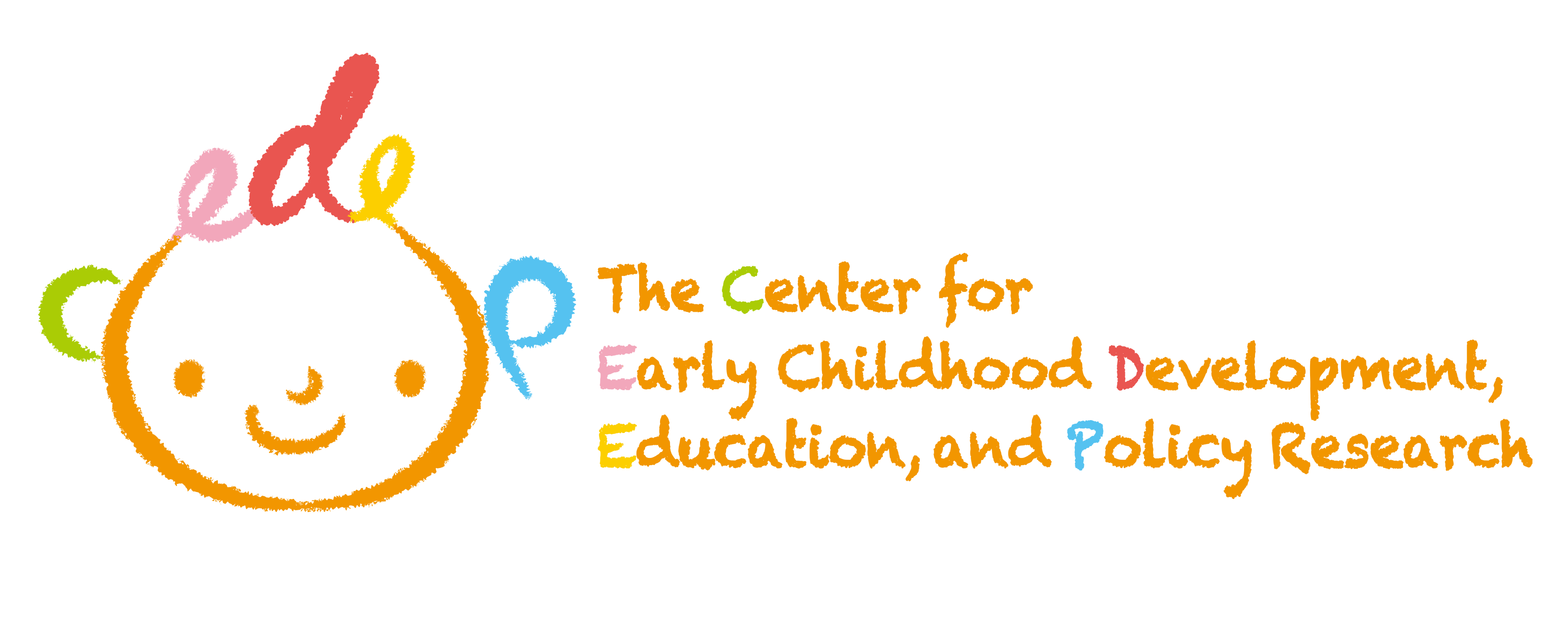比較教育社会学コース スタッフ紹介

本田 由紀(ほんだ ゆき) 教授
教育社会学
主に,家族と教育,教育と仕事,仕事と家族という,異なる社会領域間の関係について調査研究をしています。90年代以降の日本社会では,この3つの関係には矛盾が露わになっています。たとえば家庭教育に対する圧力や格差の高まり,「学校から職業への移行」の機能不全,仕事の不安定化による家族形成の困難化などです。それらをどう立て直していくか,行政や草の根的な運動がいかに関わってゆくべきかを考えています。

中村 高康(なかむら たかやす) 教授
比較教育システム論
大学入試や高校生の進路選択など、「教育と選抜」に関わる諸現象の計量的・比較社会学的検討が主要な研究テーマです。近年では関心を拡げて、社会階層と教育制度の関連、進路選択と地域性の問題、メリトクラシー(能力主義)に関する理論的考察なども手がけています。量的な研究方法を使うことが多いですが、最近は質的な方法もできるだけ取り入れた総合的なアプローチ(混合研究法)がとても重要だと感じています。

仁平 典宏(にへい のりひろ)教授
教育社会学
既存の日本型生活保障システムが新自由主義的再編によってどう変わるのか,次の2つの動きに注目して社会学的に研究してきました。一つは公共サービスの民営化の動きです。この中でNPOや市民活動が社会サービス供給の新たな担い手として注目され,それを支える活動的な「市民」の育成が称揚されてきましたが,その可能性とリスクとを研究しています。もう一つは社会保障の〈教育〉化です。これは社会保障を人的資本投資の論理で再構成していくものですが、それが包摂/排除とどのように結びつくかに関心があります。

額賀 美紗子(ぬかが みさこ)教授
比較教育学
グローバル化の進展が家族,学校,子どものアイデンティティや能力形成に及ぼす影響に関心があります。国際移動する子どもに注目し,在米日本人家族や在日外国人家族のエスノグラフィー研究を行ってきました。学校の日常や家族の教育戦略の中でジェンダー,エスニシティ,階層,学力が交錯する過程を見ています。日米の学校調査を通じて多文化教育や市民性教育の国際比較も行っており,マイノリティを包摂する教育と社会のありかたを研究中です。

多喜 弘文(たき ひろふみ)准教授
高等教育論
教育機会の不平等が生じるメカニズムの日本的特徴に関心があります。過去には,PISA のような量的データを用いて,ドイツやアメリカとの制度的な違いに注目した研究などを行ってきました。国際比較の観点からは,日本との共通点が比較的多い東アジアの社会にも興味を持っています。近年は,専門学校や短大といった短期高等教育の社会的位置づけとその変容に注目することで,日本社会の特徴を描き出そうと試行錯誤しています。

荻巣 崇世(おぎす たかよ) 准教授
比較教育学
教育の発展とはどういうことかについて,カンボジアをフィールドとして研究しています。グローバルな収斂が進む教育制度・政策のもと,教室というローカルな現場で教えること・学ぶことの意味がどう変容し,どう変わらずにあるのかということを,社会文化的な視点から捉えることを目指しています。近年は,教育改革の流れの中で,カンボジアで教師を目指す若者たちの教師像がどのように変容していくのかを追跡する研究に取り組んでいます。