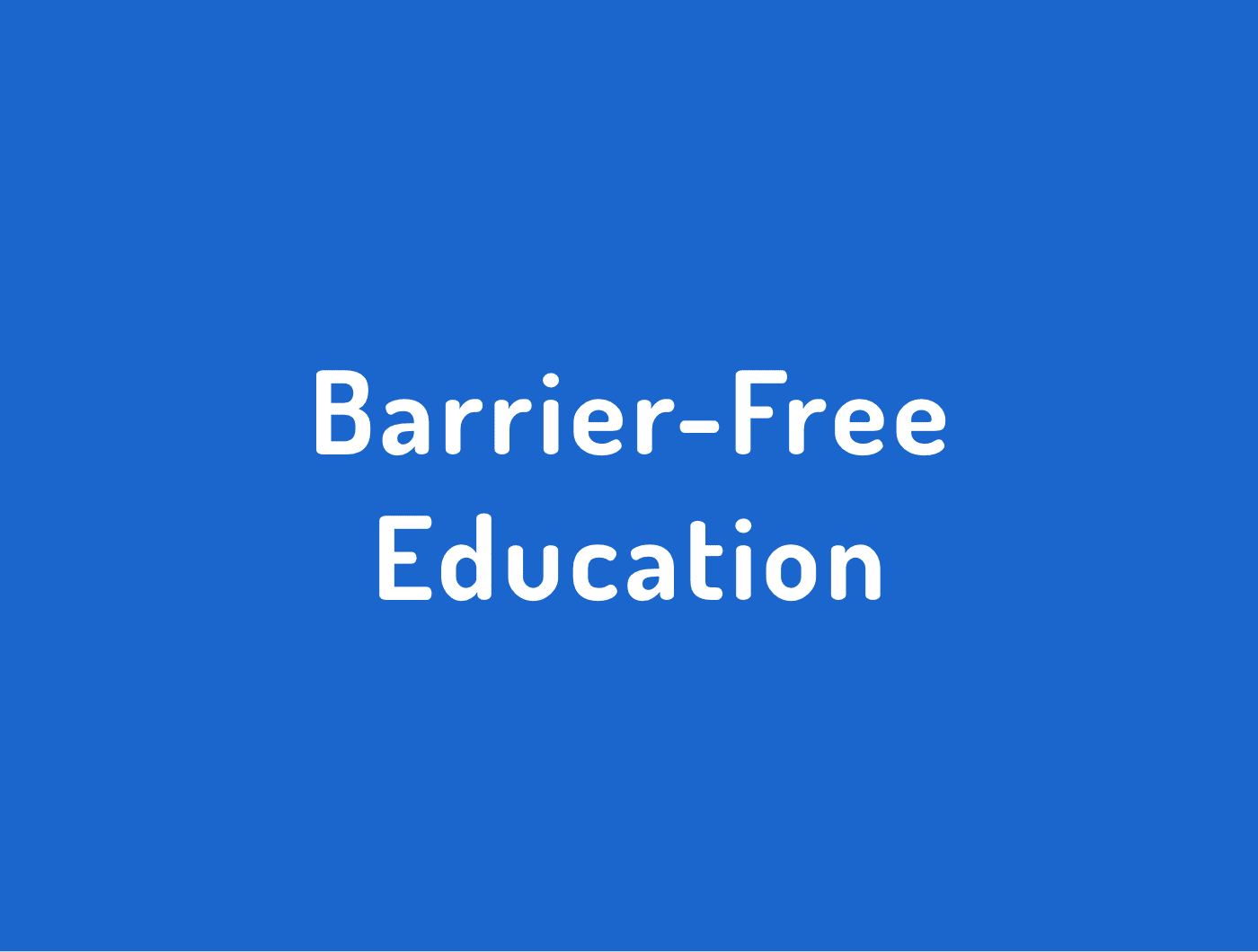「みんなの学校」こと、大阪市立大空小学校では、「すべての子どもの学習権を保障する」ことを理念に掲げ、障害のある子もない子もそれぞれの個性を大切にしながら、同じ教室で学ぶ。また、学校は地域のものという考えの下、学校は常に開かれており、サポーター(保護者)や地域住民が自由に授業に参加し、困っている子に寄り添っている。
「インクルーシブ教育の理想の姿」という多くの賛同を得る一方で、「特別支援を要する子どもが同じ教室にいると、『普通』の子どもたちの学力が付かない」などの外部からの批判も絶えない。
大空小学校で6年間学んだ卒業生たちが現在どのような考えをもち、どのような人生を踏み出しているのかを探る座談会シリーズ。
第3回は、創立10年目の卒業生、宇榮原太陽さん、中川和紀さん、田口屋香帆さん、平 美波さんが参加。4人が大空のリーダーを務めた6年時は、9年間校長を務めた木村泰子先生が退任し、子どもも教職員も少なからず動揺を抱えていたという。
初代校長として大空小学校の教育の礎をつくった木村泰子、大空小学校の実践研究を続ける小国喜弘と卒業生たちの座談会から、インクルーシブ教育や特別支援教育の課題と、今後のあり方について考える。
座談会参加者
- 宇榮原太陽(うえはら・たいよう)2003年生まれ。2016年、大阪市立大空小学校卒業。興國高校卒業後、近畿大学入学、在学中。
- 中川和紀(なかがわ・かずのり)2004年生まれ。2016年、大阪市立大空小学校卒業。堺市立堺高校卒業後、クボタ機械設計株式会社に入社、農機を担当する。
- 田口屋香帆(たぐちや・かほ)2004年生まれ。2016年、大阪市立大空小学校卒業。大阪学芸高校卒業後、広島都市学園大学看護学科に入学、在学中。
- 平 美波(たいら・みなみ)2003年生まれ。2016年、大阪市立大空小学校卒業。大阪府立長吉高校卒業後、常盤会短期大学幼児教育科入学、在学中。
- 木村泰子(きむら・やすこ)2006年~2015年、大阪市立大空小学校の初代校長を務める。すべての子どもの学習権を保障する学校をつくることに尽力。2015年、45年の教員生活を終え、現在は全国各地で公演活動を行う。著書に『「みんなの学校」をつくるために』(小国喜弘との共著・小学館) ほか多数。
- 小国喜弘(こくに・よしひろ)1966年兵庫県生まれ。早稲田大学教授等を経て、東京大学大学院教育学研究科教授。大空小学校の実践研究を行い、インクルーシブ教育の新たな可能性を模索している。著書に『戦後教育のなかの〈国民〉―乱反射するナショナリズム』(吉川弘文館)等。
- 大島勇輔(おおしま・ゆうすけ)1983年大阪府生まれ。大阪市公立小学校教諭。株式会社リクルートに入社した後、母子生活支援施設で学習指導員をしながら大空小でのボランティアを経て、教員に。2011年~2016年度まで大空小に勤務。現任校では教務主任を務める。
- 徳岡佑紀(とくおか・ゆき)大阪市公立小学校教諭。2008年に教員となり、2012年~2018年度まで大空小に勤務。スポーツ好きで学生時代はラクロス選手として活躍。
- 上田美穂(うえだ・みほ)大阪市公立小学校教諭。2011年度から3年間、大空小学校で講師をしたのち、2014年に新採として大空小に赴任。同校では2019年度まで特別支援教育コーディネーターとして、様々な子どもたちに関わった。
本文
【木村】 この人たちは、大空創立10年目の卒業生です。この人たちの5年生までを見届けて、私は9年間務めた大空の校長を退任しました。ですから、この人たちが6年生の1年間どんな学校生活を送ったのかをまったく知らないのです。
まず、みんなに聞きます。大空での6年間で一番覚えていることは何?
【宇榮原】 バースデーメッセージ集会(※1)のときに、校長先生が一人一人にメッセージを書いてくれたバースデーカードはまあまあ嬉しかった。
【中川】 卒業のときもメッセージカードをもらいました。
【田口屋】 卒業式の予行演習のときに、図工で作った写真立てをそれぞれが受け取ったのですが、その中に木村校長先生からのメッセージカードが入っていました。まだ実家にあります。
【木村】 ちゃんと覚えていてくれているんだ。
【中川】 僕が一番印象に残っているのは、学校から脱走して先生に追いかけられたことです。ランドセルを置いて帰って、怒られたこともありました。
【木村】 そっか、カズ(中川)は脱走が一番残っているんや。カズは「俺はこっから動かん」と言って、動かなくなったことがあって、台車に乗せて運んだこともあったなあ。
【田口屋】 5年か6年のときに、水道が壊れて大洪水になったことはよく覚えています。ふざけ合っていた友達が、誤って蛇口にぶつかったら取れてしまったんです。
【大島】 あったあった。みんなで雑巾で拭いたなあ。
【平】 私は、コンサート(※2)ですね。子供たちだけじゃなく、観客の人たちも一緒に歌って、みんなで盛り上がったことが楽しかったです。
【木村】 この人たちが大空のリーダーとなった6年生のときに、校長が変わり、長く在籍していた教員が転任などによりごそっといなくなり、新しく転任してきた教員が増えた…そんな年でした。
大空では、卒業する子どもたち一人一人全員が、大空をもっとよくするためのメッセージを残してくれていましたね。私は9年間それを続けて、私の後を引き継いだ市場(達朗)校長も継続してくれました。
(田口屋)カホが卒業するとき、そのメッセージにすごいことを書いているんです。覚えていますか?
【田口屋】 まったく覚えていません。
【木村】 今日はそれを持ってきたので、これから読みますね。卒業前にみんなに書いてもらっていたプリントの最後に、「大空をもっとよくするために教職員に伝えたいことを書いてください」という問いがあります。
(平)ミナミは、「地域とのふれあいをもっと増やしてください」と書いています。
(宇榮原)タイヨウは、「ゲストも学校にたくさん来るし、コンサートも開けているから、今のままでいいと思う。もうこれ以上いい学校にする必要なし」と書いています。
カズは、「もっとおもしろい授業をしたほうがいい」と書いています。
カホは、市場校長にダイレクトなメッセージを書いています。しかも①~⑦まであります。
①メリハリをつける。
②前の校長のやり方でやっていたら、やらされている感じがある。今の校長のやり方でやったほうがいいと思う。
③いろんな子どもをちゃんと見たほうがいい。
④あまり大空のことを広めないほうがいいと思う。前とちがうからクレームがくるかもしれない。
⑤次の1年生は75人ほどで多いから、がんばって。
⑥ベテランの先生たちがだんだんいなくなってきているから、立て直せないと思う。だから、②のやり方をしたほうがいいと思う。
⑦特別支援の先生は「チーム、チーム」って言っているけど、担当の子しか見れていないと思う。
これを6年生が書いているんですよ。すごいでしょう。この人たちは、教職員のメンバーが大きく変わったときのリーダーだったので、これまでとは違ったこともたくさんあっただろうし、戸惑ったこともあったと思います。
だから、この人たちの言葉を聞く価値は大きいと、私は思っているんです。自分たちが書いたメッセージを改めて聞いて、感想をどうぞ。
【田口屋】 こんなにしっかり書いているとは思っていなかったのでびっくりしています。私たちが高学年になったころから、創立時からいた先生たちが転任していって、6年生のときに校長先生も代わりました。大空は他の学校とは教育方針や子どもたちの学校での過ごし方などが異なるので、新しく赴任してきた先生たちは大空に馴染むまで少し時間がかかっていたように感じました。そんな思いがあって書いたのかもしれません。
【木村】 市場校長はこのメッセージを読んで、「僕はどうしたらいいんでしょうか」と悩んでいました。だから、「こんなに子どもが育っている。幸せな学校で校長をしているやん」って伝えたことを覚えています。
全国の校長が肝に据えて、カホが6年生のときに書いたこの7つのことを基に学校づくりをしたら、どこでも「みんなの学校」をつくれると思います。
「大空小学校が世界に誇れる、とっておきの自慢は何ですか?」という問いには、タイヨウは「ゲストが来る学校」。ミナミは「地域の人とふれ合えること」と書いています。カズは「大空の全部」。
市場校長に①~⑦までの厳しい意見を突き付けたカホが書いたのは、「(子どもの)人数が少ない」。リアルでいいですね。最高やろ。
次は、タイヨウが在校生たちに向けて書いた卒業メッセージを読みますね。
「僕が伝え残したいことは、人を大切にすることです。大人も子どもも人を大切にするのは難しいけど、たった一つの約束(※3)や4つの力(※4)を生かすことによって、僕は人を大切にすることができると思います。だから、みなさんも人を大切にしてください。
もう一つ僕が伝え残したいことは、チャレンジすることです。チャレンジしたかったけど、あきらめてしまった経験が僕にはあります。だから、みなさんにはいろいろなことにチャレンジしてほしいです。チャレンジすることによって、できることもあればできないこともあるけれど、僕はみなさんにチャレンジしてほしいです」
これが、リーダー(6年生)としてタイヨウが大空に残した言葉です。
【宇榮原】 大空では、何度も人を傷つけてきました。そういう失敗の多い自分だったので、出会う人を大事にしていきたいと思うようになりました。小・中・高という時間を経て、いろんな人と出会ってきましたが、人を大切にすることは続けています。人を傷つけるという経験をしたからこそ、人を大切にしたいと思うようになったことが、大空での一番の学びかもしれません。
【木村】 カズはずっとにこにこしながらタイヨウの話を聞いていましたね。今の話を聞いて、カズはどう思った?
【中川】 日常。タイヨウだけじゃなく、自分も含めて、みんながみんな問題を起こしていました。だから、特別なことだとは思っていません。
【木村】 日常か、なるほどな。毎日いろいろなトラブルがあることが当たり前やったもんなあ。次はカズの卒業メッセージです。
「6年間で学んだことは4つの力です。なぜなら、今までつけてきたからです。中でも自分が一番高まったと思う力は、チャレンジする力だと思います。なぜなら全校道徳(※5)でみんなの前で発表したりしているからです。中学校に行っても、4つの力を高めていきたいです」
大空で学んだことで、その後の自分の人生で役に立ったことって何かありましたか?
【中川】 大空でみんなと仲良くしていたから、どんな人ともフレンドリーにコミュニケーションが取れるようになりました。仕事でも社交的にやれています。
児童数は少ないけれど、大空には個性的な子がたくさんいました。そんな同級生の全員としゃべっていましたし、全校道徳をはじめ異学年と関わる機会もたくさんありました。それから、先生たちとの距離が近かったことも大きかったと思います。
――今、発言にあった「全校道徳」について教えてください。毎週月曜の朝、全児童が講堂に集まって、そのときどきの決められたテーマについて、異学年のグループで話合いをしてきましたね。
【田口屋】 ホワイトボードの真ん中にその日のテーマを赤で書いて、左右半分に分けて、左に子どもの発表したことを黒で、右に大人の発表したことを青で書いていました。リーダー(6年生)が、グループで話し合ったことの考えの発表することになっていました。
【宇榮原】 1年生から6年生までがそれぞれ考えて、それぞれの意見を出し合うので、「こういう考えもあるんだな」とか、自分が見えていなかった角度から物事を考えることができました。意見がぶつかることもあったけれど、自分では考えもしなかった意見を知ることができて楽しかったし、成長にもつながったと思います。
【中川】 多様な意見が出ていましたね。たとえ自分と対極の考えだったとしても、頭ごなしに否定するのは違うという気持ちで参加していました。
【平】 私はあまり参加していなかったイメージがあります。グループには入るけど、リーダーとして意見を発表することはなかったです。
【木村】 ミナミはいつも少し離れたところにいて、斜めからいろんなものを観察しているようなところがありましたね。自分から積極的に発信はしないけれど、「この人はこういう考えなんだ」とか、「私とはここが違うな」とか、そういうことをいつも考えていたのではないですか?
【平】 そういうところはあったと思います。
【木村】 自分からはあまり発言しなけれど、「ミナミはどう思う?」って聞かれると、核心を突くようなことを一言で表すんです。
――6年生になったときに、校長が変わりましたが、それでもぶれずにここは変わらなったところは何ですか?
【中川】 リーダーである6年生が1年生を見るということは、変わらなかったです。
【木村】 1年生が何か困っていることはないかというのを、常に見ているのが6年生なんですね。きっとそこは変わらずにやってくれていたんだと思います。
【田口屋】 カズが言った通り、縦のつながりは変わらなかったです。私が6年生だったとき、2年生だったミクや1年生のユウキとよく関わっていました。休み時間に遊んだり、授業中、抜け出したときには追いかけたりもしました。無理矢理連れ戻すようなことはせず、一緒に逃げるかくらいの気持ちでいたと思います。(落ち着くまで)その場に一緒にいることが多かったですね。
【上田】 ミクが2年生のとき、私が学級担当(※6)でした。ミクは怒って教室を出て行ってしまうことがよくありました。クラスのみんなになぜ怒っているのかをうまく説明することができなくて、でも、腹は立つからどうにかしたいという思いがあったんだと思います。どこに行ったんだろうと探しに行くと、カホやカズたちが話を聞いてくれていることが多かったです。
教室を出てそのときに出会った6年生にマシンガンのようにしゃべっていたというイメージがあります。6年生が一緒にいるなら、そのうちすっきりして戻ってくるだろうと思っていたので、任せていました。
カホたちもミクの話を聞いてあげようという思いよりも、たまたま出会ったミクがしゃべるから「ああ、そうなん」って聞いてあげるようなスタンスだったんじゃないかと思います。
【木村】 つまり、困っている子の横にいる。
6年生のときの思い出として、低学年のミクやユウキの名前が一番に出るのは、しっかりリーダーを務めていたということ。教室から飛び出したり逃げ回ったりするミクやユウキも、この人たちとだったらつながれるんですよね。
【徳岡】 この子たちが6年生の年は、木村校長が退任されて、大空小学校が第2ステージに入っての1年目。教職員にも不安はありましたが、「校長が変わったら、大空は変わった」と言われないようにしようという思いは強かった。
大空がずっと大事にしていることは変えずに取り組みましたが、私たち大人(教職員)の失敗が多かったと思います。ときには、木村先生に相談しながら、やり抜いた1年間でした。
【大島】 この子たちの学年は、4年生の途中で転入生がたくさん入ってきて、子どもたちの関係が複雑になりました。5年生でそれがいろいろな問題となって噴出し、5年間一緒だった木村校長がいなくなって、そういう繊細な時期にリーダーとなる6年生を迎えることになりました。ですから、子どもたちも大人も不安に感じているところはあったと思います。たくさん失敗しながら、子どもたちと学び合った1年間でした。
【木村】 公立の学校は地域住民みんなのものという考えのもと、大空小学校は「みんなの学校」として、地域の人たちと一緒につくってきました。今も「みんなの学校」として存在しているのは、この人たちの学年がつなげてくれたからなんです。ときには大人に不信感をもったり、大人の本質を見抜いたりしながら、大空のリーダーの責任を果たしてくれたのだと思いますね。
【徳岡】 あの頃、ミナミとカホを含む女子6人が、何人かでくっついたり離れたりしながら対立し合っていて、例えば3人と3人に分かれたときには、1人が相手のチームにスパイとして送り込まれて、戻ってから自分のチームに報告するみたいなことを毎日やっていたよね。今、それをどう思っているのかなと思って。
【田口屋】 それはあまり覚えていないけれど、よく1対5とかに分かれていたのは覚えています。
【平】 みんなが傷つけ合っていて、お互いに嫌な思いをしていました。グループから逃げられなかったのかな。仲よくしたいのに、そのときは本当の自分の思いを言えませんでした。ちゃんと思いを言えたら、もっと仲よくできたのかなと思います。
【木村】 なるほどなあ。ここで、ミナミの卒業メッセージを読みますね。
「私が6年間学んできたことは、たった一つの約束です。今までずっと、たった一つの約束を守ることができませんでした。たった一つの約束は、人を傷つけないため、そして、自分のやったことを理解するためにあると思います。中学校に行っても、たった一つの約束を忘れないで守りたいです」
正直に書いてるやん(笑)。
【平】 でも、中学生なってからは、傷つけ合うようなことはまったくなかったし、成長できと思います。
【木村】 小学校のときにどれだけ醜いところを出しても、そこからアップデートできたら、それでいい。
教員からすると、中学や高校と比べて、小学校の子どもは一番言うことを聞かせやすいんです。その6年間を、先生の言うことを何でも「はい、はい」と聞いて、先生たちが楽をするような、先生にとってのいい子であったなら、中学や高校に行ったときに、人を傷つけるようなことを続けてしまったのではないですか。
6年のときのどろどろとしたいざこざがあったから、あの卒業メッセージにつながったし、今ミナミの口から「中学校ではそんなことなかったよ」と聞けたのだと思います。
大島や徳岡は大変だったかもしれないけど、それは給料分の仕事をしただけです(笑)。この子たちは学校の中で、思う存分ストレスを出していたんじゃないかと思います。
【中川】 学校でストレスを発散していたところはあったと思います。野球をやっていたので、監督に怒られることもあったし、そういうストレスもあったのかな。
【宇榮原】 みんな少なからずそういうところはあったと思います。
よかったのは、いい失敗をしても、よくない失敗をしても、認めてくれる環境があったこと。普通は、よくない失敗は蔑ろにされると思うけど、大空はそうではなかったです。
小学校という人生の早い段階で、失敗しても(子どもも大人も)一緒に考えて、失敗から学ぶことを経験させてくれたのはありがたかったですね。
【上田】 6年のときに大変だったのはその通りですが、私が一番覚えているのは4年のときのことです。
【木村】 学級担当をしていた先生が結婚退職をすることになったので、2学期から(上田)美穂が担当になりました。それまでは支援担当をしていて、この年、初めて学級担当になりましたね。
【上田】 はい。採用試験を受けていたときだから、まだ講師の時代ですね。年度の途中で担当になったこともあって、すごく必死でした。今だったら「もっとこういうふうにできたのに」という歯がゆい思いがたくさんあります。
【田口屋】 でも、私は4年の2学期3学期が一番楽しかったですよ。上田先生が担当だったし、仲のよい友達も学級に集まっていたので。
【上田】本当に? 嬉しくて、今、泣きそうです…。
【小国】 大空で学んだことや経験したことで、今の自分に役立っていることは何ですか?
【田口屋】 チャレンジする力です。中学・高校・大学のすべてでいろいろなことにチャレンジしていたなと思います。
中学では1年・2年と体育委員をやっていました。3年のときも立候補したけど、1票差で負けてできなかったのは残念でした。体育祭を仕切ったり、みんなの前で説明したりするような華やかな仕事だけでなく、毎回の授業において、運動の苦手な子がどうやったらみんなと一緒に参加できるかを考えることも仕事でした。体育委員をやってたくさんのことを得られたのは、立候補するというチャレンジがあったからだと思います。
高校では、国公立大学を目指すような進学コースにいました。その中で、私は週6日活動する女子バスケットボール部に所属し、小さいときからやっているダンスも続けました。親にはバスケかダンスのどちらかにしたらと言われたけれど、部活は木曜休みでダンスの練習日が木曜だったので、両方すると自分で決めました。勉強だけをしている友達が多い中でも、チャレンジする力があったから、勉強もバスケもダンスもするという選択肢を取れたのだと思います。
【平】 私もチャレンジする力です。大空ではコンサートで(演奏する楽器を決める)オーディションがあったり、コンサートではリーダーとして人前に出て話したりすることも経験しました。そういう経験があったから、中学や高校で何事にもチャレンジできたと思います。
【中川】 繰り返しになりますが、人とのつながり、コミュニケーション能力です。
中学・高校でもいろいろな人としゃべったり関わったりしてきました。会社に入ってからもいろいろな人と交流をもっていて、仕事だけでなく、休みの日に野球をすることもあります。誰とでもコミュニケーションを取れるようになったことは大きいと思います。
【宇榮原】 僕もチャレンジする力だと思います。
大空での経験を生かして、中学・高校といろんな挑戦をしてきました。失敗のほうが多かったけれど、自分を認めることが大事なんじゃないかと思います。失敗しても学びがあるというのは、大空で学んだことです。
今、英語の勉強もしているのですが、検定に落ちたことがあります。次、成功するにはどうしたらいいだろうかとまず自分で考えて、他の人の意見も聞いたうえで、自分の考えをもう一度落ち着いて考える。こういう行動ができるようになったのは、全校道徳を経験したからだと思います。そして、自分の考えを確かなものにして、もう一度チャレンジする、この繰り返しです。
その結果、検定にも受かりましたし、今ではアメリカ人の友達もできました。最初は自分の英語力に自信がなかったけれど、友達になりたいという思いがあったので、失敗しながらコミュニケーションを取っていくうちに、少しずつ仲よくなりました。同時に、自分の英語力に自信も出てきました。
――みなさんの今後の夢や目標について教えてください。
【平】 保育士を目指しています。子どものことを一番に理解してあげられる保育士になりたいです。みんなの前に出て話すことは苦手なので、がんばって克服しようとしているところです。
【田口屋】 大学の看護学部に通っていて、看護師を目指しています。大きな夢は、看護部長になることです。従妹が福岡の済生会総合病院で看護部長をやっているので、自分は大阪の済生会の病院で看護部長になれたらいいなと思っています。
直近の目標は、手話検定試験に合格することです。まだ動画などを見ながら勉強を始めたばかりで、五十音を覚えたのと、簡単な挨拶と自己紹介ができるようになったところです。患者さんの中には耳の不自由な方もいるので、筆談だけではなく手話でもコミュニケーションを取れれば、看護師としての可能性が広がるのではないかと思っています。
【中川】 設計製図会社で、農機を担当しています。自分で企画・設計した田植機が製品化されて、実際に農場で使ってもらえるようになることが目標です。
【宇榮原】 みんなに比べてまだ自分には現実的な目標はないのですが、今ある環境や自分の周りにいる人を大切にしたいという思いはあります。いろんなことにチャレンジしながら、夢を探しているところです。
【小国】 この座談会は今回で3回目なのですが、今までで一番大空小学校の教育のことを濃密に記憶されていて、それが今の生活にいろいろな形で生きているということを聞かせていただきました。
だけど、小学校時代には必ずしもうまくいっていたわけではなかった。校長先生の交代があったり、ベテランの先生が転任されたり、それから転入生が多かったり、学校としての変革期であったということも少なからず影響していたのだろうと思います。
日常的にトラブルがあって、先生からしても必ずしも十分なことができたとは思えないような学年だったと認識されていて、本人たちも何が原因でうまくいかなかったのかはわからないけれど、いろんな壁にぶつかった。
だけど、みなさんのお話から、今日が成功していないからといって、その後それが悪い体験として残るわけではないということを知ることができました。
大人から見たときに、子どもたちがうまくいっていなくても、そのときに学んでいることはあるということを教えていただきました。ある意味、うまくいっていないその時期が、みなさんにとっての原体験になっているというお話を伺えたことは大きかったです。
そして、もう一つ大きいのは、様々な壁にぶつかっている中で、大人が常に見守ってくれたり、味方としてそばにいてくれたり、そういうことを濃密に体験されたのではないかと感じました。
【木村】2021年度の小中学生の不登校が24万人を超えたという報道がありました。文部科学省の調査によると、不登校もいじめも過去最多だったそうです。
今日、この子たちが話してくれた日常が学校現場にあれば、つまり、どの子も安心できる環境が保障されていれば、どんな個性的な子でも学校に来られて、学校でトラブルを起こせるわけですよね。学校に来てトラブルを起こしたら、まさにタイヨウが言ったように、その失敗をやり直したら成功体験になる。
カズが自分の思いを相手に伝えることができないときに、やっぱり閉じこもるわけです。みんなが心配してもカズはそこから動かないで何もしゃべらないという経験をたくさんしてきました。でも、そのカズが大空の6年間で一番学んだのは、有効な関係を築くためのコミュケーション能力だと言いました。
少し離れたところから冷めた目で斜めにものを見ていて、人前に出て何かをやるというタイプではなかったミナミが、保育士になりたい、と言っています。
市場校長に7つの厳しい意見をぶつけたカホは、手話検定を受けて、いずれは看護部長になりたいと言っています。
自分自身が最後の1年を見届けられなかったということもあって、私はずっと、この人たちが一番気になっていました。今日、再会できて、こんなに成長した姿を見ることができて、本当に幸せです。
【徳岡】こうして大人になった卒業生たちと再会して改めて大事だと思ったのは、小学校生活の中でいかに自分らしさを出せるかということ。
4人は小学校時代に自分らしさを出し切っていたからこそ、中学・高校と上がるにつれいろいろなことができるようになったんだろうなと感じました。子どもたちが自分らしさを出せるような環境をつくることは、今、私にもできることなので、そこは意識してやっていきたいと思います。
【木村】 学校で子どもたちが自分らしく生きていたとき、困るのは型にはめたいと思う教師です。
でも、大空の第2ステージをつくろうとしていた徳岡も大島も上田も、規律やルールを子どもたちに押し付けるような、教師の権力を行使するようなことはしなかった。
だから、卒業生たちの今日の言葉になったんだと思います。
註
※1 毎月開催。全校児童が講堂に集まり、その月に誕生日を迎える子をお祝いする。誕生月の子どもは一人一人、自分の体験や思いを語る。
※2 みんながつくるみんなのコンサートとして、年3回(創立記念コンサート、ふれあいコンサート、ありがとうコンサート)行われる。担当する楽器はオーディションで決まる。単なる音楽発表会ではなく、音楽を通じて人とふれあい、コンサートをつくる役割を一人一人が担うことを目的にしている。
※3 「自分がされていやなことは人にしない・言わない」という約束。大人も子どもも守れなかったときは、「やり直し」をする。
※4 10年後の予測できない社会に生きる子どもに必要な力として、「4つの力」(人を大切にする力、自分の考えを持つ力、自分を表現する力、チャレンジする力)を身に付けることを目指してきた。
※5 毎週開催。「人権って何?」などの正解のないテーマについて、異学年の小グループをつくり対話し考える。大人は大人で小グループをつくり、同じように対話する。
※6 大空小学校の基本は、全教職員が全児童を見ること。学級担任制ではなく、「学級担当」と呼ばれる。担当なので、自分のできないこと・不得意なことは他の人に任せる。



.png)