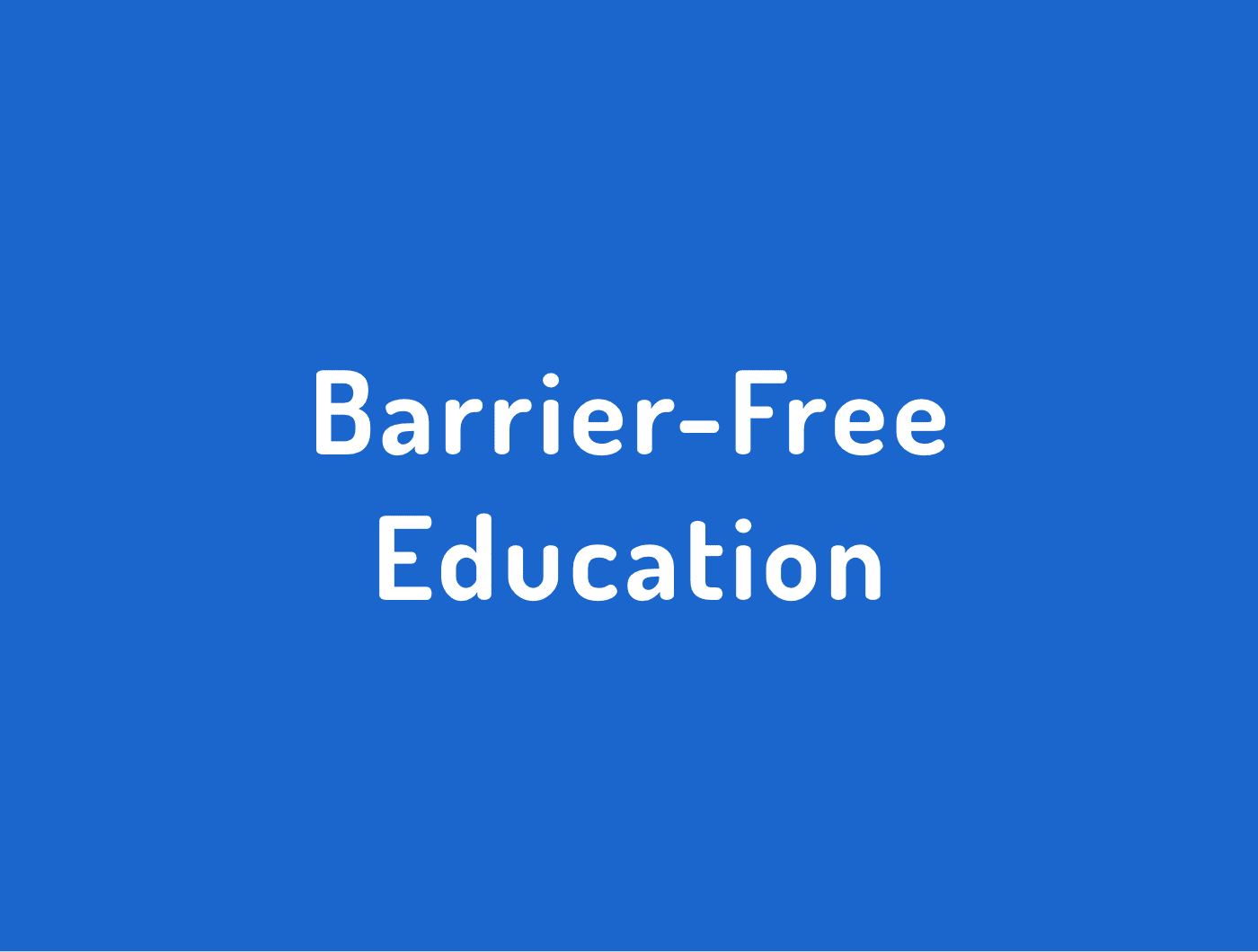「たくまく~ん」と遠くからお友だちが呼んでいる。嬉しそうに走り出すわが子の姿を見守りながら、『ありがたいなぁ』『こんな景色をずっと見ていたいな…』と幸せな気持ちに包まれる。そして、『たっくん、がんばれ~!』『楽しい時間を過ごしてね』と心の中でつぶやく。
こんな気持ちで子どもの背中を見守るのは、何もたくまに限らず、上の子たちもおんなじ。もうだいぶ大きくなっているけれど、未だにそんな気持ちで背中を見守っている。
そんな、上の子たちと変わらない子育てだが、たくまについては“ダウン症”という特徴をもってるがゆえの様々な思いや、上の子たちとは異なる体験があるのも事実だ。その多くが本当に素晴らしい体験である一方で、時に大きな葛藤を感じざるを得ない体験があることも否めない。しかし、それら全てが私に大きな気づきを与え、沢山の仲間や繋がりを運んできてくれる。私は、たくまで広がっていく新たな世界を楽しませてもらっている。
テラスから“こっそり”のぞいた子どもの世界 ~保育園時代~
たくまは現在、地域のふつう級に通う小学校2年生の男の子である。
保育園の恵まれた環境で4年間を過ごし、いよいよ小学校入学までわずかとなったころ、私は小学校入学にむけた不安でいっぱいだった。
『入学したらどうなるのだろう?』『集団の中でどんなふうに過ごしていけるのだろうか??』
地域のふつう級に就学を決めたものの、不安がつきない。入学予定の小学校からは、「こういうことは出来るのですか?」「こんな時は、どうしているのですか?」「どう対応すれば伝わるのですか?」と次々質問がくるが、家での様子や少人数でのかかわりは分かるものの、親のいない“集団”の中でどのように過ごしているのか、なかなか答えられないでいた。
保育園での様子を見ることができるのも、あとわずか。私は、園にお願いし、数日間 2階のテラスやお隣のお部屋からこっそりとたっくんの様子を見る機会を得た。
園庭遊びの時間となり、次々と子どもたちが靴に履き替えて園庭に出てきた。たくまは自分で靴を履くと、仲良しのHちゃんが履き終わるのを見守っていた。Hちゃんが履き終わると、「いこっ!」と一緒に走りだす。いつも待たせるだけかと思っていたのに、たっくん、意外に早いっ!
遊具で遊び、次はどろんこ遊びがはじまる。しばらく遊ぶと、手をとめ水道へ走るたっくん。大きいタライにお水を汲みはじめた。『あ~、あんなに水をくんで……いいのかな』とハラハラしてると、「Bちゃ~ん! おみずよ~」と、抱えきれないほどの大きなタライを一生懸命お砂場へと運んでいった。小さなバケツで何往復もお水を運んでいる女の子の姿を見て、お水を汲みに行ったのだ。「わぁ! たっくん、ありがとう!」と喜んでもらい、また皆でどろんこ遊びがはじまった。そんな様子に『おぉ、なかなかの紳士!』とまたまたびっくり。
そんな、クラスのお友だちと当たり前に一緒に遊んでいる姿を見ながら、『おともだちに迷惑かけちゃってないかな…』『ひとりで困ったりしてないかな…』と、心のどこかでつい心配ばかりしていた自分に気付かされる。たくまはお世話になるばかりではないこと、4年間の日々の中で築いてきたクラスのお友だちとの絆を感じ、溢れる涙を止められずに、ひとりテラスの影に隠れながらわが子の姿を見守った。そして、『いま、こんなにもみんなの中に溶け込んでいる。小学生になるから…というだけで、なんでばっさり分けなければいけないの?そんなの私にはできないよ…』と改めて思ったのだった。
後日、卒園時の園長先生のことばにその日の風景が蘇った。「たくまくんがいると、みんなニコニコになります。たくまくんがいると、みんなやさしくなります。それは、たくまくんがいつもニコニコで、みんなにやさしいからです」とのメッセージ。そう、たくまは与えられるだけの存在ではなく、笑顔も優しさも与えられる存在なのだ。家ではあたりまえに感じていることなのに…。園長先生のことばに、改めて大切なことに気づかされる。また、卒園を控えたある日。クラスのママが、「たっくんが一緒で良かった。たっくんがいたおかげで大人も子どもたちもどれだけ多くのことを学べたか。“助ける”とか“優しくする”とかじゃないんだよね。当たり前なんだけど、本当に対等で。同じ仲間として過ごせたことを本当に感謝してる。」と涙ながらに伝えてくれた。楽しく立ち話することはあっても特に深い話をする機会もなく過ごしてきたが、こんなふうに想ってくれ、それを伝えてくれたことに、またまた涙が溢れ出た。クラスのおともだち、ママ・パパたち、先生方に温かく見守っていただき、どれだけ有難く、どんなに安心して過ごせたことだろう。たくまや私がずっと笑顔でいられたのは周りのみんなのおかげだ。思えば、保育園のスタートでも色々心配したが、こんなにも素晴らしい時間の中で大きく成長していたのだった。

障がいのある子の多くは、特別支援学校・支援学級に就学していく。そして、「保育園(幼稚園)では、みんなと一緒に楽しく過ごせていた。まさにインクルーシブだったね」と話す。なぜ、小学校にあがる瞬間に、分けられてしまうのだろうか?日々において、ともに過ごすということが出来ない環境が用意されているのだろうか?年齢があがるから?小学校は勉強する場所だから?もっと適した環境のほうが成長する?・・・もしそうだとしても、今のこの自然な環境を、ともに過ごす時間を大切にしたい…。そんな思いは今でも続いている。
また我が家においては、小学校入学と同時に分けられることへの違和感だけが、ふつう級を選択した理由ではない。「小学校、どうする?」という話が本格的に出始めた頃から、支援級への送迎が夫婦の重要な課題になっていた。駅まで徒歩、電車2駅、さらに徒歩…。自転車? 今はいいけど大きくなったら乗せられないよね?そこまでかけて支援級に行かせたいだろうか?行かせなくてはいけないだろうか?実質的に送迎が負担になることは目に見えており、話し合いは先延ばしになっていた。
そんな中、10歳のお兄ちゃんが「えっ、なんで?なんで、一緒の学校に行けないの??」と言ってきた。そして、「たっくん、あまりおしゃべりできないじゃない? 〇〇小に行っても困るかもしれないし…」という私に、「えっ、そう? だいたい言ってること分かるじゃん。大丈夫だよ」とあっさり。そんなセリフに思わず笑ってしまい、「絶対に同じ学校がいい!ぼくが一緒に行くから。ねっ!」という兄の言葉に大きく背中を押されていた。入学後、優しさが深みを増し、とても大きく成長していったお兄ちゃんの姿に、『可愛い大好きな弟と一緒の学校に通いたい』という思いを大切にして良かったと思っている。
新たな世界をきずく、子どものちから ~小学校入学後~
ふつう級に入学し、私は『焦らない』『まずは学校に行けていれば良し』ということを意識していた。
授業が中心の学校生活において、保育園のようなお友だち関係は難しいかもしれない。それでも、一緒にその場にいることの大切さがきっとある。そして、たくまにはたくまのペースがある。ゆっくりゆっくり、ゆっくりゆっくり・・・。
思ったいたより穏やかに過ごした一年生を終えて二年生になると、慣れと自我の成長からか「ふざけ過ぎて手が出てしまいます」と言われるようになる。ある日、連絡帳に『お友だちの顔をたたいてしまい、保健室にいきました。注意しています』と、先生にしては珍しく、“困った行動”と“注意したこと”がたくさん記載してあった。ケガには至らずほっとしたが、たくまの気持ちもお友だちの様子も気になり、翌朝一緒に登校することにした。
朝、いつになく、ぐずぐずのたっくん。玄関先でしゃがみ込み、動こうとしない。気持ちを説明できないことへのもどかしさと切なさ、無理をさせてしまっているのだろうか、学校で居場所がないのだろうか、色々な思いが押し寄せてくる…。
すると、そこへ「あっ、やっぱりここだ!」「たっく~ん! 迎えにきたよ!!」と男の子3人がこちらに向かって歩いてきたのだ。いつもは、わが家の前は通らず、少し先で合流するルートのクラスメイトたち。一人は、前日に保健室に行ったお友だちだ。たくまは急にげんきな笑顔になってお友だちの輪に入り、一緒に歩き始めた。嬉しさのあまり、子犬のようにくっつくたくまに、「たっくん、うれしい?!」と笑顔の3人。たくまは私の存在を気にも留めず、皆と登校していった。私は、胸がいっぱいになり溢れる涙を隠しながら、4人が登校する姿を後ろから見守った。
家まで来てくれたのはその時だけ。翌日からはいつもの地点でたまたま会えば「おはよう!」と合流する。2年生男子、『心配だったから』とか『気になって』なんて言葉はない。そんなことば以上に、いや、ことばがないからこそ余計に優しさと絆が伝わってきて、子どもの世界に感動し、私にとって一生忘れられない光景になった。

その日の夕方、私は入学して初めてクラスのママに謝罪の連絡をいれた。緊張と、落ち込む気持ちを抑えつつ「痛い思いをさせてしまってすみません…」と謝る私に、そのママは「(こどもに)『それで、あなたはたっくんのことどう思ったの?』と聞いたら、『だいすきだよっ!』と力強く言ってまして(笑)『じゃあ大丈夫だね!』と思って」と明るく伝えてくれた。もう一人の方も、お子さんから聞いている学校の様子を教えてくれ、楽しく過ごしていることを伝えてくれた。感謝と共に、私はこんなふうに子育てできているだろうか、こんなステキな人になれるだろうか…と深く考える時間となった。そんなママたちの優しさを感じながら、『どうか、お友だちや(そしてたっくん自身も)傷つくようなことが起こりませんように…』と日々祈るような気持ちでいる。
『もっと子どもを信じてあげて』というのは、入学前「教室を出ていったら、どうしたらいいのでしょう?」と心配する私に伝えてくれた先輩ママのことばだ。実際、私の心配をよそに、たくまは一度も教室から出ていっていない。ひらがな一字さえ書けなかったのに連絡帳を板書するようになり、ペーパーテストが配られれば誰よりも早くお名前を書くようになった。体育が終わると着替え、自ら校庭に出て、時にみんなのドッチボールに交じり遊んでいる。これらはクラスのお友だちあってこそで、私が想像もできなかった姿だ。
同じ保育園卒の子がいない中でのスタートだったが、「2年生でも同じクラスになりたい!」「一緒に遊べる?」と声をかけてもらったり、たくさんのお手紙をもらってきたことにもとても驚いた。さらに、あの日の朝の光景。気づけば、たくまは自分自身で新しい世界を築き、皆の中で成長していた。子どもは子どもの世界で生きているのだ…と改めて気づかされたのだった。
はじめて感じた「社会の障壁」~就学にむけた一年をふりかえる~
生まれたわが子に障がいがあることで、当初、私が一番恐れていたのは社会の障壁や偏見であったように思う。しかし、実際はそんなことを感じることは殆どないに等しく、通院や療育といった実質的な大変さを感じることはあったとしても、とても温かい世界で生きていた。ところが、就学相談がはじまると、社会の障壁、偏見とはこういうことか…と痛感することが一気に増え、少し先行く先輩ママさんたちが「来年は就学相談だね…。がんばれ!」と口々にエールを送ってくれていた意味がわかるようになっていった。
いわゆる“就学判定”は、初めて会った方との短い面談において“できなかったこと”を次々に説明され、「お子さんにとって…」「お子さんが成長するために」「楽しく過ごすために」そのために「あなたのお子さんには手厚い支援が必要」と伝えられて、特別支援学校が妥当であると告げられるものだった。ふつう級を視野にいれていた私は、親として子どものことを考えられていないのか、ちゃんと見ようとしていないだけなのだろうか…と、茫然とした。また、複数回にわたる校長面談では、たくまの入学がウェルカムでないことが十二分に伝わってきた。さらに支援学校の保護者の方から「優秀なのね。でも、子どもの心は傷ついたら元に戻りませんよ」と言われるなど、ふつう級選択はとてもイレギュラーなのだと痛感した。
それでも、なぜふつう級に挑戦しよう(挑戦という言葉もおかしいけれど…)と思ったのだろう。
・すでに成人されてる方の保護者が「ふつう級で過ごしたあの2年間は、今でも宝物」と言っていた
・尊敬している先輩ママが「この子を成長させよう、というだけではいくらやっても限界がある。周りも一緒に成長していくことが大切なのよ」と話されていた
・ふつう級のママの「少しでも『行かせてみようかな…』と思うならぜひ行ってみて。1年でもいいじゃない。半年でも、もしムリだと思ったら1か月でもいいじゃない」という言葉に、心のハードルがさがった
・ふつう級就学にむけた道筋を示してくれる心強い先輩がいらした。そんなたくさんの出会いが私たち夫婦の背中を押してくれ、大きな支えとなっていった。
子どもが新たな環境へと移る時、どんな子でも親は少なからず不安と期待が入り混じるものである。子どもに障がいがあるとなれば、その不安はなおさらだ。特別な環境が準備され、『そこに行けばお子さんは安心して過ごせますよ』『そのほうが成長しますよ』と言われたら、そちらを選ぶだろう…。
もちろん、それだけでなく、親は様々なことを考え選択しているし、それらが事実である面もあるかもしれない。しかし、もし、地域の学校から「安心して入学してきてくださいね」「不安はあるかもしれませんが、みんなでやっていきましょう!」と言ってもらえ、多様性への理解と適切な配慮が期待でき、そこに前を歩く同じ仲間がいたら…?? ふつう級を選択する人はもっと多いのではないだろうか?
どちらを選択するにしても、地域の学校はそういうスタンスであって欲しい、そんな世の中になって欲しいと切に願う。特に就学相談においては、親が安心して相談でき、偏りのない情報を得、誘導されることなく、納得して意思決定できる。そして、必要に応じ就学先の環境を整えるための支援へと繋がっていく。そのための相談支援であるべきだと強く思っている。
「合理的配慮」ってなんだろう??
「合理的配慮は、親から求めるものです」「人とお金がかかることはムリです」と教育委の方は言うけれど、それがまた難しい。私も素人だし、どんな配慮があればいいのか分からない。一般の保護者が、法的な根拠を基に行政や学校に主張するというのはムリがあると思う。頑張って伝えなければ先に進まないことも多いのに、うるさい親だと思われるのも切ない。入学後も子どもや親が支えられるシステムがあったらいいのに…。そんな中、同じ道を歩く先輩ママや、インクルーシブな社会の実現にむけ活動されている方々からの示唆は大きな気づきと学びをくれ、私を支えてくれている。
入学後、分からないながらも合理的配慮について色々いろいろ考えてみたけれど、ベースは「思いやり」なんだろうな、と思う。困っていたり戸惑っている人がいたら、手を差し伸べる優しさ。合理的配慮なんて言葉が必要ないくらい当たり前になればいい。そう思ったりするけれど、実際の具体的な事例や助言があったら、やっぱりとても助かる。
例えば、特別支援教育に携わっていた教育委の先生は、たくまの入学式にむけちょっとした工夫を伝えてくれた。入学式用に設営された体育館での前日の予行練習である。たくまの椅子には小さなリボンがしてあり、“ここが自分の席”と分かる。音楽の先生が伴奏してくれ、たくまは入場と着席を体験した。コロナによる緊急事態宣言により、校庭での「あおぞら入学式」に変更になったが、きっとたくまにとって安心に繋がっていたと思う。そして、何より親の私が安心した。体育館でちょっと緊張ぎみに先生のあとを行進し、しっかり着席&礼ができたたくまの予行練習。前日の忙しい中、時間を作ってくれ笑顔で見守ってくれた先生方。不安でいっぱいだった私にとって忘れられない思い出となった。
特別支援で培った感覚や専門的知識をふつう級でも生かせるように助言してもらえたら、「わざ」のようなアイデアをふつう級に散りばめて頂けたら、きっと本人はもちろん現場の先生方も助かるだろう。さらにはすべての子どもにとっても良い影響があるのではないだろうか。
また、「合理的配慮」とは少し異なる話になるかもしれないが、「配慮」と「支援をすること」はイコールではないということも意識していきたいと思っている。
たくまの担任となった先生は、ちょっとキャラの濃い熱血なY先生だ。卒園間近に保育園に様子を見にきてくださった先生で、その際「心配いらないですよ」と力強くおっしゃった。おそらく他の先生だったらそんな風な見立てにならなかったのでは…? 私は先生の言葉に、安心したような、信じられないような気持ちでいた。
入学し、私にとっては手探りのような気持ちで始まった学校生活。Y先生とは本当にたくさんのお話をした。その中で、「一番、意識しているのは“特別扱いしない”ことです」という言葉が非常に印象的である。
たくまには特定の支援員がつかなかったのだが、入学当初は、ほぼたくまの教室にいてくださる支援の方がいらした。Y先生は、たくまがどの程度の支援が必要か見極め、きめ細やかに支援の方に伝え、支援員やお友だちが必要以上の手出しをしないことにとても気を配っていた。特別扱いしないことを意識しつつ、同時に、どうすれば仲間としてクラスで共に過ごせるかの工夫を色々と考え、実行してくれていたのだと思う。現在、たくまに支援員はついておらず、時々お友だちに助けてもらいながらも当たり前に皆と一緒に学校生活を送っている。クラスに馴染み、周りのお友だちも絶妙なタイミングでたくまを気にかけてくれているのは、Y先生の感覚と、作り上げてくれた空気、先生に合わせて支援の手を入れたり緩めたりしてくださった支援員の方のおかげであろう。何よりも先生がたくまのことを楽しみ、成長を喜んでくれているのがとても嬉しい。たくまがめげることなく色々なことに取り組み、大きく成長できているのは、Y先生はじめ学校の先生方、入学当初ついてくださった支援の方、そして何よりクラスのお友だちのおかげであると感じている。
おとなの変化と、変わらない子どもたちと。
入学し数か月経った頃、校長先生が「がんばってますよー! 本当によくがんばってます」と私に伝えてくれた。入学前の面談からは想像できなかった言葉である。私は、『きっと私ほどではないにしろ、学校や学童の先生方も色々イメージがつかず、心配があったからこその反応もあったんだろうな』と思うようになった。つい先日、私は「たくまが入学してから、たくまのイメージって変わったりしましたか?」と校長先生に質問してみた。校長先生は「変わりましたねぇ! 入学する前は集団の中でどんなふうになっていくか想像できなかったですから。やはり、何かあったら…と思いますし、どうしても心配になることを先に考えますからね」と話して下さった。そんな言葉に、入学のその先を体験することができて良かったと思ったのだった。時折交わす短い会話でも、さすが長年子ども達を見てきている…と感じる一言を頂くことも多い。今は、“学校の子どもの一員”としてたくまを見守ってくれていると感じている。
担任の先生は、初めての運動会の後、しみじみとこんなふうに話してくれた。
「限界は絶対にあるんだと思うんですよね。でもその限界は、僕や周りや、もしかするとお母さんが思ってるところともまた違う所にあるのかもしれないですねぇ……」
子どもたちはどうだろうか。私は入学してから「なんで、たっくんは~~なの?」と聞かれたことが一度もない。学童の先生も、「毎年、支援学校から学童に来ているお友だちについて『なんであの子は~なの?』と聞く子が多いけれど、そういえば、たくまくんについては聞かれたことがないです。学校で一緒にいるからかしら?」と話していた。
「たっくん、こんなことが出来るようになったんだよ!」「たっくんは、こう思ってると思うよ!」と私に教えてくれる子どもたちの存在に、私はとても助けられている。
どんな子でも個性豊かに輝くいのち。お互いの違いを自然に受け入れながら育った子どもたちが大人になった社会は、きっと今よりもっと生きやすく、豊かな世界に違いない。そんな願いを抱きつつ、これからも『ともに過ごす』を大切に、たくまの背中を応援したいと思っている。
きょうだいのおもい
たくまが生まれ一年近く経ち、長女に初めて「たくま君はゆっくり育つんだって」と伝えた時のこと。
「知ってるよ。赤ちゃんっていろんな子がいるでしょ。お腹にくる時に『たくま君はそうやってつくりましたよぉ』って神様が言ってたから」との言葉にびっくりした。また、「目が見えないとか、歩けないとか、神様はなんでそういう子をつくるのかしら…」という私に、「それはね、例えば車いすだったら、どうやったらいろんなことができるだろうとか、どうやったら周りの人に手助けしてもらえるだろうって考えるでしょ。本人が頑張ることや工夫を知るためなの。そして、周りの人は、その人がどうやったら頑張れるか、どうやったら助けてあげられるかって考えるでしょ?周りの人が優しさや工夫を学ぶためだよ」と答えてくれた。
それから7年が経ち、中学生になった長女は「区長の手紙」コーナーに以下の投稿をしていた。
「私は、弟が生まれるまで、弟のような障がいのある子が学校にいないことを特に疑問に感じていませんでした。お友だちの妹で自閉症の子が遠くの支援学級に入学した時も、寂しかったけど仕方ないと思ったし、“障がいがある子は他の学校に行くもの”という先入観があったのだと思います。以前、クラスメイトに『お前の弟、障がいがあるんだってな。お大事な』と言われたことがあり、“お大事に”という言葉にとてもびっくりしたことがあります。いじわるではなく、優しい気持ちで言ってくれていたので、本当に知らないだけなんだと思いました。私も知らなければ、同じことを言っていたかもしれません。今は、たくさんの人に、弟のようにダウン症がある子たちの存在や、可愛さを知って欲しいと思っています。(略)一緒に過ごせたら、もっともっとこの子たちの魅力がわかるし、周りの人も自然に接することができるようになると思うから」と。
それに対し教育委から返信をもらえたことを喜びながら、続けてこう言った。
「私は、たっくんがダウン症なのを何か思ったことは本当に一度もないの。たっくんがダウン症で全然いい。でも、世の中のそういう見方がなくなったらいいな、ダウン症はこういう感じなんだって自然に受け入れてくれて、理解してくれて、当たり前になったらいいな…と思うから、皆に知って欲しいし、そういう偏見?っていうの?よく分からないけど、そういうのがなくなるんだったら、そのためにできることは何でもしようって思ってる」と話した。
また、あるアンケートで「障がいのあるきょうだいについて、どう思いますか?」という問いがあり、私が(少し表現を変えて)質問した時のこと。お兄ちゃんの答えは「べつに」だった。そして、「…っていうか、障がいがあるとかないとか関係ないだろ。たっくんはたっくんだろ」と付け加えた。私が質問を変えて「たっくんのことどう思う?」と聞くと「めっちゃ可愛い!」とげんきに答えてくれたのだった。
きょうだいにはきょうだいの思いがあるという。年齢によって受け止め方が変化することもあるのかもしれない。けれども、こんなふうに弟を大切に想っている二人を誇りに思う。これからもこの子たちの思いが大切に守られていく社会であって欲しいと願う。

地域の優しさに見守られて
たくまは、登下校や学童への移動に、移動支援や移動ボランティア制度を利用している。入学前、これらの人材確保は大きな課題であったが、現在、ご協力くださる方々のおかげで私は安心して日々を過ごすことができている。
そのうちの数人は、私が“ダメ元…”と勇気を出して声をかけたママ友や顔見知りのご近所の方だ。有難いことに、ガイドヘルパーの資格まで取得してくださり、一端を担ってくれている。さらに、その姿を見ていた娘さんが同じく資格を取得してくれた時には、想像もしない出来事に感動で胸がいっぱいになった。学業の合間にたくまを可愛がってくれ、たくまもとっても嬉しそう!
温かい気持ちで私たち親子に寄り添ってくれ、たくまだけでなくクラスメイトの様子なども伝えてくれる。そんな優しい存在に地域で見守られている安心感。付き添いのための時間を空け、変わらずに支援を続けてくださることはとても大変なことだろう。なのに、皆さん口々に「たっくんに、げんきをもらっている」「とても大切なことを学ばせてもらっているのよ」とおっしゃってくださるのだ。たくまの存在は、子どものちからは、本当にすごいな、と思う。そんな方々に尊敬する思いを感じながら、人としての在り方を考えさせられる。
私は、たくまを通して出会う人たちからたくさんの学びをもらっている。

広がる世界を楽しみながら
子どもは様々な体験をしながら成長していくし、親は色々と心配したり気を揉んだりするものだ。さらに障がいがあるとなるとなおさらだろう。しかし、その心配は知らないからゆえの周囲の無理解や、社会システムといった環境からくるものが多いのではないだろうか。そこをどう整えるか、親のエゴになっていないか、ということが常に頭の中にある。こんな気持ちを抱かずに、当たり前にインクルーシブな社会だったらいいなと思う。“インクルーシブ”なんてことばはいらなくなるくらい当たり前に…。
しかし、そんなふうに時に大変さや葛藤がありつつも、私はそれ以上の感動と、楽しさと、たくさんの素晴らしい繋がりをたくまからもらっている。家族みんながたくまのおかげで大笑いし、優しい気持ちになり、癒されている。たくまが運んでくる出会いは本当に素晴らしく、人生の宝物となり、世界はどんどん広がっていて、ワクワクするような時間をたくさん体験させてもらっている。
これからも次への階段を上るたび、私はドキドキと色々な心配をするのだろう。
その度に親の心配を裏切り、たくましく成長していってくれるわが子の姿を、これからも存分に楽しんでいきたいと思う。『ともに過ごす』その先に、いまよりもっと成熟した社会があり、誰もが自分のもっている“ちから”を生かして楽しく過ごせる未来があることを祈りながら・・・。



.png)