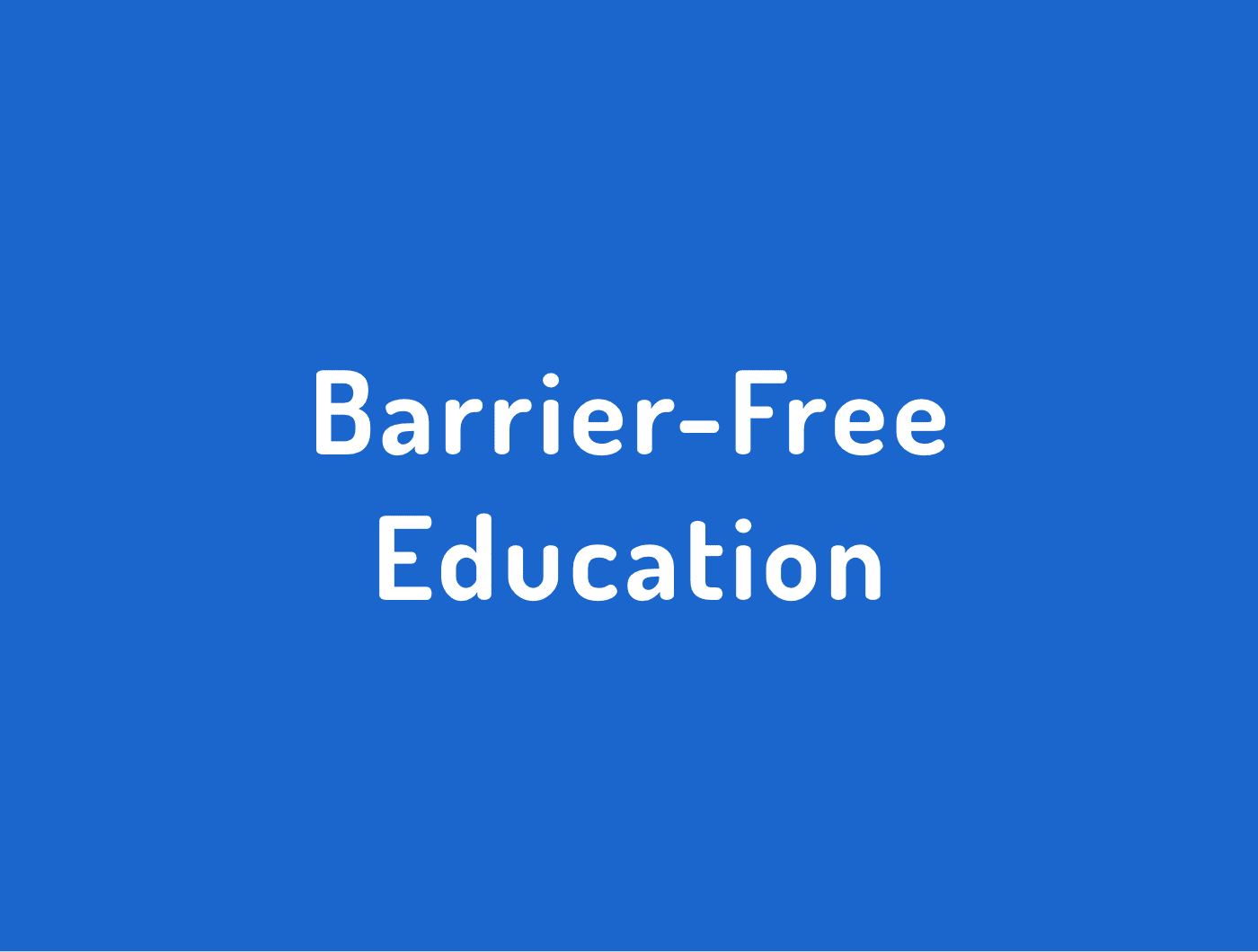<悲しみからの、療育時代>
私達は東京目黒区在住、娘めぐみはダウン症。私は山形生まれで小学校には特殊学級があったが、学級の名前を知っている位でどんなところか全く知らなかった。ダウン症と言われて、何故かそこと結びついて、そんな知らない世界に行ってしまうのだと思い、悲しくなった記憶がある。
しかし、泣いてばかりはいられず、母子手帳についていた葉書で「ダウン症なのでいろいろと教えてください」と送ったら、保健師から連絡がきて訪問を受けて目黒区立の療育園に通うことになった。10ヶ月の4月から週1で2年、翌年の3年保育の保育園生活に備えて1年は毎日、保育園が始まると週1で3年の計6年母子通園をした。出産後いろいろ調べて辿り着いたダウン症協会の相談員から「成長はゆっくりだけど辿る順番は健常児とかわらない」という心温まる手紙をもらい、2人の兄達と同じように育てていこうと思った。
療育で出会った保護者と就学についての学習会等でいろいろ考えた。就学相談は相談とは名ばかりで就学先の判定をされて普通級に行き難い事や、保護者の心を傷つける言動が横行していることを知り、教育委員会と話し合いをした。
〈就学まで〉
保育園の方が身辺自立は進むと思い、区立保育園に3年通った。個別ではなく全体に付くと言われた加配の保育士がいて、特に心配することもなく、優しく愛に溢れた保育士の方々に育まれ、少しずつできる事も増えた。お友達がやる事を観察し、次は自分もやってみようというのは「子どもは子どもの中で育つ」にピッタリな性格だった。お友達との関係も仲良く絵本を見たり等一緒に遊ぶこともあれば、1人になりたかったり自分でやりたくて、お友達と喧嘩になったりと様々。近所のスーパーで固まって困っていた時、保育園のお兄さんに「めぐちゃん!」と声をかけられると今迄固まってたとは思えないような動きをして、異年齢との関わりもあるんだなぁとわかった。大人が言うより子ども同士のほうが素直になれたりなれなかったり。
小学校をどうするか、私の中では保育園に入った時からほぼ決まっていて、その思いが強くなる毎日。長男のクラスには中学校まで一緒の男子と3年生迄学童も一緒だった女子の2人の自閉症のお子さんがいた。その事がめぐみも普通級にいけるのではと思わせ、就学を考える真っ盛りの長男達が20歳頃、自閉症の女の子のお父さんが急死されてお通夜・告別式その後の集まりの時に学童も一緒だった女子達がその子に寄り添う姿がその思いを加速させた。「知ってる」「同級生」ってこういうふうになれるんだと。
また、就学に向けていろいろな経験談等の話を聞く中で地域の学校に通っていると、買い物や散歩をしていると「アッ、◯◯ちゃん!」とよく声を掛けられるという話を何回か聞いて、地域に知ってる人がいた方が率直に心強いと思った。
<小学校入学〜>
就学相談を受けたら、判定は「支援級」。以前から普通級希望だと言っていたし、教育委員会との話合いで就学相談は就学先の判定会ではなく、決めた就学先でどんな支援をしたら良いかの相談が本来ではないか等々と申入れしていた。そうしたらあっさり「一回やってみますか」言われ、すんなり地域の普通級の就学通知が来た。
しかし、学校にあいさつに行くと、校長からいきなり「付き添いますね」と言われ、即座に「できません」と答えたので少し険悪なムードに。その時養護教諭と特別支援教育コーディネーターから、「お母さんができる日だけでも付き添ってもらえれば」と言われ、週1付添を4年迄続けた。本来学校の責任で行うべきことを親に肩代わりさせるのは筋が違うし、それよりも何よりも「普通級ではこんなにできない」事を親に自覚させようとしてるのが嫌だった。校長の対応と比して他の2人の先生があまりに優しく、流れで不覚にも受けてしまったが、普通なら見られない運動会や学芸会等学校行事の練習を近くで見る事ができた。学校に行くと娘の様子がわかるので毎回保健室で養護教諭と話していた。付添ではなく、障害の有無に関わらず子どもの様子をいつでも見にきていいよとなれば親もどんなに気が楽だろうと思った。
1年は区外から転任してきた担任で娘ができない事をよく連絡してきて夏休み前には私もだいぶまいっていた。その頃PTAの家庭教育学級という保護者向けの学習会を開催する活動を引き受けて知り合った方に障害児を普通学級で教えその著書もある「障害児を普通学校へ・全国連絡会」の片桐先生を紹介してもらい、夏休み中に娘を連れて相談に出かけた。先生曰く、「子どもも慣れるし、先生も慣れていく。それに担任は替わるから毎年最悪の先生ばかりではなく良い先生にも巡り会えるから」と言われ元気を貰った。担任も障害がある子を受け持つのが初めてで、自信がないと連絡帳に書いていたが、特別支援教育コーディネーターや養護教諭の協力を得て、好ましくない行動の4〜5項目をあげ、良くできたら花まるをつけるカードを毎日作り、保健室に行く事を娘と一緒に考えてピヨピヨタイムと名付けクールダウンが出来る様にもしてくれた。お友達との関係は保育園で一緒の子が1人もいない不安のスタート。お友達と仲良くなりたいけれど、言葉でうまく伝える事が出来なくて良くない行動がでるのはちょこちょこあったが少しずつ理解してくれる友達も出てきた。春の運動会の練習に飽きて砂いじりから友達に掛けてしまったが、その友達はその後もいろいろ関わりがあり中学では一緒にお花屋さんの職業体験をした。その子のお母さんから、何故いろいろ面倒を見てくれる学校に行かないのと聞かれて、地域の学校でみんなと一緒に過ごしたいからと答えたような…それ以降は何か言われた記憶はない。休み時間は保育園の時のように鉄棒、ジャングルジム、一輪車をするみんなの行動観察。自分はやらずにじっと見て、休み時間が終わりみんながいなくなるとおもむろに始める。そうすると時間が守れないとなって花まるカードは×になるけれど、お友達が迎えに行くと帰ってきたと言うコメントがあり嬉しかった。担任からは学年末に「めぐみさんの成長を感じます」と言ってもらえ、先生もめぐみがいたことで何か得ることがあったのかもと思った。
4年迄は毎年担任も替わったが、娘は在籍児だという前提で進み、新担任も娘の様子を校内で見て知ってる状態で受け持つので、学年代わりに多少のお試し行動はあっても穏やかに過ごせた。2年の担任は前任校で障害のあるお子さんが在籍していたので「お母さん達の苦労はとても良くわかります」と言われ泣けた。3年はベテランの先生、4年は若い先生でとちらも娘の事をとても良く理解してくれた優しく温かい先生で、この時期のトラブルの記憶はあまりない。
5、6年は区外から転任してきた担任でトラブルが増えて少し苦労したが、春の運動会迄で付添を止め卒業となった。
小学校は学童保育の生活が、娘と私にとても良かった。区立学童は障害のある子どもがいるのが前提で運営されていた。娘の自立支援はもちろん周りの子ども達との関わりも本当に良かった。学校から学童に行くのに寄り道となって指導員に怒られた時のやりとりが連絡帳あった。
お友達「めぐちゃん、いけない事反省してる?」
娘「…」うなずく
お友達「◯◯先生に許してもらいたい?」
娘「…」うなずく
お友達「そしたら先生のそばに行って遅くなってごめんなさいと言って、みんなにもごめんなさいといってごらん。」
こんな関わりがあり、私も指導員の方々に安心して相談をしアドバイスを貰ってこの時期を乗り切った。

<中学校から高校へ>
区役所で教育育委員会のあるフロアを歩いていると顔見知りの係の人に、「関さん、中学の就学相談はどうしますか?」と声をかけられた。「受けませーん!」「気が変わったら早めに言ってくださいね。」「大丈夫です。」それで終わった。
担任は、区内から転任してきて担任を持つのが初めての美術の先生。
先生は私に、なぜこの学校にいるのかときいてくる生徒がいるんですよと言ってきたので、先生は何て答えたんですかと逆に聞いた。そしてなぜこの学校に行かせたいのかを言い続けた。地域で生活して、理解してもらいたい、知ってもらいたいから。障害があるから違う場所に行けというのは差別だと。先生達が何と言おうと子どもの人生には責任は取れないのだから。
中学校は歩いて15分かかるし教材が重いし教科毎に教室を移動するので大変だった。中学は小学校とは違って軍隊ちっくだし、厳しい先生が多いいし、勉強も定期テストもとても難しい。そんな中でも、数少ない優しい先生を娘の独自の勘で探し当て何とか乗り切り通い切った。部活も1年は担任が顧問の美術部だったが、2年では新しく出来たダンス部に入って厳しかったが頑張ってやり遂げた。文化祭の時は男子から「関さーん!」と掛け声がかかった。小学校の高学年の頃から好きな男の子がいる時の接し方が問題になったが、それはそれで思春期の大切な経験だった。そのうち少し優しく接する先生も増えて、中学は評価が「1」でも進級はできたが、いろいろな先生のお陰で「1」ばかりではなかった。
娘に中学はいろいろ大変だったので嫌だと思わなかったか聞いてみたが、行きたくないとは思わなかったそうだ。ただ、ダンス部は嫌だったと言われたのが意外だった。ダンスは好きだけど、毎日部活だと放課後デイに行く日が減ってしまうからだそうだ。
高校受検の為に「障害児・者の高校進学を実現する連絡協議会」に年3、4回通うようになった。東京は定員内不合格は出さないし、都の施策のお陰でタイミングよく都立全日制も1倍を切る学校が出て来て高校生になれた。
高校では進級に向けて「1」はとれないし、授業中寝ていると成績に響くので1年の時は慣れずに大変だった。テストの点数が取れないと、課題として何教科も大量の教科書写しを出されそれはそれは大変だったが、何とか厳しい1年を乗り切った。
私はまた担任に普通校に来ている意味、将来親亡き後も生きていく為いろいろな経験体験を積んでいろいろな人とうまくやっていけるようにしたい、みんなにも慣れて欲しいと伝えた。担任はめぐみの困り感に寄り添ってくれる支援員と連携して、各教科担任と話し合ってくれた。
毎朝、学校近くで待ち合わせしていく友達も出来たが、最近は友達が待合せの時間にいつも遅れてくるので、友達が考えを改めるまで待合せをやめたのだそうだ。せっかく出来た友達なのにそんなに強気で良いのかなぁと思う。
今、高校3年の進路の時期を迎えたが、毎朝前髪を巻いて超ミニの制服姿で電車通学し、本人曰く「まあまあ」な高校生活を送っている。



.png)