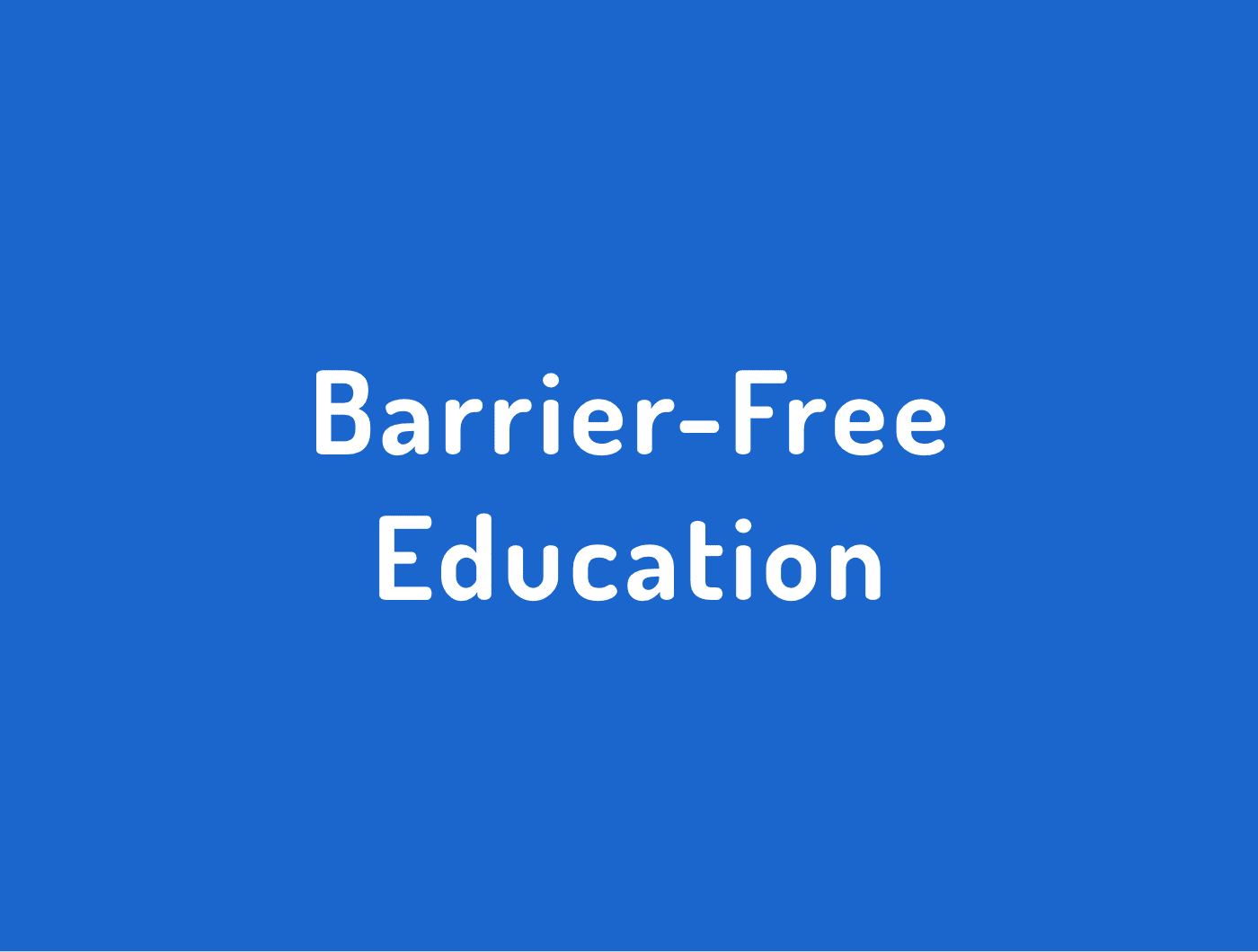*この文章は、「インクルーシブな学校づくり研究会」の取り組みをまとめた『インクルーシブな学校づくりハンドブック 2023』に掲載されたものです。より多くの人にアクセスしやすくなることを目的に、ウェブ上に転載いたします。
インクルーシブ教育は社会正義の問題
インクルーシブ教育は障害のある子とない子がともに学ぶ仕組みと考えられていますが、ユネスコが定義するインクルーシブ教育の理念を調べると、もう少し大きな意味があります。インクルーシブな社会をどう作るのかというそもそもの課題があって、その課題の下に、学校においてもインクルーシブな空間をどう作るのかという問題がある。学校にうかがって先生方とお話をしていると、インクルーシブ教育にすると学力が下がるのではないかとか、インクルーシブ教育にしても学力を上げる方法があるのかという議論が出てきます。しかし、これはそういう問題系ではありません。
ユネスコ(2020)の文章を見ると、インクルーシブ教育の利点を議論することは奴隷制やアパルトヘイトの廃止の利点を議論することに等しいと考えられると述べられています。これは非常に重要な文章です。日本の戦後で言うと男女平等がこれと同じです。戦前においては小学校でも高学年になると男組女組に分かれていました。戦後になると男女共学になるわけです。その時にはいろんな議論がありました。男女共学にしてしまうと男子の学力が下がってしまうのではないか、女子が女子らしく育つことができなくなってしまうのではないか。こういった議論は今から見てみれば、女性差別になるというのは極めて明らかです。
しかし、当時は女性差別と思わずに真剣に議論していました。インクルーシブ教育の問題も、10年か20年経って振り返ってみれば、あの時の私たちの発言はたくさん障害者差別を含んでいたということに気づくことになるはずです。ですから、利点を議論するのではなくて社会的な正義の問題なんだと考える必要があります。ここが、インクルーシブ教育を語る上で共有しなくてはいけない大前提です。
インクルーシブ教育= インクルーシブな授業ではない
インクルーシブ教育を考えていく上では5つのポイントがあると考えています。1つは民主的な地域もしくは民主的なコミュニティを作るために、その基盤としてどういう風に学校を作っていけばいいのかが問われているということです。日本はインクルーシブ教育を矮小化していると強く言いたくなるのは、インクルーシブな学びと言っても授業場面にのみ焦点が当てられている状況があるからです。インクルーシブ教育というとほぼ授業の問題にだけ焦点が当てられています。しかし、欧米の文献を見るとインクルーシブなクラスルームという議論はほとんどなくて、インクルーシブな学校をどう作るのかということがまず議論されています。
インクルーシブ教育は障害のある子どもの教育?
2点目に日本では障害のみにフォーカスが当てられていますが、人間はそもそも多様な差異を持っていて、その多様な差異を持っている人たちがともに生き合っていくということをどう作るのかということが課題になるわけです。ですから、民族、貧困、言語、宗教、性差、LGBTQ、いろんな差異が対象になるということも押さえておきたいです。日本の学校で考えますと、例えばニューカマーの子どもをどういう風に教育するのかといった問題も、インクルーシブ教育の中に含めて考えなくてはいけないということになるはずです。
インクルーシブ教育は 一人ひとりの意見を尊重
3点目は生徒の参画についてです。障害者権利条約では「Nothing about us without us:私たちのことを私たち抜きで決めないで」が重要なスローガンとされました。その意味で言いますと、生徒自身がどんな学校を作りたいのかとか、どんな学びを作りたいのかという意見を出すことができる、その権利が保障されていうことが非常に重視されています。生徒会や自治会の問題とインクルーシブ教育の問題は日本では全く切り離されて別々の問題のように考えられていますが、むしろそういったものと一体のものだということも考えなくてはいけません。
インクルーシブ教育というのは学校をどういう風に、地域のコミュニティの原点として作っていくのかということです。学校というコミュニティには生徒だけではなくて先生方もいらっしゃるわけです。そうすると教職員の一人ひとりが人間として尊重されているであるとか、教育委員会によって意見が聞かれているとかその意見が尊重されているということも非常に重要です。
バリアフリー教育開発研究センターではイギリスで作られた『インクルージョンの指針』というガイドブックを訳しました。ウェブサイトから日本語版を見られます。この中には「新しく着任した教師が歓迎されているか」といったこともインクルーシブ教育を考える一つの重要な指標としてあげられています。ですから児童会・生徒会、PTA、コミュニティスクール、そういったものと一体のものとして考えることが重要だと考えていただけるとよいと思います。
インクルーシブ教育では社会モデルの視点が重要
4つ目ですが、 例えば「発達障害と診断されるお子さん」がいらっしゃったとします。今までは、そのお子さんが特別なトレーニングを受けなくてはならないという風に考えられていました。ところが国際的な比較をしてみると、例えば何をもって発達障害とみなすのかは国によってかなり違うという状況があります。ですから国際比較はそもそもできません。つまり、学校・日本社会の文化とか習慣の中で何を障害とみなすのかが変わります。
障害者権利条約は障害の社会モデルを採用していますので、一緒に暮らすというのはどうするのかと言えば、その困っている子を特別にトレーニングするということではありません。困っている子がいるとしたらその子を困らせてしまっている様々な学校の習慣やルールをどのように見直していくのかという授業改善・学校改善が非常に重要なキーになります。ここが日本では殆どユニバーサルデザインの問題に矮小化されてしまっているのが現状です。
ユニバーサルデザインが、より多くの子どもたちにとって授業が受けやすかったり学校にいやすかったりするためのルールであることは確かですが、それは具体的なAさん、具体的なBさんにとってそのルールがよりいやすくなるかどうかということとは違います。具体的なAさん、Bさんに即して、この子たちがいやすいような環境、この子たちが学びやすいような環境はどういう風にしたら工夫できるのだろうかというのを先生たち、それから教育委員会の方たちも一緒になって検討していくことがインクルーシブ教育では非常に大事なことです。
もっと言うと、先生方の中でも非常に働きづらさを抱えていらっしゃったり、生きづらいな、しんどいなと思ってらっしゃる方がいっぱいいらっしゃるんではないかと思います。そういう方たち一人ひとりが、自分自身の人間性を学校の中で認められてゆったりと働けるような環境をどうやって作っていけるのか。よりしんどい生徒、より弱い立場の先生にフォーカスを当てる中で、全体の環境を改善していく。つまり、みんなが人間らしく、より生き生きといられるような環境をどうやって作っていくのか。これが大きな課題になるんだということも共有したいです。
インクルーシブ教育は人権を保障するためのもの
最後に、学校教育の目標をもう一度、憲法理念に戻すことが求められています。その意味において言えば、必ずしも新しい学校を作ることが求められているわけではないんだということも先生方と一緒に共有しておきたいです。近年はテスト学力をどういう風にして向上させるのかということに非常に神経が使われるようになってきています。ですから、少し外れている子、少し授業が理解できない子は「もしかしたら発達障害かもしれませんから、特別支援学級でその子に合った教育を受けた方がいいかもしれませんね」というような議論になりがちです。
障害者権利委員会から、2022年9月9日、日本政府に対して、こういった特別支援学級のあり方は一種の差別であると、そういう強い調子での勧告がなされました。憲法に規定されたようなさまざまな人権を行使し、市民社会の担い手となり得るような子どもを育てるということが大事です。
『山びこ学校』という戦後直後に書かれた教師の手記を読んでいただければ、学校においてどこが授業でどこが休み時間なのかなっていうことは分からないですよね。子どもたちが一生懸命村のことについて、自分自身のことについて、そして友達のことについて考え合う。そして議論し合う。そういう中にかれらの成長がある。その中のひとコマとして授業が存在している。
今は、算数もしくは数学の授業をうまくやるために休み時間があって、休み時間は休憩時間です。だけど、「休憩時間はおいたしちゃいけませんよ」、「隣のクラスに行ってもいけませんよ」といった、そんな規則まで作っている学校が多いのではないかと思います。休み時間も含めて、子どもたちが人間らしく過ごせる、一人ひとりの子どもの人権が尊重されるような学校をどう作っていくのかということが、インクルーシブ教育の中では問われているのだということを一緒に確認しておきたいというと思いました。以上です。 どうもありがとうございました。

東京大学バリアフリー教育開発研究センター副センター長
私の専門は日本教育史で、特に1945年を画期とする戦後の教育史に関心を持ってきました。近年は1979年の養護学校義務化反対闘争の記録を蒐集し、当時の関係者への聞き取りを行っています。これについては、ゼミをベースとした研究の成果として、2019年に『障害児の共生教育運動: 養護学校義務化反対をめぐる教育思想』(東京大学出版会)にまとめました。
この10年間で、特別支援学校在籍児童生徒の割合は1.3倍、特別支援学級は2.1倍、通級による指導の対象は2.3倍と急増しています(2016年現在)。社会的マイノリティに対する学校の包摂力が低下していることが懸念される状況の中で、背後にある問題の構造を析出すること、同時にフル・インクルージョンを可能にする学校のビジョンと教育の方法を明らかにすることに取り組んでいます。



.png)