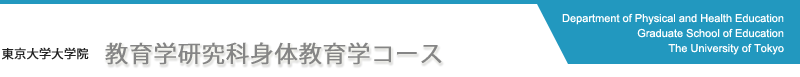本コースの特色
身・心・脳−からだとこころのしくみ

本郷キャンパス赤門と教育学研究科
本コースでは、たとえば運動の制御や学習、発達・成長、睡眠や疲労、情動などの身体現象のメカニズムを、身体と精神の相互関係、そして脳の機能にも焦点を当てつつ解明していこうとする基礎的な研究から、そうした理解を子ども・青少年や大人・高齢者の生活習慣の改善や身体・精神の疾患の予防につなげ、また学校教育や生涯教育の場における実践のあり方を模索・提言していこうとする応用・実践的な研究まで、少しずつ重なり合う分野を専門とする各教員が協力しながら行っています。それぞれの分野で世界的に通用する研究を進めると同時に、毎週の研究ミーティングで教員・大学院生が一同に揃って、基礎から応用・実践まで相互に密な議論を行っているところが、本コースの大きな特色です。(※現在本コースで行われている研究の具体的な内容については、各教員の紹介ページ・個人ウェブサイトをご覧ください。また、よろしければ「研究のキーワード一覧」「最近の学位論文題目例」「システム脳科学に興味のある方へ」もご参照ください。)
基礎から実践まで−確かな分析力を身につける
たとえば運動の制御について調べると言った場合、かねてから筋代謝についての生化学的研究が脈々と行われてきており、また、分子・細胞生物学の著しい発展を受けて遺伝子・タンパク質レベルの研究も最近特に盛んに行われています。そうした、いわば構成要素の物性についての研究は、もちろん意義深いものです。しかし、それだけで、果たして運動制御の仕組みの本質を理解できるでしょうか?一つの遺伝子の変異や差異によって個体の行動やパフォーマンスが大きく変わるというのは、確かに興味深いことです。しかし、その理由を理解し、革新的な応用につなげていくためには、構成要素の性質のみならず、要素が集まったシステムとしての振る舞いを、しかるべき方法論を用いて調べる必要があると私達は考えています。同様のことは、応用・実践的研究にも当てはまります。心理・社会的要因を含めて多くの要因が複雑に絡み合う状況で、どの要因(の組み合わせ)が特に重要なのかを、思い込みではなく客観的に導き出すためには、システム全体を捉えて分析することが肝要です。本コースでは、このような共通の問題意識のもとに、研究・教育を展開しています。
さて、システムとして捉える、と言うは易しですが、上でも「しかるべき方法論を用いて」と述べたように、そのためには、それなりのスキルを身につける必要があります。スキルにも色々ありますが(具体的には研究のデザインの仕方、実験・調査の方法、各種の統計解析やモデリングなどです)、研究内容や、各人の好み・適性に応じて、相応しいものを習得することが求められます。ここで重要なことに、そうしたスキルというものは、基礎的研究でも応用・実践的研究でも、多くの研究に共通する部分がかなりあります。それゆえに、それらをしっかりと身につければ、狭い意味での専門性を超えて、様々な分野・領域で活躍することができると私達は考えています。事実、沢山の本コース(及びその前身)修了生の方々が、学術界でも、企業や学校、官庁等でも幅広く活躍されています(具体的にはこちらをご覧下さい)。確かな洞察力・分析力とバランスの取れた感性を身につけ、スペシャリストとして頼られるジェネラリストを目指したいという方々に、ぜひ本コースへの進学を考えてみて頂けたらというのが、私達、教員一同の願いです。
豊かな環境とフレキシブルな体制
本コースには、最先端のものを含めた様々な実験設備や装置、各種分析・統計解析などのためのコンピュータやソフトウェア類、書籍などが豊富に揃っており、大学院生は、教員や先輩の指導を受けながら、それらを原則として自由に利用することができます。また、教育学研究科・教育学部は、附属中等教育学校と連携しており、本コースでも、精神保健に関するアンケート調査や、授業の試験的実施などの連携した取り組みを、大学院生が主体的に参加して進めています。さらに、附属学校において過去数十年に渡って集められてきた双生児についてのデータも、現在、本コースをスタッフ中心に維持・整備を行っており、それらに基づいた研究を行うことも可能です(倫理委員会の承認を得た上で行う必要があります)。これらに加えて、本コースでは、他大学・機関と連携体制を取っており、より幅広い分野の専門家から指導を受けることも可能となっています。
ところで、学術界を含め様々な分野において国際化の必要性が叫ばれ、本学においても全学的な取り組みが行われていますが、実際、学生の間に高い国際性を身につけておくことは、これからの時代、将来どのような道に進むにしても、殆ど必須とも言えることのように思われます。本コースは、(現時点での)教員は皆、国際的な場での研究経験があり、また現在も、国際論文誌・国際学会での研究発表は元より、海外の研究者との共同研究も盛んに行われるなど、極めて国際的な環境が整っています。短期または長期の留学を希望する場合、教員自らの経験に基づく助言が受けられるのは勿論、教員と交流のある海外の研究者のもとに推薦・紹介(さらに状況によっては経済的サポート)を受けて留学するというようなことも考えられます。
本コースに進学した大学院生は、上述の研究ミーティングの場で、各教員から指導・アドバイスを受けることができます。研究テーマを定め、いざ研究を深化させていく段階では、そのテーマに応じて特定の教員と深い議論をしながら進めていく場合が多いですが(進学する時点に既にやりたいことが明確に定まっている場合には、原則として、希望する教員を指導教員として初めから密な議論を行うことも勿論可能です)、そうした段階でも、研究ミーティングの場はもちろん、それ以外でも適宜、他の教員のアドバイスを受けられます。大学院生は各自、専用のデスクを割り当てられますが、部屋の割り振りは指導教員ごととは決まっておらず、オープンで自由闊達な雰囲気の中、同輩との交流は元より、色々な先輩からアドバイスを受けたりすることもできます。