教えて考えさせる授業の実践 連載第5回(最終回) 「教えて考えさせる授業」を展望する ■1 「教えて考えさせる授業」とは かつて、偏差値教育と言われた「教え込み・詰め込み」の時代、1990年代の「ゆとり教育」の時代、そして2000年前後の学力低下論争を経て、教育界はいま新しい局面にはいっている。その中で、「習得と探究」、「教えて考えさせる」といったフレーズが2005年以降、中教審答申の中で幾度かとりあげられるようになり、2008年3月に告示された学習指導要領にもつながって浸透しつつあるのは、ありがたいことだと思っている。 私自身がこれらの言葉を使いだしたのは、2001年ごろであり、学校や教育委員会での講演、中教審の会合、教育雑誌の記事などでたびたび用いてきた。ここには、1990年代、とくに小学校で行き過ぎの感があった、「自力解決」、「問題解決」、「指導より支援」という方針の授業への警鐘であるとともに、詰め込み教育に戻ってほしくないという思いも込められていた。図1に表したように、目標となる知識や技能を身につける「習得サイクルの学習」と、自らの興味・関心に応じて課題を設定し、それを追究する「探究サイクルの学習」の双方が、車の両輪として重要であることを押さえてほしかった。その上で、習得の授業においては、「教師の説明」「理解確認」「理解深化」「自己評価」という4段階ですすめることを授業設計の原理として提案したのが「教えて考えさせる授業」である。  <図1 習得の授業としての「教えて考えさせる授業」> けっして、授業のすべてをこの原理で行うべきであるという主張ではないのだが、そう受け止めて批判する教育関係者や、「教えて考えさせる」というフレーズ自体に反発する教員もいるだろうということは承知していた。1990年代に、「教える」という言葉(そして行為)は、極めて悪いイメージをもたされた。教師の役割は教えることではなく、「学びの支援だ」というしだいである。とくに、問題解決型の教科といわれる算数・数学や理科ではそれが強かった。これは、私から見ると、探究型の授業スタイルを無理やり拡張して習得を図ろうとする、無謀な教育論に思えた。「既習事項をもとに未習の内容を発見的に獲得できる」という児童・生徒がそういるはずもなく、また、学力の高い生徒は塾や予習で先取り学習をしていることもあり、学校では名目的に未習となっている内容を1時間えんえんと考えさせる授業は退屈だと言い出すことになる。 個人差の大きな公立の学校で、「先取り学習をしている子どもに足踏みさせない」、「学力の低い子どもも、基礎的なことが理解でき、高いレベルの問題解決や討論に参加できる」。そんな魔法のような方法があるのか、と思われるかもしれないが、「教えて考えさせる授業」は、まさにそれを正面からめざしている。それは、すべてを自力解決に委ねるのではなく、教科書に解説されていることや、答えの出ている例題はいわゆる「受容学習」として教えた上で、それを理解確認し、さらに、理解深化で発見的な問題解決学習に取り組むという、シンプルな原理でこそ可能になる。 ■2 「理解」を大切にした授業 上記の4段階を意識した授業展開になっていることが、「教えて考えさせる授業」の定義ともいえる基本的な特徴である。すでに述べたように、「未習内容を教えてしまうなど、とんでもない」という反発がある一方、「それはあたり前だ。とっくにやっている」という意見もよくある。確かに、教師が解説し(つまり、教えて)、問題を解かせる(考えさせる)というのは、昔からよく見られる授業スタイルである。しかし、教師が解説したあとで、それが本当に生徒に理解されたのかという「理解確認」や、授業が一通り終わったあとに、何がわかり、何がわからなかったのかを「自己評価」として行っているのは、まず見たことがない。授業中の表情や発言があまり豊かでなくなる中学校や高校で、教師が生徒の理解度を確認するのは、いきおいテストのときだけになってしまい、日々の授業で教師が生徒の理解度をチェックする機会や、生徒自身が自分の理解度をモニターするような機会はほとんど設けられていないのが実態ではないだろうか。 「教えて考えさせる授業」の背景にあるのは、私自身が研究室で行ってきた子どもへの学習相談活動(「認知カウンセリング」と呼ばれる)と、認知心理学の理論である。相談に来るのは「授業がさっぱりわからない。家で勉強してもわかるようにならない」という子どもたちだ。とくに、小学校の高学年くらいから、内容が高度で、学習内容も増えてくると、「わからない」という悩みが急増する。私たちが大切にしたいのは、「理解」にほかならない。理解できなければおもしろくない。理解できなければ、すぐ忘れてしまう。理解できなければ、応用的な問題も解けない。勉強の苦手な子どもにとっては、教師の説明がわかるだけでもまず素直にうれしいものだ。それを、「人に教えてもらってわかるのは、受身の学習だ」などと言わずに、まず認めた上で、それをもとに自分で考える課題に取り組むという、ごく自然な考え方に立っている。 ■3 授業展開における工夫 外からの情報を理解して取り込むという「受容学習」をしてから、その知識を生かして「問題解決学習」に取り組み、全体として理解を促進するというのは、大学生、社会人、さらには、教師も、科学者も皆行っている学習行動なのである。ただし、そのために授業で重要なのは、理解を促すための教師からの説明の工夫や、生徒の学習行動の組織化、そして、理解診断の場面をどのように設けるかということである。これらが、従来の解説型の授業でも、討論型の授業でも、弱かったのではないかと私はつねづね思っていた。討論型の授業で一部の子どもたちが活発に発言していても、他の子どもたちの理解状態を把握する手立てはとられていないことがほとんどである。 表1は、「教えて考えさせる授業」の4段階において、どのような方針で、具体的にどのような教材、教示、課題をつくるかという私自身の覚え書のようなものである。教えて考えさせる授業」というからには、「段階レベル」(予習は必須ではないので、カッコ書きになっている)は意識してほしいし、指導案にも段階区分を書き入れてほしい。「方針レベル」や「教材・教示・課題レベル」は、教師によっていろいろなバリエーションがありうるだろう。だから、「教えて考えさせる授業」によって授業が画一的になるなどという批判はまずあたらない。 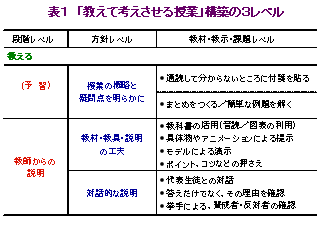 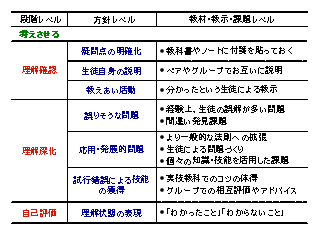 実際、同じ単元の同じ内容の授業でも、多様な授業がなされている。これは、「起承転結」という枠組みに沿っていても、4コマ漫画や小説が画一的にはならないのと同様で、「教えて考えさせる授業」というのは、それくらい広い枠組みなのである。ただし、コンセプトとして大切にしてほしいのは、「理解」を大切にした授業だということだ。それがないと、形骸的な授業に堕してしまうリスクがつきまとう。もちろん、どんな授業スタイルでも同様である。「教えて考えさせる授業」は、その趣旨を喚起するためにこそ、「理解確認」や「理解深化」といった段階のラベルをつけている。理解確認は、説明活動や簡単な課題でよいので、学習者の行動からチェックしてほしいし、理解深化は単なるドリルによる反復習熟ではなく、「なるほど。そういうことだったのか」と思える問題を用いてほしい。 ■4.学校現場からの声 「教えて考えさせる授業」は、4段階に沿って授業計画を立てることで、「習得目標は何か」「何をどう教えるか」「理解状態をどう診断するか」「より深い理解のためにどういう課題を設けるか」「自己評価はどうであり、次の授業にどう生かすか」がいやでも意識される。これが、初任者でも授業が組み立てやすく、ベテランならさらに奥の深い授業になるといわれるゆえんである。また結果として、子どもからは、「よくわかる」「やりがいがある」「おもしろい」と言われる授業になり、意欲も向上することになる。 今回の連載では、中学校の先生方が、そのような授業の様子を描いてくださっている。小学校については、すでに実践も多く、実践事例集も出版されているので、この報告は貴重である。中学校の場合、学校で取り組むとなると全教科での体制を作ることとなるので、導入のしきいは高い。しかし、「教えて考えさせる授業」は、教科を越えた枠組みであるため、実践校では、導入をきっかけに、教科を越えて指導案検討や授業後の協議会で活発なやりとりができるようになったという声をよく聞く。とくに、教師の説明のしかたや、理解確認のしかたには、教科を越えて使える指導技術があり、それがお互いに参考になることが多いという。また、理解深化課題も、教科や校種を越えてアイデアを出し合うことが、お互いの指導レパートリーを広げることにつながっているという。 私自身が書物やデモ授業で紹介する例が、算数・数学や理科が多いために、「自分の教科は、教科の特質上合わない」とか、「できる単元が限られている」とおっしゃる先生方もはじめは多い。今回の連載で、「結論からいえば、適さない単元はない。とくに、先に教えるというスタイルは、基礎・基本の習得という点ですべての授業に適用したほうがよいと言える」(第2回、理科の松本圭代教諭)、「新しい表現を教え活用させるという英語科の特性から考えると、基本的にどの単元でも実践できるはずである」(第3回、水岡彩教諭)、「3年間の研究を終えてはっきりしてきたことは、『教えて考えさせる授業』の考え方は、国語科においても大変有効だということである」(第4回、的場教諭)という意見が現場の実践者から出されたことの意味は非常に大きいし、ありがたいことである。 「教えて考えさせる授業」は、公開研究会のときだけに行う授業ではない。あくまでも、「普段着の授業」をめざしたものである。同時に、研究会でもまったく見劣りのしない授業になりうる。教師の教える工夫の先にある、生徒たちのわかる喜び、高度な問題解決への取り組み、協同学習への意欲的な参加などを見ていただければ、これが授業のオーソドックスな姿であり、原点であることがわかってもらえるであろう。今後のさらなる展開に期待したい。 ■参考書籍 市川伸一著 『学力低下論争』(ちくま新書、2002年) 市川伸一著 『学ぶ意欲とスキルを育てる−いま求められる学力向上策−』(図書文化、2004年) 市川伸一著 『「教えて考えさせる授業」を創るー基礎基本の定着・深化・活用を促す習得型授業設計ー』(図書文化、2008年) 市川伸一編 『教えて考えさせる授業 中学校』(図書文化、2011年) 市川伸一編 『「教えて考えさせる授業」の挑戦ー学ぶ意欲と深い理解を育む授業デザインー』(明治図書、2013年7月) 下記の「現代教育科学」の連載+全国各地のとりくみ事例の紹介 市川伸一著 『教えて考えさせる算数・数学』(図書文化、2015年) 副題は、「深い理解と学びあいを促す新・問題解決学習26事例」で、この数年間、 市川が行ってきた授業をまとめたものです。 市川伸一・植阪友理編著 『教えて考えさせる授業 小学校』(図書文化、2016年) 副題は、「深い学びとメタ認知を促す授業プラン」。「教えて考えさせる授業」の最 新の動向、全国各地の小学校の全教科にわたる授業例、学校全体の取り組みを紹介。 市川伸一編 『授業からの学校改革』(図書文化、2017年) 副題は、「教えて考えさせる授業による主体的・対話的で深い習得。小学校4校、中 学校2校の先進的な取り組みを紹介。 ■特集雑誌 "教えて考えさせる"授業設計のポイント(『楽しい理科授業』、明治図書、2006/9) 教えることの復権−何が課題か (『現代教育科学』、明治図書、2009/1) 「教えて考えさせる授業」の工夫 (『授業研究21』、明治図書、 2010/2) 「教えて考えさせる」授業の提案 (『国語教育』、明治図書、 2010/4) 連載 教えて考えさせる授業の実践 (『指導と評価』、図書文化、2010/7〜12) 連載 「教えて考えさせる授業」をめぐって (「現代教育科学」、明治図書、2011/ 4〜2012/3) ■情報ページ(市川研究室) http://www.p.u-tokyo.ac.jp/lab/ichikawa/ok-toppage.html |
||||