センター長
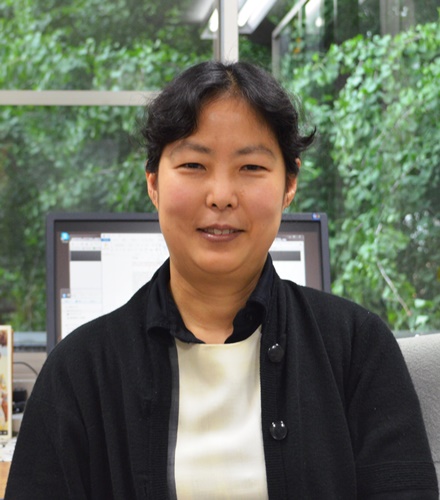 恒吉 僚子 (つねよし・りょうこ) 恒吉 僚子 (つねよし・りょうこ)
総合教育科学専攻・比較教育社会学コース・教授
一橋大学社会学部卒、プリンストン大学大学院社会学研究科、Ph.D.。東京大学大学院総合文化研究科・助教授を経て、現職。社会学、比較教育学。日米の学校のフィールドワークを中心に、教育と社会化の国際比較研究、多文化共生と教育、教育とグローバル化、国際化等に関連する研究を行ってきた。
<主要著書>
『人間形成の日米比較―かくれたカリキュラム』中公新書、1992年
『子どもたちの三つの「危機」』 勁草書房、2008年
The Japanese Model of Schooling: Comparisons with the United States、RoutledgeFalmer, 2001年
Minorities and Education in Multicultural Japan: An Interactive Perspective, Routledge, 2010年(共編著)
副センター長
 北村 友人(きたむら・ゆうと) 【研究員兼務】 北村 友人(きたむら・ゆうと) 【研究員兼務】
学校教育高度化専攻・教育内容開発コース・准教授
グローバル化時代における教育のあり方について、政治・経済・社会などとの関わりのなかから理論的および実証的に明らかにすることを目指しています。そのために、アジアの途上国を中心とした学校教育の充実に関する研究、日本の学校での「持続可能な開発のための教育(ESD)」概念にもとづく安全教育の可能性に関する研究、高等教育の国際化と国際協力に関する研究などに取り組んでいます。これらの研究を通して、教育の公共性とは何であるのか、深く考えていきたいと思っています。
<主要著書>
Emerging International Dimensions in East Asian Higher Education, Springer, 2014年(共編著)
The Political Economy of Educational Reforms and Capacity Development in Southeast Asia, Springer, 2009年(共編著)
『激動するアジアの大学改革』上智大学出版、2012年(共編著)
『揺れる世界の学力マップ』明石書店、2009年(共編著)
運営委員
 村上 祐介(むらかみ・ゆうすけ) 【研究員兼務】 村上 祐介(むらかみ・ゆうすけ) 【研究員兼務】
学校教育高度化専攻・学校開発政策コース・准教授
現代民主政治における教育政策・行政は,(政治家や市民による)民主性の担保と(教育の専門家による)専門性の確保をいかに両立させるかという困難な問題=ジレンマを本質的に抱えています。いずれかを優先すべきとの見方もあれば,両者のバランスが重要という考え方もあります。こうした民主性と専門性の関係が教育政策や学校の教育活動の帰結にどのような影響を及ぼすのかといった課題を,実証的な手法を用いて研究しています。
<主要著書>
『教育行政の政治学―教育委員会制度の実態と改革に関する実証的研究』木鐸社、2011年
『テキストブック地方自治 第2版』東洋経済新報社、2010年(分担執筆)
『現代日本の政治―政治過程の理論と実際』ミネルヴァ書房、2009年(分担執筆)
 多賀 厳太郎(たが・げんたろう) 多賀 厳太郎(たが・げんたろう)
総合教育科学専攻・身体教育学コース・教授
発達過程において、脳・身体・環境の間の動的な相互作用を通じて、運動・知覚・認知が獲得される原理を追求しています。特に、乳児期の発達に関する研究を行っています。
<主要著書>
『脳と身体の動的デザインーー運動・知覚の非線形力学と発達』金子書房、 2002年
専任助教
 伊藤 秀樹(いとう・ひでき) 伊藤 秀樹(いとう・ひでき)
学校教育高度化センター 助教
不登校、学業不振、非行などの背景をもち、社会的自立に向けた困難を抱える子どもへの、教育支援・自立支援のあり方について研究しています。日本の後期中等教育では、定時制高校・通信制高校・高等専修学校・サポート校などの学校・教育施設が、先述の背景から全日制高校に進学できない子どもにとっての、教育上のセーフティネットとなってきました。社会的自立への困難を抱えた生徒たちの学校適応や進路形成のプロセスがどのように成り立っているのかについて、高等専修学校での事例研究などを通して、探究を進めています。
<主要著書・論文>
「指導の受容と生徒の『志向性』ーー『課題集中校』の生徒像・学校像を描き直す」『教育社会学研究』第93集、2013年
「不登校経験者への登校支援とその課題ーーチャレンジスクール、高等専修学校の事例から」『教育社会学研究』第84集、2009年
『ダルクの日々――薬物依存者たちの生活と人生(ライフ)』知玄舎、2013年(分担執筆)
|

