 れ始めた1999年に文部省が示した「我が国の初等中等教育での学力はおおむね良好」という認識(⇒2-1 文部科学省)に関するものです。各当事者の立場の間に埋まらない溝を作り出した原因の1つは、このときの文部省の態度が事態を軽く見すぎていたことではないでしょうか。
れ始めた1999年に文部省が示した「我が国の初等中等教育での学力はおおむね良好」という認識(⇒2-1 文部科学省)に関するものです。各当事者の立場の間に埋まらない溝を作り出した原因の1つは、このときの文部省の態度が事態を軽く見すぎていたことではないでしょうか。
3-2
「ずれ」の背景
文部省の対応の問題
「学力低下」論の論調
教育のあり方を考える出発点
|
1つ目の背景として挙げた、「学力」に対する文部省の評価の甘さは、「学力低下」が言わ れ始めた1999年に文部省が示した「我が国の初等中等教育での学力はおおむね良好」という認識(⇒2-1 文部科学省)に関するものです。各当事者の立場の間に埋まらない溝を作り出した原因の1つは、このときの文部省の態度が事態を軽く見すぎていたことではないでしょうか。
れ始めた1999年に文部省が示した「我が国の初等中等教育での学力はおおむね良好」という認識(⇒2-1 文部科学省)に関するものです。各当事者の立場の間に埋まらない溝を作り出した原因の1つは、このときの文部省の態度が事態を軽く見すぎていたことではないでしょうか。
「学力はおおむね良好」という認識の根拠となったデータは、2-1 文部科学省で挙げたとおりです。これらのデータとそれに対する文部科学省の解釈は、以下のようなものでした。
○小・中学校の「教育課程実施状況調査(平成5〜7年度)」(文部省)![]()
・文章表現や論理的な思考力などがやや弱いなどの問題点も見られる
・計算の技能や文章を読み取る力などは比較的よく身に付いている![]()
→児童・生徒の学習状況はおおむね良好
・過去の調査と同一の問題も出題・・・通過率が高くなったものや低くなったもの様々![]()
→全体としてはほぼ同様の状況
○「第3回IEA国際数学・理科教育調査(平成7年)」(国立教育研究所)![]()
・数学および理科の学力=参加国中2〜3位(小学校26、中学校41の国が参加)
→国際的に見て依然トップクラス(第1・2回の調査もトップクラス)
・過去の調査と同一の問題の正答率はほぼ同じ
○「第3回IEA国際数学・理科教育調査−第2段階調査−(平成11年)」![]()
・平成7年と平成11年の生徒(中学2年生)の比較
→数学および理科についての同一問題の正答率はほぼ同様の結果
→学力はおおむね良好であり、維持されている
○同調査の算数・数学や理科に対する態度の比較
・算数・数学や理科が好きという子どもの割合は国際的に見て低いレベル(小・中とも)
・中学生…教科の学習が生活にとって大切であるとか、
将来数学や科学に関する職業に就きたいと考える子どもの割合も低いレベル![]()
・数学や理科に対して好意的な態度を持つ生徒の割合は平成7年に比べ減少
○大学生の学力低下について
・客観的な全国調査があるわけではない
・平成10年に大学入試センターが実施した「学生の学力低下に関する調査結果」
対象:国立大学の学部長
目的:学部新入生の学力についてのアンケート調査
結果:学部長の約55%が「学力が低下している」「やや低下している」と回答![]()
その他、意欲の低下や論理的思考力・表現力の低下を訴える声があった
約45%は「変わりない」「やや上昇している」「上昇している」と回答![]()
→近年の学生の学力が低下していると断定することはできない
「学力低下」という問題提起が社会に与える影響の大きさを考えれば、「学力低下はない」という認識を表明するにあたっては、その認識について社会の納得を得られる根拠を示 す必要があったはずです。こうした根拠を提出するために調査が必要ならば、「学力低下」という事態が実際に生じているかどうかを明らかにしようとしている文部省の姿勢と、そのために用いる方法および調査の進捗状況を、社会に対して誠実に伝えるべきです。
す必要があったはずです。こうした根拠を提出するために調査が必要ならば、「学力低下」という事態が実際に生じているかどうかを明らかにしようとしている文部省の姿勢と、そのために用いる方法および調査の進捗状況を、社会に対して誠実に伝えるべきです。
上記のデータは、「学力低下」はないという趣旨の主張をする十分な根拠であったといえるでしょうか。これらのデータが得られた調査は、サンプリングの方法やサンプルサイズといった統計的な点から、全国レベルで「学力」の実態を適切に推測できるものであったかは疑問です。ま た、これらのデータの中には「学力低下」はないという結論に反するものもあり、「学力はおおむね良好」という認識の根拠として、こうした認識の恣意性に対する国民の疑いを払拭できる程度に確かなものであったとはいえないと考えられます。
た、これらのデータの中には「学力低下」はないという結論に反するものもあり、「学力はおおむね良好」という認識の根拠として、こうした認識の恣意性に対する国民の疑いを払拭できる程度に確かなものであったとはいえないと考えられます。
しかし、文部省は、「学力低下」論によって生じた社会の動揺に対抗するには不十分な証拠に基づいて「学力低下」はないという趣旨の結論づけをしてしまいました。「学力低下」論が、文部省が進めていた教育改革路線を真っ向から否定する意味合いを持ったものであったことから、このような文 部省の対応は、「教育を文部省に任せておいて大丈夫なのか」という社会の不安をあおったと考えられます。中でも特に児童生徒の保護者の間で、文部省の認識とは反対に「学力低下」問題を危惧する空気を強めてしまった部分があるといえるのではないでしょうか。そして、このような保護者の不安が自らの利益と結びつき得る私学や塾とともに、文部科学省の立場との間に大きな「ずれ」を生じることにつながったのではないでしょうか。
部省の対応は、「教育を文部省に任せておいて大丈夫なのか」という社会の不安をあおったと考えられます。中でも特に児童生徒の保護者の間で、文部省の認識とは反対に「学力低下」問題を危惧する空気を強めてしまった部分があるといえるのではないでしょうか。そして、このような保護者の不安が自らの利益と結びつき得る私学や塾とともに、文部科学省の立場との間に大きな「ずれ」を生じることにつながったのではないでしょうか。
|
「学力低下」論の表現や論調には、センセーショナルなものが少なくありませんでした。たとえば、[1-1 論争の経緯]で紹介した『分数ができない大学生』(岡部他, 1999)や『論争・学力崩壊』(「中央公論」編集部他(編), 2001)は、本のタイトル自体が強いインパクトを与えます。また、本の帯コピーにも、見る人の不安や危機感をかきたてるものが多く見られます。
たとえば、『ゆとりを奪った「ゆとり教育」』(![]() 西村和雄(編), 日本経済新聞社,
西村和雄(編), 日本経済新聞社, 2001)の帯コピーは以下のとおりです。「日本は自滅への道を歩むのか? 「4桁の計算は電卓で」「円周率は3で問題なし」−。こんな教育が続けば、日本の人的資源は根絶やしになってしまう! 子どもの能力を低下させ、可能性を奪う「ゆとり教育」の弊害を、独自のデータと国際比較を通じて明らかにする、問題提起の書。」 この本は、「教育が危ない」シリーズの第2弾として出されていますが、同シリーズの他の本の帯コピーも同様の調子です。
2001)の帯コピーは以下のとおりです。「日本は自滅への道を歩むのか? 「4桁の計算は電卓で」「円周率は3で問題なし」−。こんな教育が続けば、日本の人的資源は根絶やしになってしまう! 子どもの能力を低下させ、可能性を奪う「ゆとり教育」の弊害を、独自のデータと国際比較を通じて明らかにする、問題提起の書。」 この本は、「教育が危ない」シリーズの第2弾として出されていますが、同シリーズの他の本の帯コピーも同様の調子です。
他にも、「いま、日本の教育は水や空気が汚染されたのと同じ状況にあります。しかし、残念なことに、文 部省は二一世紀の主人公である子どもたちに十分な教育を行おうとはしていません。2002年から実施される学習指導要領は、五千円札を出したときに電卓を使わないとお釣りの計算ができない大人をつくろうとしています。」(
部省は二一世紀の主人公である子どもたちに十分な教育を行おうとはしていません。2002年から実施される学習指導要領は、五千円札を出したときに電卓を使わないとお釣りの計算ができない大人をつくろうとしています。」(![]() 大野晋・上野健爾『学力があぶない』岩波新書, 2001)など、枚挙にいとまがありません。
大野晋・上野健爾『学力があぶない』岩波新書, 2001)など、枚挙にいとまがありません。
このような表現や論調は、実態の客観的な評価とはややかけ離れた観があります。浅沼茂氏や市川伸一氏は、「学力低下」論で引き合いに出されるデータの収集や解釈、解説の方法に問題があると指摘しています(![]() 浅沼茂「『学力』はほんとうに下がったか?-国際比較調査から」『世界』2000.5,
岩波書店, 市川伸一『学力低下論争』ちくま新書,2002)。
浅沼茂「『学力』はほんとうに下がったか?-国際比較調査から」『世界』2000.5,
岩波書店, 市川伸一『学力低下論争』ちくま新書,2002)。
「学力低下」が実際にあるということになれば、それは特に学齢期前後の子どもを持つ保護者という一般の人々にとって直接の利害がある重大な関心事であり、しかもその利害をコントロールするには即座の対応を要すると受け止められます。したがって、「学力が低下している」という問題提起自体が、広く一般社会に敏感な反応を生じさせる性質を持っています。こ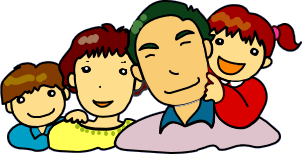 のような問題提起を、さらに上のようなセンセーショナルな表現で行えば、保護者の不安はいとも簡単に助長され、不安を解消するための手段を今すぐに講じなければならないという思いに駆り立てるでしょう。その思いを引き受ける場所としての役割を私立校や塾が自認して、文部科学省の方針を否定しこれに逆行する自らの対応をアピールすれば、保護者の認識は文部科学省の立場とますます離れたものとなっていくでしょう。
のような問題提起を、さらに上のようなセンセーショナルな表現で行えば、保護者の不安はいとも簡単に助長され、不安を解消するための手段を今すぐに講じなければならないという思いに駆り立てるでしょう。その思いを引き受ける場所としての役割を私立校や塾が自認して、文部科学省の方針を否定しこれに逆行する自らの対応をアピールすれば、保護者の認識は文部科学省の立場とますます離れたものとなっていくでしょう。
このように、「学力低下」論のセンセーショナルな表現や論調が、各関係者の立場の「ずれ」を大きくした一因になっていると考えられます。
|
「ずれ」 の背景として、3つ目に、関係者によって教育のあり方を考えるときの出発点が異なることが挙げられます。この違いによって、「学力低下」論の受けとめ方やそれに基づく対応も異なってきます。
の背景として、3つ目に、関係者によって教育のあり方を考えるときの出発点が異なることが挙げられます。この違いによって、「学力低下」論の受けとめ方やそれに基づく対応も異なってきます。
保護者や教員が教育について考えるときには、目の前にいる自分の子どもや自分の生徒といった個々の子どもが専ら関心の対象となるでしょう。そして、子どもに関する問題の判断や対応にあたっては、「この子ども(たち)に今起きている問題、今起きそうな問題を解決または回避する」ことが中心的な視点になると思われます。そのような視点に立つと、「学力低下」が実際にあるとする説とないとする説が提示されたときに、自分の関心対象である子どもに今問題が 生じる可能性を示す説、つまり「学力低下」があるとする説に従って行動することになります。また、「学力」については、問題の有無や程度を客観的に評価できる「見えやすい学力」、すなわち「実践的な力」よりも「基礎学力」に注目し、判断の基準にすると考えられます。
生じる可能性を示す説、つまり「学力低下」があるとする説に従って行動することになります。また、「学力」については、問題の有無や程度を客観的に評価できる「見えやすい学力」、すなわち「実践的な力」よりも「基礎学力」に注目し、判断の基準にすると考えられます。
また、私学・塾は、「2-3 私学・塾」で考察したように、自らにとっての現在の利益という視点から教育を考える側面が大きいと思われます。したがって、「学力」については利害の鍵を握る保護者が専ら関心を持つ「基礎学力」を重視し、「学力低下」問題については自らの利益に結びつく「学力低下は深刻」という立場に立つことになります。
一方、文部科学省が教育を考えるときには、日本の子ども全体が関心の対象となります。そして、子どもに関する問題は、全体としての子どもの現在と将来のありようという一般的な視点から考察さ れると思われます。そのような視点に立つと、「将来の日本社会において求められる人間像」をまず想定し、そこから子どもに身につけさせるべき「学力」が導かれることになります。現在文部科学省が提唱する「生きる力」も、おそらくこうした思考ルートで導かれたものです。「学力低下」論がいかに喧しくても、問題にされている「学力」が文部科学省の「学力」観の中心にある「学力」と異なるならば、その論によって文部科学省の方針が本音の部分で転換するということはないといえるでしょう。
れると思われます。そのような視点に立つと、「将来の日本社会において求められる人間像」をまず想定し、そこから子どもに身につけさせるべき「学力」が導かれることになります。現在文部科学省が提唱する「生きる力」も、おそらくこうした思考ルートで導かれたものです。「学力低下」論がいかに喧しくても、問題にされている「学力」が文部科学省の「学力」観の中心にある「学力」と異なるならば、その論によって文部科学省の方針が本音の部分で転換するということはないといえるでしょう。
したがって、「学力低下」という問題が提起されたときに、保護者・教員や私学・塾は目の前の現実から出発し、一方で文部科学省は一般的な理念から出発して、問題についての判断や対応を行っていると考えられます。この差は立場の違いから必然的に生じるものです。差 異があっても、その差異の背後にあるそれぞれの考え方について共通認識があればよいのですが、そのような共通認識の存在は感じられません。
異があっても、その差異の背後にあるそれぞれの考え方について共通認識があればよいのですが、そのような共通認識の存在は感じられません。
現実から教育の問題を考える保護者・教員や私学・塾は、教育に対する長期的なビジョンが欠落していることが多いと思われます。そして、目先の利害と社会を扇動する力に流された意見形成を行ってしまう可能性が大きいのではないでしょうか。
これに 対して、理念から教育の問題を考える文部科学省は、現場の意識や感覚に注意を払い理解しようとする姿勢が欠けていると思われます。そして、意識的か無意識にかはともかくとして、理念に基づく方針や施策を肯定する方向にデータを解釈していることがあり得るのではないでしょうか。
対して、理念から教育の問題を考える文部科学省は、現場の意識や感覚に注意を払い理解しようとする姿勢が欠けていると思われます。そして、意識的か無意識にかはともかくとして、理念に基づく方針や施策を肯定する方向にデータを解釈していることがあり得るのではないでしょうか。
それぞれの立場への固執によるこのような視野の狭さが、各関係者の間の断絶をもたらしていると考えられます。