2-4
保護者・教員
「学力低下」問題に対する意識調査
日本PTA全国協議会の調査
北九州市教育委員会の調査
ベネッセ総研の教員意識調査
国立教育政策研究所の研究調査
朝日新聞社・くもん子ども研究所の共同調査
|
学校教育の現場に最も近い位置にあるのは、児童生徒の保護者や公立校の教員![]() です。「学力低下」問題に対する彼らの認識は、これまでに多くのアンケートによって調査されています。以下に、その主なものを紹介します。
です。「学力低下」問題に対する彼らの認識は、これまでに多くのアンケートによって調査されています。以下に、その主なものを紹介します。
|
2002年6〜7月に行われたアンケートで、2002年4月から実施された新学習指導要領などについての意識を調査しています。全国公立小中学校の会員6000人を対象とし、4777人から回答が得られました。
アンケートでは、新学習指導要領に対する保護者の抵抗感が強いことが示されました。これは、当時マスコミなどが「教科内容の3割削減」といったセンセーショナルなキーワードによって否定的 な評価を繰り返していたことの影響があると思われます。新指導要領について心配なこととして上位に挙げられたのは、「教員や学校により教育内容や質に格差が出る」(57%)、「児童・生徒の学力格差が拡大する」(45%)、「学力が全体として低下する」(39%)、「塾や補習などの割合が増える」(35%)などでした。また、学力低下については、75%の保護者が不安を感じているという結果でした。
な評価を繰り返していたことの影響があると思われます。新指導要領について心配なこととして上位に挙げられたのは、「教員や学校により教育内容や質に格差が出る」(57%)、「児童・生徒の学力格差が拡大する」(45%)、「学力が全体として低下する」(39%)、「塾や補習などの割合が増える」(35%)などでした。また、学力低下については、75%の保護者が不安を感じているという結果でした。
保護者としては、自分の子どもたちに十分な学力を持ってほしいと願うのは当然の意識でしょう。文部科学省の取った政策は、当初はその願いとは相容れるものではありませんでした。この時点では、親が不安に感じるのはまず当然と思われます。しかし、この調査は、2-1 文部科学省で述べた「学びのすすめ」緊急アピールが出された後に行われています。この揺り戻しに対して、親は何を感じているのでしょうか。毎日新聞の取材に対して、協議会の赤田英博会長は、次のように答えています(毎日新聞2002年8月22日朝刊)。「(新指導要領 の)実施直前に、宿題や補習を奨励する「学びのすすめ」を出すなど、方針がぶれている。不安になるのは当然だ」。新指導要領自体に対しても不安を感じるが、急に転換した(ように見える)文部科学省の姿勢も不安だ、というわけです。
の)実施直前に、宿題や補習を奨励する「学びのすすめ」を出すなど、方針がぶれている。不安になるのは当然だ」。新指導要領自体に対しても不安を感じるが、急に転換した(ように見える)文部科学省の姿勢も不安だ、というわけです。
それなりの説明責任を果たしていればそのような不安は広がらなかったのかもしれませんが、文部科学省は理由をきちんと説明せず、方針転換は認めず、学力低下もなし崩し的にしか認めていません。このような状態の行政を信頼することはそう簡単ではないということを、このアンケート結果は示しているといえます。
|
2002年7月に行われたアンケートで、市立の小中学校と養護学校に子どもを通わせる親とこれらの学校の教員を対象としています。
まず親の回答結果について、新指導要領の実施にともなう「学力低下」に関す る質問では、「学力は低下しない」という回答は7.3%にとどまり、「学力は低下する」と回答した40.3%とは大きくかけ離れた結果となっています。子どもの学校・学年別に見ると、小学校よりも中学校で学力低下を心配する意識が強くなっています。
る質問では、「学力は低下しない」という回答は7.3%にとどまり、「学力は低下する」と回答した40.3%とは大きくかけ離れた結果となっています。子どもの学校・学年別に見ると、小学校よりも中学校で学力低下を心配する意識が強くなっています。
また、学力低下を防ぐために学校に望むものは何か、という質問では、「毎時間の授業で、基礎・基本の内容を確実につけさせてほしい」(63.2%)、「習熟度(理解度)に応じた指導を充実させてほしい」(52.8%)、「計画的な宿題を出すなど、子どもの学習意欲や学習習慣を身につけさせてほしい」(35.3%)、「補習など学習機会を広げてほしい」(23.7%)、「『総合的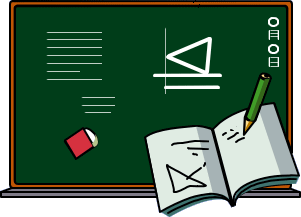 な学習の時間』を充実してほしい」(11.0%)という順になりました。この質問は「学力」の低下を前提としていて、ここから全体の傾向を判断するのは困難ですが、『総合的な学習の時間』のような文部科学省が進めてきた教育改革の方針とは逆のベクトルが働いている状況を見ることができます。
な学習の時間』を充実してほしい」(11.0%)という順になりました。この質問は「学力」の低下を前提としていて、ここから全体の傾向を判断するのは困難ですが、『総合的な学習の時間』のような文部科学省が進めてきた教育改革の方針とは逆のベクトルが働いている状況を見ることができます。
次に教員の回答結果について、「学力低下」に関する質問では、「学力は低下しない」という回答が17.9%、「学力は低下する」という回答が38.5%となっています。この質問に対する中学校教員の回答に着目すると、興味深い結果が出ています。管理職以外では「学力は低下する」が58.8% に達するのに対し、管理職は「学力は低下しない」が41.7%であり、立場によって認識が異なる傾向が顕著に見られました。また、学力低下を防ぐために望むものとしては、「毎時間の授業で、基礎・基本の内容を確実に定着される努力」(70.9%)、「子どもの学習意欲や学習習慣を身に付けさせる努力」(59.7%)が高くなっています。
に達するのに対し、管理職は「学力は低下しない」が41.7%であり、立場によって認識が異なる傾向が顕著に見られました。また、学力低下を防ぐために望むものとしては、「毎時間の授業で、基礎・基本の内容を確実に定着される努力」(70.9%)、「子どもの学習意欲や学習習慣を身に付けさせる努力」(59.7%)が高くなっています。
親と教員の結果を比較すると、親の方が「学力は低下しない」と考える割合が低く、また「習熟度に応じた指導の充実」を望む割合が高いことが分かります。教員の中でも特に管理職は学力低下に対する危機感が薄いということが示唆されているので、総合的に見ると、子どもとのつながりが弱いほど危機感が減少する傾向があるとも考えられます。また、自分が今までに行ってきた授業の形式に対するこだわりがあるのか、教員は習熟度別授業の![]() 導入にはより慎重な姿勢が見られます。
導入にはより慎重な姿勢が見られます。![]()
なお、この他にも各地の教育委員会が同様の調査を行っており(岐阜県教育委員会(2003年1月公表)など)、「学力低下」については親、教師ともに低下すると考える意見が多数を占め、おおむね一致する結果が報告されています。
|
2002年10月から12月にかけて、14都道府県の公立小中学校の教員を対象に行われ、管理職1200人、一般教員7000人から回答を得ています。
これに よると、小学校教員、中学校教員、さらに管理職も約7割が、新指導要領の教育内容を「削減しすぎ」と回答しています。また、新指導要領の実施で「学力が低下する」と予測した教員は、小学校で76.0%、中学校で87.1%にのぼりました。新指導要領の見直しが「必要」とした教員も、小学校で73.4%、中学校で82.4%に達しました。
よると、小学校教員、中学校教員、さらに管理職も約7割が、新指導要領の教育内容を「削減しすぎ」と回答しています。また、新指導要領の実施で「学力が低下する」と予測した教員は、小学校で76.0%、中学校で87.1%にのぼりました。新指導要領の見直しが「必要」とした教員も、小学校で73.4%、中学校で82.4%に達しました。
「ゆとり路線」に対する危機感を顕著に示しているのは、宿題に関する回答です。小学校教員の90.2%が宿題を「毎日出す」としており、ベネッセが1998年に行った調査の80.4%から上![]() 昇していました。中学校でも、「宿題はほとんど出さない」教員が1998年には38.1%だったのに対し、今回は25.1%と減少していました。
昇していました。中学校でも、「宿題はほとんど出さない」教員が1998年には38.1%だったのに対し、今回は25.1%と減少していました。
教員は教育現場の当事者として彼らなりの危機感を持ち、あるいは保護者の不安に応えるために、それぞれ「学力低下」の対策を講じている、ということが、この調査からは見えてきます。
|
2003年3月に、「ホリスティックな教育改革の実践と構造に関する総合的研究」(研究代表者:菊地栄 治・国立教育政策研究所総括研究官
治・国立教育政策研究所総括研究官![]() )の中間報告書が発表されました(学会発表は2002年9月)。この研究の調査では、全国公立中学校の5%がサンプルとして抽出され、校長320人、一般教員5610人から回答を得ています。調査はアンケート方式で、様々な学校の現状を聞く内容となっています。
)の中間報告書が発表されました(学会発表は2002年9月)。この研究の調査では、全国公立中学校の5%がサンプルとして抽出され、校長320人、一般教員5610人から回答を得ています。調査はアンケート方式で、様々な学校の現状を聞く内容となっています。
報告の内容はマスコミでも大きく取り上げられ(たとえば朝日新聞, 2002年9月22朝刊)、また遠山文部科学大臣や金森審議官が記者会見でコメントするなど、1つの研究発表としては社会的な注目を集めました。この研究は、平成13〜15年度の日本学術振興会科学研究費の基盤研究として行われたもので、いわゆる世論調査などとはその位置づけが異なります。しかし、国立教育政策研究所という、文部科学省組織令によって設置された機関に所属する研究者が、以下のような研究成果を発表したことの意味は大きいと考えられます。
アンケートの中で教育改革に関する項目を見ると、「もっと中学校の教育現場の現実を踏まえた教育改革にしてほしい」という項目に「とてもそう思う」「ややそう思う」と回答した教員は96.8%、校長は93.4%でした。また、「教育改革のペースが速すぎてじっくりと取り組む余裕をなくしている」という項目では、「とても」と「やや」を合わせて「そう思う」教員は86.8%、校長は85.3%でした。教育改革の一つの柱である「総合的な学習の時間」が生徒にとってプラスかどうかについては、「そう思う」教員が50%、「そう思わない」教員が40.2%と、評価が割れる結果となりました。
また、「どのような教育改革が進められるとよいと考えられるか」という質問に対する自由記述には、 校長の約8割、教員の約5割が記入しましたが、そのうち最も多い記述は現在の教育改革のあり方への批判で、全体の約29%を占めました。具体的には、「机上の空論」、「方針のぶれが大きい」、「上からの押しつけ」といった厳しい意見が出されました。さらに、教科内容の削減に対する不安や総合学習への反対など、改革内容についての疑問を記したものも約17%ありました。
校長の約8割、教員の約5割が記入しましたが、そのうち最も多い記述は現在の教育改革のあり方への批判で、全体の約29%を占めました。具体的には、「机上の空論」、「方針のぶれが大きい」、「上からの押しつけ」といった厳しい意見が出されました。さらに、教科内容の削減に対する不安や総合学習への反対など、改革内容についての疑問を記したものも約17%ありました。
菊地研究官は朝日新聞の取材に対して、「改革を担うのは学校。子どもと向き合っている教師の声を生かさなければ、実りが少ない。これまでの改革も、学校でやった結果を十分反映してこなかった。現場の実感を改革に生かす道筋をつくる必要がある」と話しています。
|
全国の小学4年生から高校3年生を対象として2002年に朝日新聞社とくもん子ども研究所が共同で実施したもので、子どもの学習意欲などとともに、親の意識についても調査が行われました。父親と母親を合わせて1481人が回答しています(![]() くもん子ども研究所 『からざレポート 2002 vol.2 学ぶ意欲』)。
くもん子ども研究所 『からざレポート 2002 vol.2 学ぶ意欲』)。
「子どもの成績を気にするか」という質問に対しては、「気にする」と「どちらかと言えば気にする」を合わせて75.6%の親が気にしていて、1994年の同研究所の調査と比較すると5.1%の増加が見られました。また、「学歴は重要だと思うか」という質問に対しては、「そう思う」「どちらかと言えばそう思う」が77.2%に達し、1997年の同研究所の調査と比べて1.2%増加していました。
この2つの比較調査の結果は、詰め込み教育への批判が落ち着き、確実に知識をつける教育が再び求められ始めていることを示しています。
|
これらのアンケートの結果からは、保護者、教員ともに、「ゆとり」や「生きる力」を重視する文部科学 省の教育改革路線に対する不安やとまどいが強いことが分かります。アンケートにより結果にばらつきがありますが、総じて、特に保護者の間で教育改革によって「学力」が低下するという意見が多く、「学力」として「基礎学力」を重視する「学力」観に立っていると思われます。
省の教育改革路線に対する不安やとまどいが強いことが分かります。アンケートにより結果にばらつきがありますが、総じて、特に保護者の間で教育改革によって「学力」が低下するという意見が多く、「学力」として「基礎学力」を重視する「学力」観に立っていると思われます。