その他
翻訳について―
一つはチームワークで、もう一つはキャリアです。
チームワークは、臨床を関係性や連携など、空間軸に拡げてくれます。
そして、キャリアは臨床を人生という時間軸に拡げてくれます。
私たちの日々の生活は、空間軸と時間軸の接点に成り立っています。
その一瞬一瞬に生命が宿り、それが人生につながっていきます。
心理支援は、クライエントの生命も生活も人生という3つのLIFEを少しでも自分らしく、少しでも生きやすくするための支援だと思っています。
そのために必要な本を翻訳してきました。
一つは、チームワークです。
上述のように、臨床でも研究でもチームワークは欠かせません。
もちろんゼミの運営でも、コース運営でも同じです。
本書は臨床以外の一般の会社のチームにも役に立つと思いますが、何よりも臨床心理学の世界にチームワークというセンスを拡げたいと考えました。

高橋美保(訳)『チームワークの心理学 エビデンスに基づいた実践へのヒント』マイケル A ウェスト(著)、下山晴彦(監修)、 東京大学出版会、 2014
もう一つが、キャリアです。
これも臨床心理学の世界ではあまり正面切って言われてこなかったものです。
むしろ、キャリアカウンセリングは近隣の領域として位置づけられてきたように思います。
しかし、心理支援において、どうやって働くか、どうやってキャリアを築くかに関する相談は少なくありません。
そんな時に、キャリアは射程外です、といっていては話になりません。
もちろん、就職支援そのものはキャリアコンサルタントさんに任せて、協働した方が良いでしょう。
しかし、働くことは生きることです。
どう働くかを考えるためには、就職活動とは違った次元で、自分はどう生きたいのか、どうありたいのかをじっくり考える必要があります。
そこはもしかしたら心理職ならではの仕事ができるところかもしれません。
そのためにも、近接領域であるキャリアカウンセリングについても基礎的なことは理解しておいた方が良いでしょう。
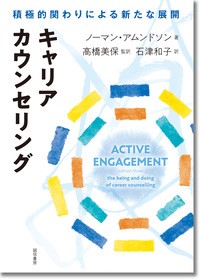
高橋美保(監訳)『キャリアカウンセリング 積極的関わりによる新たな展開』、ノーマン・アムンドソン(著)・石津 和子(訳)、 誠信書房、2018
最後に、今はマインドフルネスに関する本を翻訳しています。
私の臨床心理学の原点―
“無の感覚”
1.私の中の“それ”
私は特定の宗教への信仰が篤いわけではない。しかし、自分を超えた絶対的なものがあるという感覚は常にある。人はそれを神というかもしれないし、仏というのかもしれない。少なくとも私にとっては、“それ”は必ずしも偶像化されたものではない。そのイメージを持ち始めたのは小学校の時に遡る。
たぶん、小学校1年くらいであったと思う。毎日登校する通学路の、ある交差点に差し掛かると、私はいつもある不思議な感覚に襲われていた。今の私は“それ”を“宇宙と私の関係”と表現してみる。しかし、無理に言葉にしたことで、大事な何かがそぎ落とされてしまっているようで、しっくりこない。今でこそ“それ”を“それ”以外の言葉で表現することもできるが、当時の私には自分が何を考えているのかもよくわからなかった。抽象語を的確に操れない発達段階において、抽象的な事象について考えることはとても難しい。そのため、“それ”は言葉というより、体感やイメージ、感覚、感情に近いものであり、考えるというより感じていたものであった。さらに、感じていたというよりは、感じさせられていた感覚であった。つまり、自分が主体的に考えたい、感じたいと思うのではなく、物理的なある地点に着くと、何度となく同じ感覚に襲われていたという感覚である。
先述のように、敢えて言うなれば、“それ”は宇宙と自分の関係であり、宇宙は物理的空間であると同時に超越的な存在でもあった。自分は宇宙の中で塵のような存在であり、私が多少悩んでいても、あるいは私自身が生きて死んでも宇宙には何の影響もない。自分は何と小さく、無力で、瑣末な存在なのか、と感じていた。“それ”は、小さな私には怖くてたまらない感覚であると同時に、当時の私にはこれは事実であり、“それ”は受け入れなくてはならないという妙な感覚もあった。“それ”は考えても答えが出ないことであり、恐怖感も伴う体験であったが、私はそうして感じされられる(あるいは考えさせられる)体験を、何か崇高なものと捉えていた。
この体験について、当時、自分の親にも話したことはなかったと思う。ひょっとしたら、しようとしたことはあったのかもしれない。しかし、恐らくうまく言えなかったと思う。誰かに“それ”をきちんと話し、理解してもらえたという記憶はない。
いつの間にか、“それ”について集中的に意識するということはなくなっていた。集中的に意識したのは、実際にはほんの数日間だったのかもしれない。そして、その後、“それ”は私の体験の中で日常化したのかもしれない。そのせいだろうか、私にはいつも強い無力感や無常観がある。
2.私の中の“それ”と臨床心理学
“それ”は、恐らくその後の私の臨床や研究にも緩やかに繋がっているように思う。臨床心理学の世界にいると、「どうして臨床心理学を勉強しようと思ったのですか?」と訊かれることが度々ある。その時の答えは、実は一貫していない。相手との関係性や、質問の意図等によって答えを意図的に変えることもある。また、その時の気分で違う答えになってしまっていることもある。しかし、いずれも嘘ではない。その時の自分に言える答えを精一杯答えていることに違いはない。
ここで、上述の幼い時の私の体験から、「なぜ私が臨床心理学の道に入ったのか」を考えてみると、恐らくこの無力感が大きく関係しているように思う。私の根底にある無力感や無常観は私自身のものであると同時に、人間全体や、地球上にある生きとし生けるものすべてのものにも繋がっている。ある時代、ある地域に束の間、生を受けたものが、どのように生き、死んでいくのか。何が良くて何が悪いというわけでもなく、その時代、その地域に生まれ出でたことの宿命をただただ引き受けて生きていく。そういうとても小さくて、儚く、健気な存在という人間観がある。
しかし、それはただ恐怖や絶望に満ちているわけではない。単に受動的というわけでもない。その現実をしっかりと見据え、ある意味受け入れる中で、それでも与えられた命を生きることはできるという、ある意味の光がある。個人的な体験が重なって恐縮ではあるが、私の中の最も原初的なイメージは真っ暗闇の中の一筋の光である。しかし、これも“光”と表現してしまうと、少し違うものになってしまう気がする。いつどこで見たものかもわからないが、とても暗い中に、ぼわっとした膜をまとった白いものがすーっと射してくるイメージである。それは、敢えて言うなら光というかもしれないが、これも色やかすかな温もり、イメージなどを伴う不思議な感覚である。それは、実際には何の保証もないが、少しの希望に繋がるイメージである。
私の個人的な体験にやや宗教じみた感じを抱く人もいるかもしれないが、私の体験には何の宗教的な意味もない。ただ、このような穏やかな白いものというのは、無力感や無常観の中で生きることを少し後押ししてくれるものである。何も信じることはできないし、何の保証もないが、とりあえずは今を精一杯生きてみようという気持ちにさせる。
このような体験を振り返ると、私が臨床心理学の世界に足を踏み入れた理由の一つは、「自分の力では抗えないものがある中、それでもその人なりに生きていくことを一緒に考えたい」からではないかと思う。抗えないものには生老病死はもちろんのこと、様々な次元のことがある。
私が臨床心理学の道に入ってから続けてきた失業者の研究は、社会的な経済情勢、労働市場の変化という社会的事象における、個人では抗えない次元の体験としての失業を扱っている。また、細々と関わっている遺伝子診療は、自らが生まれながらに保有する遺伝子情報という生物学的な抗えない次元の体験に関わるものである。いずれも自分の力では抗えない次元の体験である。
しかし、私の関心や研究の目的は、単純に失業がなくなればよい、あるいは遺伝子情報は知らなければよい、ということではない。失業は経済の発展の中で生じた現象ともいえる部分もあり、遺伝子診断も医学の進歩の中で生じた現象である。つまり、それらはある意味では社会の発展の必然の中で生じたひずみであり、それは単に回避すればよいという問題でもないように思う。したがって、失業が起こることが、あるいは遺伝子疾患がわかることが問題であるということではなく、そういう誰にも起こりうる、避けがたい、抗いがたい事象がこの世には否応なくあり、その中にあって、どのようにそこから生き進んでいくのかを考えたいと思っている。
3.臨床心理学におけるしなやかな受容
それは単に個人の内界を重視する志向性とも異なる。心理的な深みというだけではなく、それと同等かそれ以上に厳しい現実を見据えるため、その援助は極めて現実的な志向性を持つこととなる。極めて深い個人の内面と同時に、その人が生きる現実社会もしっかりと把握する、そのいずれもが重要であると改めて感じている。
これらの志向性を敢えて現代の臨床心理学の潮流になぞらえるならば、前者が精神分析的、分析心理学的であり、後者は認知行動療法的と捉えられよう。ただし、勿論これは極論であり、実際には良き臨床家であればいずれを標榜していても、もう一方の視点をしっかりと持っているように感じている。認知行動療法におけるアクセプタンスの流れもその一つと言えるであろう。
私個人の臨床場面では、「役に立つこと」を判断基準にしたいと思っているが、基本的なアプローチとしては「ないものを獲得する」よりも、「持てるものに気づき、活かす」方がより好みである。これは私の中の無力感や無常観にも関係しているのかもしれない。しかし、獲得する発想は自分が何かを持っていないことを認めることから始まるが、持てるものに気づく発想は、実は自分は既に何かを持っているということに気づくところから始まるという意味で、より積極的であるともいえよう。
失業の臨床でも、資格を取って何かを獲得しようとする人もいるが、必ずしも再就職に直結しないこともある。むしろ、自分の中でやれてきたことや、自分が何を大事に生きていきたいと思っているかを今一度問い直していくことが重要のように感じている。勿論、あった方が良いものは積極的に獲得すべきであるが、抗えない体験の中ではそれ自体がままならないことが多い。
このような厳しい現実を受け入れることを、時代の潮流に乗って、“受容”や“アクセプタンス”という言葉を使って表現するのが適切かどうかはわからない。私のイメージする受容は、単に受動的であるだけでなく、認知を過度にポジティブにするのでもなく、あるがままの現実を等身大で認めることであり、それは極めてしたたかで、しなやかな強さを持つものである。テーゼに対するアンチテーゼとしてではなく、それらを止揚するものが求められているのかもしれない。
所詮宇宙の塵ではあるが、塵だからといって意味がないというわけでもない。塵ながら、それでも存在する意義を考え、自分に何ができるかを考え続けていきたいと思っている。無から何かを生み出す力を信じたいと思う日々である。
