第三回総会・合同シンポジウム開催報告
2017年10月26日
10月21日(土)に教職支援ネットワーク第三回総会が開催されました。
◆教職支援ネットワーク役員紹介
本ネットワークの会長は東京大学教育学研究科長、幹事は教育学研究科教職課程委員会委員となります。当日は、会長及び出席した幹事から、参加者のみなさんにご挨拶いたしました。
◆教育学研究科・教職支援ネットワーク合同シンポジウム
「開放制の教員養成」の意義の問い直しが迫られるなかで、東京大学における教員養成の意義や可能性と課題について、学校現場、教育学研究者、それぞれの立場から検討し議論する主旨でシンポジウムを開催いたしました。
登壇者(五十音順、敬称略)
勝野 正章 (東京大学大学院教育学研究科教授)
菅間 正道 (学校法人自由の森学園高等学校教頭)
前田 香織 (東京大学教育学部附属中等教育学校主幹教諭)
山屋 秀夫 (長野県下高井郡木島平村立木島平小学校長)
コメンテーター
小玉 重夫(東京大学大学院教育学研究科長)
コーディネーター・司会
藤江 康彦(東京大学大学院教育学研究科准教授)
藤江 康彦准教授からの主旨説明ののち、登壇者より20分ずつ話題提供がありました。

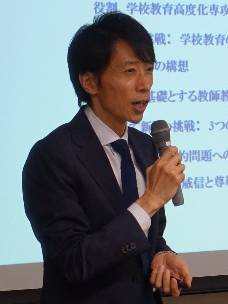
勝野教授からは「東京大学における教員養成の意義と展望」としてお話がありました。まず、東京大学における教員養成の現状や教育学部・教育学研究科の歴史を踏まえて、教育学研究科の今後の構想をお話しいただきました。その後、ご自身の意見も交えつつ「研究を基礎とする教師教育」についてお話があり、最後は保障されるべきものとして「教職の自律性」「専門職に相応しい労働条件・環境」「専門職に相応しい社会的威信と尊敬」が挙げられました。
菅間教頭からは、まず自由の森学園の映像上映があり、続いて学校の全景や授業中の生徒達の表情のスライドを紹介しつつ、自由の森学園が大切にしている「学び」や、実際の授業の進め方や様子、生徒の評価方法について説明され、自由の森学園の教育についてお話がありました。その後、業務の多様化・多忙化等により教員が現在置かれている厳しい状況について、ご自身の経験を踏まえて話題提供がありました。「昔は、教師は12月(師走)だけ走っていたのかもしれないが、今は一年中走っている」とのお言葉が印象的でした。
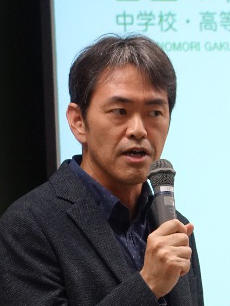
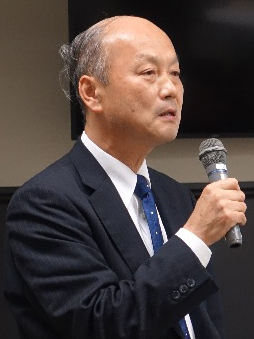
山屋校長からは、木島平村の概要紹介があり、その後木島平村で進める一貫型教育とその内容についてお話がありました。「学び続ける教師は崩れない」との考えから教員の研修に力を入れていることが紹介され、地域や諸大学との協力により「協同的な学び」の取組を持続する工夫をしているとの報告がありました。また、昨年度より実施されている本学教育実習生の受け入れと木島平小学校6年生修学旅行時の本学への訪問について、児童や引率された先生の所感の紹介があり、その意義と継続することの大切さについてお話がありました。
前田教諭からは、まず教育学部附属中等教育学校と本学の連携について具体例を示しつつ説明がありました。続いて、授業についていけなくなる生徒と授業の内容では物足りない生徒への対応について、教員養成系大学出身教員と研究大学出身教員の特性を踏まえつつ話題提供がありました。その後、多様性をキーワードに、生物部の活躍に本学学生のコーチが大きな影響を与えたこと、昆虫に興味を持った生徒が、それをきっかけとして研究者を目指すために勉強でも飛躍したことが紹介されました。関連して、附属中等教育学校の特徴である卒業研究の説明がありました。また、教員の業務の多様化・多忙化についても生物部の活躍を例に、教員が多忙であることからコーチが付いたゆえに飛躍できた側面もあると、具体例を挙げて指摘がありました。

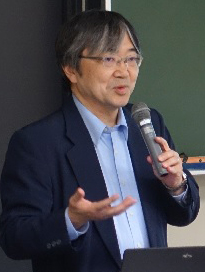
登壇者の話題提供を受け、小玉研究科長よりコメントがあり、続いて下記の質問が発せられました。
「研究者としての教師の育成を阻んでいるもの」
「研究者としての教師が育成される条件」
「東大教育学部との連携が継続される条件:全学への説得(勝野)、中高生が研究することはすべてにとって可能か(菅間、前田)、公立学校の継続性(山屋)」

休憩を挟んだのち、登壇者から小玉研究科長の質問への回答があり、続いてフロアの参加者からも意見を募りました。参加者からは大変活発な意見が寄せられ、また多くの方が発言を希望なさいましたが、予定の時刻を迎えたため、最後に登壇者から本日の感想を伺い、惜しまれつつも盛況のうちに閉会となりました。
本シンポジウムにおいては、東京大学が養成しうる「学び続ける教師」=「研究者としての教員」の意義が確認され、一方で教員の業務の多様化・多忙化等により、教員が学び続けることの難しさが存在することが指摘されました。また、そのような状況における教職支援ネットワークのような組織の有用性と意義についても、改めて確認されました。
教職支援ネットワークでは、今後も各種イベントを開催していく予定です。引き続きまして、ご参加・ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。


