March 25, 1999
この小文は、昨今流行の「脳と心(こころ)」についてのものではない。 心といっても心臓のことである。
私事で恐縮だが、今を溯ること15年あまり前、初めて本格的に読んだ
科学論文が、Physiological Reviews誌の``Physiological
adaptations in diving vertebrates.''[1]というものであった。
当時の指導教官の一人であった宮下充正教授(現東洋英和女学院大)から、
ヒトの水中運動の生理についてテーマをいただき、測定した心拍数をあれこれと
いじっていた関係で目に触れたということである。水中での運動では呼吸に
制限があり![]() 、常識的にはより
「苦しい」はずなのに、運動中の心拍数があまり上昇しないという
観察結果が得られた。学部学生の私にはどうにも解釈できない結果で
あった。この潜水動物の生理的適応に関する論文には、ちゃんと答えが
載っていた。もちろん当時の私が納得した答えであったが。
、常識的にはより
「苦しい」はずなのに、運動中の心拍数があまり上昇しないという
観察結果が得られた。学部学生の私にはどうにも解釈できない結果で
あった。この潜水動物の生理的適応に関する論文には、ちゃんと答えが
載っていた。もちろん当時の私が納得した答えであったが。
潜水動物とは、イルカやクジラなどの哺乳類やカモなどの水棲鳥類を 指すのであるが、これらの動物は体内の酸素貯蔵量と安静時代謝の比を はるかに凌ぐ長時間、潜水を行うことができる。潜行中、これらの 動物の体内では、徐脈や活動筋を含む各臓器の血管収縮が起こり、 致命的臓器である脳に血流を確保するような反射、すなわち潜水反射 (diving reflex)とか酸素節約反射(oxygen conserving reflex)と 呼ばれている反応が起こる。運動中の活動筋の血流さえも犠牲にする (もちろん活動自体は無酸素性代謝でまかなわれているのであるが)と いうこの反応は、潜行中のペンギンを捕獲し直ちに羽を切り落とした ところ、絞っても血液が出てこなかったという象徴的な記述とともに、 「致命的臓器としての脳」を私の脳裏に焼き付けた。ヒトにおいても 同様な反応が残存するという記述もあり、私の観察結果は、比較的 強度の高い運動中でもそのような反応がみられることを意味するのでは ないかなどと思い、本誌にささやかな論文を書いた[7]。1984年の ことである。これが私の初めての論文だった。
今回、編集委員の加賀谷淳子教授より、「研究生活のスタートにおいて 関わったテーマであると伺っております。その後、今日までの成果も 含めて、やさしく解説していただければ幸いです。」というお申し出を いただいた。どこでお聞きになられたのかは不明だが、それ以降この 問題にはあまり正面から取り組んでいない、という事情も出来れば お調べいただきたかった、などと愚痴をこぼしていても仕方がない ので、本題に入ることにしよう。
つい最近、同じPhysiological Reviews誌に、 ``Physiology of diving birds and mammals.''[4]と いう総説が発表された。
冒頭で述べたような潜行中の生体反応、およびその生理学的意義に関する 仮説を発見者の名にちなんでIrving-Scholander仮説と呼ぶ。代表的な 例としてWeddellアザラシの潜行中のデータを図1に示すが、潜行開始と ともに、60拍/分あった心拍数が10拍/分まで急激に低下していることが 分かる(図1C)。このとき各臓器への血流量は、脳を除いて大幅に減少する (図1A; -100 %に近い減少ということは「血流がほとんどない」という こと)。これは主として末梢血管抵抗の増大によるものとされるが、血管 抵抗の増大により、心拍数(一回拍出量はあまり変化しないので心拍出量 と言い換えてもよい)が低下しても脳への潅流圧が維持されるのである。 潜行中に血流が制限されるため、活動筋は無酸素性代謝を余儀なくされる。 その結果、潜行終了とともに動脈血乳酸濃度の急激な上昇が認められる (図1B)。
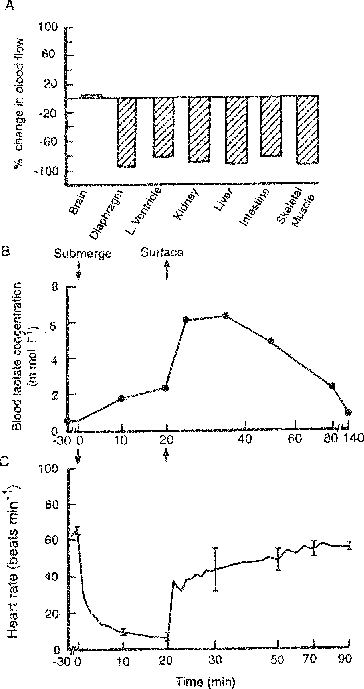
Figure 1: Weddellアザラシの潜行中の生体反応。(A)各臓器への血流量、
(B)動脈血乳酸濃度、(C)心拍数。文献[4]より引用。
この最近の総説の著者であるButlerとJonesによると、Andersenの 総説[1]が発表された1966年から30年間の進歩は、 主として生理学的データの計測技術の発展により、自然界に生息する 潜水動物のありのままの姿を捉えることが可能となったことである という。その結果以下のような事実が明らかになった[4]。
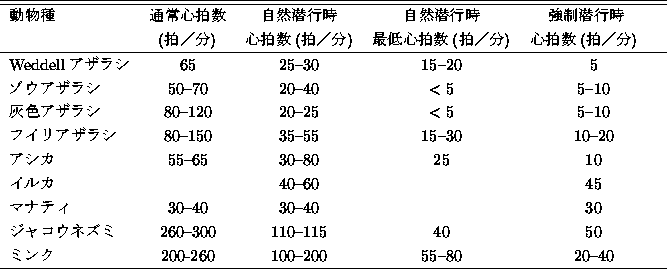
Table 1: 各種潜水哺乳類の潜行時心拍数。文献[4]より
抜粋。
ButlerとJonesは明記していないのだが、私は、この結果を酸素供給システム に起こった進化論上の変化として捉えたら面白いのではないかと考えている。 すなわち、これらの動物において、致命的臓器である脳を守る潜水反射・ 酸素節約反射は、どうやればうまくエサを捕れるかなど行動の進化により その基本的反応としての意義を失いつつあるのではないだろうか。いわゆる 大脳化の進行したイルカやマナティの例を出すまでもなく、動物はその行動 が洗練されればされるほど、捕食のために生存を脅かすというような危険な 状況を避けるようになると言えるのかも知れない。そして、この調節システム の大脳化という事態(もしあるとすれば)により、生命維持を目的としたより 基本的な反射がどのような系統発生的運命をたどるのか、興味が持たれる のである。このことをより詳細に調べるためには、表1で抜け落ちているイルカや マナティの自然潜行時最低心拍数を調べる必要があることは言うまでもない。 すなわち、これらの動物が本当に必要なときには潜水反射を用いて長時間 潜行を行うことがあるのか(あるいはその潜在能力があるのか)否かは、 その行動をつぶさに観察しないと何とも言えないのである。これらの動物の 行動範囲は広く、その観察は決して容易ではないが、その結果は、ヒトに おける酸素節約システムの意義を考える上でも貴重な資料になるものと 期待される。
余談だが、本年4月のアメリカ生理学会大会(Washington, D.C.)において、 このButler氏とJones氏によって、``Remote monitoring of physiological function''というオーガナイズド・セッションが開催されることになって いる。上述した通り、潜水動物の生理学に関する近年の進歩は、これらの 動物を、自然のままで遠隔モニタリングできる技術の発展なしには達成 されなかった。ある時はGPSを利用し、潜水のみでなく飛行さえ行う水鳥を 追跡したり、荒波にもまれるクルーザーからイルカに取り付けられた発信機の電波を 追いかけたり、北極海の氷上で穴掘りをしてアザラシが潜ってくれるのを じっと待っていたりと、実験水槽とはかけ離れた過酷な条件下で得られた データが進歩を演出したということである。実験的研究が隆盛の生理学で あるが、自然の理解のためにはこのような「フィールド・ワーク」が依然 として有効であることを物語っているようにも思える。セッションでは、 このような遠隔モニタリング技術に関する最近の話題が討論される予定である。 かく言う私も、約3ヶ月間に渡ってヒトの心拍数、体動を記録できる開発中の 携帯型生体信号記録装置[2]について紹介しようと思っている。 世間の「荒波」にもまれるヒトの行動・心理生理的特性については、やはり ありのままをモニタリングしてみないと何とも言えないような気がするから である。
もう一つ、この30年間の進歩が顕著であったのは、脳・神経科学の分野で
あり、この分野でも潜水反射・酸素節約反射の脳内機序が次第に明らかに
されつつある[5]。ただし、そこで得られた実験動物についての知見と、
例えば冷水への転落とかある種の極限状況におかれたヒトが奇跡的に一命をとり
とめたという逸話的報告との間の距離は、未だ大きいと言わざるを得ない![]() 。
水中でのヒトの生体調節に潜水反射・酸素節約反射がどの程度の役割を
果たしているのかという点については、依然として十分に解明されていない
ように思える。
。
水中でのヒトの生体調節に潜水反射・酸素節約反射がどの程度の役割を
果たしているのかという点については、依然として十分に解明されていない
ように思える。
再び私事となるが、その後Waterloo大学(Ontario, Canada)でのポスドク時代は、
上記のテーマと離れて重力負荷に対する心臓血管系の応答に関する研究を行う
ことになった。いわゆる下肢陰圧試験とかティルト試験を用いて、下肢への
血液の貯溜を物理的に促進させ、その際脳灌流を確保するためにどのような
生体反応が起こるか調べるというものである[3]。大学院時代に
はやったことのない実験だったので、いかにも頑丈そうな被検者の青年が最初
の実験で失神した時は驚いた。私は心拍数を見張っている役だったので、
彼の瞬時心拍数が、一拍毎に60(拍/分)、30、15、と低下して行き、最後には
10〜15秒間に渡って完全に停止したとき、その反応の異様さゆえ、コトの重大さ
を忘れて、コンピュータの画面に見入っていた記憶がある![]() 。
。
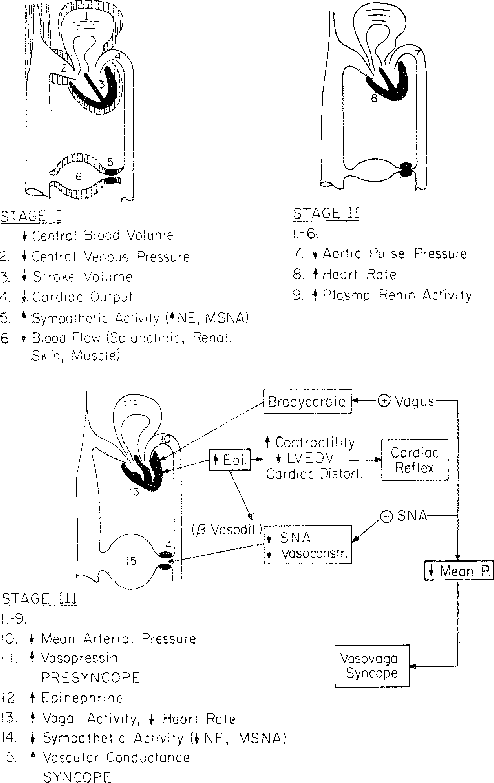
Figure 2: 重力負荷時における血管迷走神経性失神発生のメカニズム。
文献[6]より引用。
この反応は、血管迷走神経性失神(vaso-vagal syncope)と呼ばれているもので、 朝礼中に子どもが立ち眩みを起こしたりするという起立調節障害との関連が 示唆されている。その大まかな機序を図2に示す[6]。要約すると、
よく知られているように、進化論上のヒトの大きな特徴は、大脳皮質の発達
および直立姿勢の獲得である。特に後者と関連して、起立調節障害のような
事態は、循環系が重力の影響をまともに受けて脳循環の安定性を脅かされた
結果と考えられるのであるが、その場合なぜ最も重要な(はずの)脳を守らない
のか、私には理解できないのである。脳の重要性が増した(はずの)ヒトに
このような反応がみられるというのだから、なおさらである。脳はそれ自身の
死活が心臓に握られているという事情を認識しているとでもいうのだろうか。
この私の疑問は取るに足らないものかも知れないが、誰か答えをご存知の方が
いれば、是非ともお教えいただきたいと思う![]() 。
。
資料収集にご協力いただいた北出篤史氏(東京大学大学院教育学研究科) に謝意を表します。本研究の一部は、文部省科学研究費補助金基盤研究B (課題番号10480005; 1998年)、宇宙環境利用に関する公募地上研究 (財団法人日本宇宙フォーラム; 1997年)、および科学技術庁振興調整費 (1996年)の補助により行われた。
(体育の科学, 1999 (印刷中) より)
脳と心 -水中と陸上でのヒト-
This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 96.1 (Feb 5, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
The command line arguments were:
latex2html -split 0 jres_12.
The translation was initiated by Yoshiharu Yamamoto on 1999年03月25日 (木) 14時41分45秒 JST