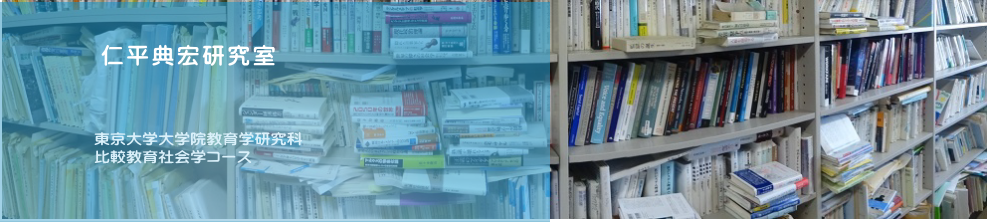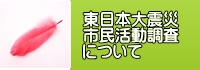調査票を受け取られた方は、お手数をおかけして誠に恐縮ですが、何卒ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
「第二次首都圏の市民活動団体に関する調査」について
政府の限界、市場の限界が明らかになるなか、市民社会の力量と責任は確実に増しております。しかし他方で、管理や監視の強化や、活動資金獲得における障壁など、市民活動を妨げる要因もあるかと存じます。日本の市民社会は現在どのような役割を果たしているのか、また活動を進める上で、どのような課題があり、どう改善していけばいいのかについて本調査を通じて明らかにしていきたいと考えております。
本調査は2回目になります。前回は2006年に、首都圏で活動されている市民活動団体を対象に、同様の質問紙調査をさせて頂き、その際、貴団体にも調査票を送付させて頂きました。
前回調査から13年が経ちましたが、その間に日本の市民社会の構造はどう変わったのか、どれくらい力を増したのか、そして活動の阻害要因・促進要因や、活動を取り巻く都市空間はどう変化したかなどについて、前回調査の結果との比較を通じて明らかにし、皆様と知見を共有していきたいと考えております。また、市民社会の各アクターが共通に抱えている課題を明確に浮かび上がらせて、その背景にある制度的・社会的な阻害要因を改善していくためのきっかけ、新たな連帯を紡ぎ出す一助となることを願っております。
お忙しいところ大変恐縮ですが、前回ご協力頂いたか否かを問わず、ご協力を賜れますと幸甚に存じます。つきましては、アンケート調査にご記入の上、同封の返信用封筒にて、4月30日(火)までにまでにご投函くださいませ(切手は不要です)。
年度の切り替わるお忙しい中、誠に恐縮でございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
●本調査のねらい
本調査は、首都圏における市民活動団体・運動団体・NPO・NGOの現状について、広く深く理解することを目的としております。2006年に実施した第一回調査と共通の質問項目も用い、13年の間に市民社会組織の構造や役割はどう変わったか、その促進要因や阻害要因にどのような変化があったのか、明らかにしていきたいと考えております。
1)市民活動、運動、NPO、NGO、社会的企業といった区別を超え、共通の質問項目によって実施する点で、これまでにない試みです。これにより、市民社会のアクターの実態、歴史性と構造、可能性などが捉えられるものと期待します。
2)行政などではなく、独立した研究グループの実施する調査ゆえに、グローバル化の進展、国家に対する意識の変化や格差社会化などの時代の変化の影響、法人制度の浸透、都市空間の変容など、市民活動を取り巻く制度的・社会的環境の変化などにも踏み込んで、現実を明らかにできるものと期待します。
3)市民活動団体と行政・企業の関係を詳細に調べることにより、市民社会のアクターが抱える新しい課題を明らかにすることができると期待しています。
これらを通じて、市民活動が全体としてどのように実践を編み上げ、どのように新しい動きを作りだしているのか、皆様と知見を共有していきたいと考えております。また、市民社会の各アクターが共通に抱えている課題を明確に浮かび上がらせて、その背景にある制度的・社会的な阻害要因を改善していくためのきっかけ、新たな連帯を紡ぎ出す一助となることを願っております。
●調査対象団体の選定方法――なぜ貴団体が選ばれたのでしょうか
本調査は、2006年の調査で調査票を送付させて頂いた団体を対象としております。
2018年に改めて団体名をインターネットで検索し、住所等に変更があったと思われた団体様には、新しい住所にお送りさせて頂いております。また改称・改組があったり、後続団体に変わった場合も、同様に送付させて頂いております。
2006年調査の時は、次のように団体を選定させて頂きました。
1)団体の機関誌
2)市販の団体名鑑
3)都県および内閣府所轄のNPO法人一覧
から、約3500団体を抽出させていただきました。
調査票は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に事務所をお持ちの団体様宛に発送しております。
詳細は以下の通りです。
1)団体の機関誌
4都県に事務所を持つ団体が2000年~2006年に発行した機関誌から、「機関誌を発行した団体」と「機関誌内に団体名が掲載された団体」を選び出しました。機関誌は、書店「模索舎」(新宿区)で購入した他、埼玉大学共生社会研究センター(当時)にて閲覧いたしました。
2)市販の団体名鑑
下記を参照し、4都県に事務所を持つ団体から、政策提言や外部向け啓発活動等の活動をおこなっている団体を選びました。
①『全国患者会障害者団体要覧』プリメド社、2006年.
②『全国組織女性団体名簿 2004年版』市川房枝記念会出版部、2004年.
③『女たちの便利帳』ジョジョ企画、2004年.
④『国際協力・交流全国NGO・NPO名鑑 2002年』日本外交協会、2002年.
⑤『国際協力NGOダイレクトリー』国際協力NGOセンター、2004年.
⑥『平成13年版 環境NGO総覧』(財)日本環境協会、2001年.
3)認証NPO法人
4都県庁のホームページからNPO法人一覧を閲覧し、「定款に記載された目的」の欄に下記のキーワードのいずれかを含むNPO法人を抽出いたしました。
<キーワード:権利、市民活動、市民参加、市民社会、情報発信、人権、政策、提言、都市>
●調査主体、調査倫理
・本調査は、社会運動論、市民社会論、都市社会学を専門とする大学の研究者のグループが実施しています。前回調査の代表者は一橋大学大学院社会学研究科社会学部教授・町村敬志でした。今回は代表者は異なりますが、前回代表者も含め調査メンバーの多くが参加しております。
・本研究は、独立行政法人日本学術振興会の助成金(基盤研究C 17K04093)を得て実施しております。
・本調査は匿名で行い機密を厳守します。調査結果の公表に際しては統計的に処理し、個票データは絶対公表されることはありません。また結果は研究目的以外には使用致しません。調査にあたっては「社会調査協会倫理規程」を遵守いたします。もちろん、お答えいただけない質問にはお答えいただかなくて結構です。
●結果のフィードバック
・集計概要は、回収・入力・分析が終了後、本ホームページにて発表する予定です。紙媒体の結果概要をご希望の方は、調査票の最終頁の送付先住所欄にご記入頂くか、メールまたはFAX(03-5841-3945)にて、ご連絡くださいませ。
・もし個別に分析をご希望される場合は、ご連絡をいただければ実施いたします。
●調査者について
・調査責任者(仁平)は社会学を専門とし、ボランティア活動や市民活動、社会運動等の役割と歴史性の分析を主な研究テーマとしております。
・個人的な運動や市民活動との関わりにつきましては、2002年よりささやかながら野宿者の支援運動や反貧困の運動に関わってまいりました。
何卒ご協力賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
2019年3月 仁平典宏
質問紙はこちらからもダウンロードできます。
→質問紙(PDF)
本調査は2回目になります。前回は2006年に、首都圏で活動されている市民活動団体を対象に、同様の質問紙調査をさせて頂き、その際、貴団体にも調査票を送付させて頂きました。
前回調査から13年が経ちましたが、その間に日本の市民社会の構造はどう変わったのか、どれくらい力を増したのか、そして活動の阻害要因・促進要因や、活動を取り巻く都市空間はどう変化したかなどについて、前回調査の結果との比較を通じて明らかにし、皆様と知見を共有していきたいと考えております。また、市民社会の各アクターが共通に抱えている課題を明確に浮かび上がらせて、その背景にある制度的・社会的な阻害要因を改善していくためのきっかけ、新たな連帯を紡ぎ出す一助となることを願っております。
お忙しいところ大変恐縮ですが、前回ご協力頂いたか否かを問わず、ご協力を賜れますと幸甚に存じます。つきましては、アンケート調査にご記入の上、同封の返信用封筒にて、4月30日(火)までにまでにご投函くださいませ(切手は不要です)。
年度の切り替わるお忙しい中、誠に恐縮でございますが、何卒ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
●本調査のねらい
本調査は、首都圏における市民活動団体・運動団体・NPO・NGOの現状について、広く深く理解することを目的としております。2006年に実施した第一回調査と共通の質問項目も用い、13年の間に市民社会組織の構造や役割はどう変わったか、その促進要因や阻害要因にどのような変化があったのか、明らかにしていきたいと考えております。
1)市民活動、運動、NPO、NGO、社会的企業といった区別を超え、共通の質問項目によって実施する点で、これまでにない試みです。これにより、市民社会のアクターの実態、歴史性と構造、可能性などが捉えられるものと期待します。
2)行政などではなく、独立した研究グループの実施する調査ゆえに、グローバル化の進展、国家に対する意識の変化や格差社会化などの時代の変化の影響、法人制度の浸透、都市空間の変容など、市民活動を取り巻く制度的・社会的環境の変化などにも踏み込んで、現実を明らかにできるものと期待します。
3)市民活動団体と行政・企業の関係を詳細に調べることにより、市民社会のアクターが抱える新しい課題を明らかにすることができると期待しています。
これらを通じて、市民活動が全体としてどのように実践を編み上げ、どのように新しい動きを作りだしているのか、皆様と知見を共有していきたいと考えております。また、市民社会の各アクターが共通に抱えている課題を明確に浮かび上がらせて、その背景にある制度的・社会的な阻害要因を改善していくためのきっかけ、新たな連帯を紡ぎ出す一助となることを願っております。
●調査対象団体の選定方法――なぜ貴団体が選ばれたのでしょうか
本調査は、2006年の調査で調査票を送付させて頂いた団体を対象としております。
2018年に改めて団体名をインターネットで検索し、住所等に変更があったと思われた団体様には、新しい住所にお送りさせて頂いております。また改称・改組があったり、後続団体に変わった場合も、同様に送付させて頂いております。
2006年調査の時は、次のように団体を選定させて頂きました。
1)団体の機関誌
2)市販の団体名鑑
3)都県および内閣府所轄のNPO法人一覧
から、約3500団体を抽出させていただきました。
調査票は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県に事務所をお持ちの団体様宛に発送しております。
詳細は以下の通りです。
1)団体の機関誌
4都県に事務所を持つ団体が2000年~2006年に発行した機関誌から、「機関誌を発行した団体」と「機関誌内に団体名が掲載された団体」を選び出しました。機関誌は、書店「模索舎」(新宿区)で購入した他、埼玉大学共生社会研究センター(当時)にて閲覧いたしました。
2)市販の団体名鑑
下記を参照し、4都県に事務所を持つ団体から、政策提言や外部向け啓発活動等の活動をおこなっている団体を選びました。
①『全国患者会障害者団体要覧』プリメド社、2006年.
②『全国組織女性団体名簿 2004年版』市川房枝記念会出版部、2004年.
③『女たちの便利帳』ジョジョ企画、2004年.
④『国際協力・交流全国NGO・NPO名鑑 2002年』日本外交協会、2002年.
⑤『国際協力NGOダイレクトリー』国際協力NGOセンター、2004年.
⑥『平成13年版 環境NGO総覧』(財)日本環境協会、2001年.
3)認証NPO法人
4都県庁のホームページからNPO法人一覧を閲覧し、「定款に記載された目的」の欄に下記のキーワードのいずれかを含むNPO法人を抽出いたしました。
<キーワード:権利、市民活動、市民参加、市民社会、情報発信、人権、政策、提言、都市>
●調査主体、調査倫理
・本調査は、社会運動論、市民社会論、都市社会学を専門とする大学の研究者のグループが実施しています。前回調査の代表者は一橋大学大学院社会学研究科社会学部教授・町村敬志でした。今回は代表者は異なりますが、前回代表者も含め調査メンバーの多くが参加しております。
・本研究は、独立行政法人日本学術振興会の助成金(基盤研究C 17K04093)を得て実施しております。
・本調査は匿名で行い機密を厳守します。調査結果の公表に際しては統計的に処理し、個票データは絶対公表されることはありません。また結果は研究目的以外には使用致しません。調査にあたっては「社会調査協会倫理規程」を遵守いたします。もちろん、お答えいただけない質問にはお答えいただかなくて結構です。
●結果のフィードバック
・集計概要は、回収・入力・分析が終了後、本ホームページにて発表する予定です。紙媒体の結果概要をご希望の方は、調査票の最終頁の送付先住所欄にご記入頂くか、メールまたはFAX(03-5841-3945)にて、ご連絡くださいませ。
・もし個別に分析をご希望される場合は、ご連絡をいただければ実施いたします。
●調査者について
・調査責任者(仁平)は社会学を専門とし、ボランティア活動や市民活動、社会運動等の役割と歴史性の分析を主な研究テーマとしております。
・個人的な運動や市民活動との関わりにつきましては、2002年よりささやかながら野宿者の支援運動や反貧困の運動に関わってまいりました。
何卒ご協力賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
2019年3月 仁平典宏
質問紙はこちらからもダウンロードできます。
→質問紙(PDF)
仁平典宏研究室
〒113-0033
東京都文京区本郷7?3?1
東京大学大学院教育学研究科
比較教育社会学コース