クライエントの主観的体験から見た心理面接のプロセス
―面接内と面接間の双方に注目して―
第I部 クライエントの主観的視点から心理面接のプロセスを理解する試み—面接内と面接間の双方に焦点を当ててー
心理面接においてクライエントの主観的視点を尊重することは重要である。それは,面接の進展に関するクライエントとカウンセラーの理解は必ずしも一致しない(Swift&Callahan,2009)ことからも言える。このような面接の中(面接内)で生じたカウンセラーとクライエントのすれ違いは,面接と面接の間の時間(面接間)にも維持されたままとなる可能性がある。すれ違いはカウンセラーとクライエントの双方から見ないと判らないにも関わらず,従来の心理面接に関する研究の多くは,カウンセラーや研究者の視点から行われていた。クライエントの主観的体験から,初期面接のプロセスを,面接間も含めた一連の流れの中で明らかにした研究は充分でない。そこで本研究は,面接初期におけるクライエントの主観的体験を,面接内と面接間の双方から探索的に明らかにし,それにより心理面接における臨床的示唆を得ることを目指した。そのための研究の構成は下記の通りとした。
- 面接内のクライエントの主観的体験に関する研究(第II部)
- 面接内・面接間双方におけるクライエントの主観的体験に関する研究(第III部)
- 第II・第III部で非臨床群から得られた知見が臨床群に転用可能か検証する研究(第IV部)
第II部 面接内におけるクライエントの主観的体験
第II部では,まず第5章(研究1)で,1回のロールプレイ/試行カウンセリングを受けたクライエントを対象としたインタビュー調査を行った。面接は,共感的に話を聞き,変化を促すような特別な介入は行わない設定で行った。インタビューは,面接の録音/録画を視聴しながら,筆者とクライエントが自由に話し合う形式(IPRインタビュー)を取った。そのインタビューデータを,グラウンデッド・セオリー・アプローチを用い分析した。その結果,同じ設定で行われたにも関わらず,話が深まると感じたクライエントと,深まらないと感じたクライエントがいることが明らかになった。そして,話が深まらない場合にも,それに伴う不満や批判がカウンセラーに対し表明されることはなかった。ここから,面接内において,表明されないクライエントの不満が存在する可能性があることを,常にカウンセラーが心に留めておくことが,ドロップアウト等を防止につながることが示唆された。
第6章(研究2)では,同様のデータを,ケース・マトリックス,事例比較法を援用し分析した。それにより,話が深まるプロセスや,深まらない場合との違いを明らかにすることを目指した。その結果,話が深まるためには,自分の話がカウンセラーに伝わっているとクライエントが感じるだけでなく,それが受け入れられていると実感できることが必要であることが明らかになった。たとえ話が伝わったと感じたとしても,それを受け止めてもらえないと感じた場合,クライエントは回避的に感情を抑制していた。ただ,この場合も面接中のやりとりは流暢に流れていた。ここから,傾聴という技法は,単独で有効なのではなく,受容と組み合わされて初めてクライエントにとって有益なものとなることが明らかになった。また,面接中のやりとりは問題ないようであっても,それが感情回避的なものでないかに留意する必要性も示唆された。
第III部 面接内と面接間の双方におけるクライエントの主観的体験
第III部では,面接内と面接間の双方におけるクライエントの主観的体験を探索的に明らかにすることを試みた。3回の短期試行カウンセリングを受けた4人のクライエントに対し,IPRインタビューを行った。まず,第7章(研究3)において,そのうちの1人のクライエントのケースに関する体験・ナラティブ指向事例研究を行った。このケースの1回目の面接で,クライエントはカウンセラーの態度に不満を抱いていたが,3回目の面接では,主訴となる問題は一定の解決へと至っていた。このように最終的に良い形で面接が終了した要因として,クライエントの面接観が寄与していた。このケースでは,クライエントは,面接の場が日常会話とは異なる意義を持つと感じていた。このような面接観が面接を継続させ,継続することが治療関係の修復につながっていた。ここから,クライエントに形成された面接観をカウンセラーが共有することの重要性が示唆された。
第8章(研究4)では,4人のクライエントに対するIPRインタビューデータを,M−GTAを用い分析し,次の2点を検討した。第1が,面接内と面接間におけるクライエントの主観的体験である。第2が,面接内と面接間の相互作用である。分析の結果,クライエントの主観的体験として,研究3で示された面接観に関するカテゴリが他のクライエントでも見出され,これを《面接を自分なりに使えるようになる過程》とした。他にも面接内に関するものとして《話すことで何かを得る過程》・《面接の場だからこその関係を認識する過程》が抽出された。また,面接間に関するものとして《面接間に変化の兆しが現れる過程》が見出された。カテゴリ間の分析によって,これら面接内と面接間に関するプロセスは相互に高め合うようにして働いていることが明らかになった。面接内と面接間の相乗効果により,クライエントの日常は何らかへの変化と至っていた。それを,コアカテゴリ【日常生活の変化へと向かうベクトル】とした。
第IV部 クライエントの主観的体験に焦点を当てた臨床事例研究−面接内と面接間の双方に焦点を当てて−
第IV部では,非臨床群から得られた研究4の知見が臨床群においても見られるかを検証するために臨床群を対象としたインタビュー調査を行うこととした。まず第9章(研究5)で,短期臨床事例(事例A)を取り上げた。
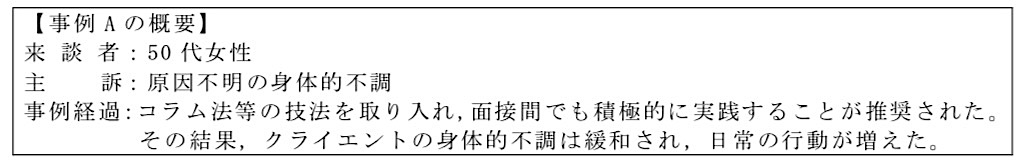
調査のため,事例終結の数カ月後にクライエントにインタビューを行った。その結果,非臨床群を対象とした研究4で得られた【日常生活の変化へと向かうベクトル】に向かうプロセスは,臨床群である事例Aにおいても同様に見ることができた。さらに,臨床群においては,次の4点が問題解決の動きを加させることも明らかになった。それは,1来談前から問題の整理が行われていた点,2面接をどのように役立てるかも来談前からイメージされていた点,3カウンセラーの専門性に重きを置く姿勢,4カウンセラーの介入とクライエントの動機づけの高さが,面接内と面接間の相乗効果を強める点である。 次の第10章(研究6)では,長期事例を取り上げた(事例B)

調査のため,事例終結後の数ヶ月後に,クライエント本人と母親にインタビューを行った。分析から,事例Bにおいても,研究4で得られた【日常生活の変化へと向かうベクトル】へと至るプロセスが確認された。しかし,事例Bは,事例Aとは異なり,《話すことで何かを得る過程》や《面接の場だからこその関係を認識する過程》のプロセスに停滞や遅延の時期があることも明らかになった。ここからは,事例経過が順調でない際に,プロセスのどこに遅延や停滞が起きているかを,クライエントの問題状況と関連づけて査定し,対処していくことで,面接過程の軌道修正をはかりうることが示唆された。
第V部 クライエントの主観的体験から見た心理面接のプロセスとは
本研究では,クライエントの視点から心理面接のプロセスを,面接内・面接間の双方に焦点を当て明らかにすることを目指した。クライエントへのインタビュー調査を基本とした研究の結果,次のことが明らかになった。
- 面接内のプロセスとして,話の進展・治療関係の進展・面接構の理解の進展という要素があること。また,これらの要素には相乗効果があること。
- 面接内のプロセスは,面接間の認知や行動に影響を与える。一方,面接間は面接内に影響を与えるという相乗効果があること。
本研究から得られた臨床的示唆として次のことが挙げられる。
- 話の進展に関しては,傾聴は受容が組み合わされて初めて効果がされること。また,クライエントの表明されない不満や批判があることに留意すること。
- クライエントの中に暗黙裡に形成された治療構を共有することは,話の進展を促すだけでなく,面接の継続や治療関係の修復につながる。そのため治療構の共有が重要であること。
- 面接内と面接間の相乗効果を高めることが重要であること。そのため,カウンセラーの介入の工夫や,クライエントの動機づけの維持向上が必要であること。
- 面接プロセスが思うように進展しない場合のチェックポイントとして,話の進展・治療関係の進展・面接構の理解の進展・面接間の動きという要素があること。
最後に本研究の限界としては,臨床事例として取り上げたのが2ケースであるということがある。よって,本研究の結果を一般化することには限界がある。そこで,今後は事例を追加し,転用可能な範囲を精査していくことが必要である。また,得られた知見を臨床実践の場に導入し,効果との関連を検証していくことも課題となる。
