山本義春
(東京大学大学院教育学研究科)
物理学が「物理現象の原理」を追及するのと同様に、 生理学は「生命現象の原理」を追及する学問である。 そして物理学で「ニュートンの運動の法則」がその基本原理 であったように、「キャノンのホメオスタシス」は、 今世紀の生理学の基本原理であった。ホメオスタシス (homeostasis)とは、同一の(homeo)状態(stasis)を 意味するギリシア語からの造語で、 「生体内の組成・物理的状態を一定に維持する機能」 を表わす生理学用語として、今世紀初頭の米国の 生理学者キャノン(Walter B. Cannon)により命名 された。わが国では、「生体恒常性」などとも訳されて いる。
これがどのくらい基本的な原理であるかは、たまたま 筆者の手元にある3冊の生理学の教科書の、いずれも第2ページ にその記載があることからも伺える(要するにまず最初に 書いてあるということ)。これらの記載を要約すれば、 「われわれが個体として生命を維持していくためには、 ホメオスタシスを保つことが必要であり、何らかの 原因により、体内のホメオスタシスが著しく乱されると 病気になる。ホメオスタシスが保たれるのは、生体に 自動調節機構が存在するからであり、その作動原理 は負のフィードバックと呼ばれる。」とでもなろう。
われわれのからだの中で一定なものの具体例として、
動脈血二酸化炭素分圧( ![]() )を取り上げる。
二酸化炭素は別名炭酸ガスと呼ばれるとおり、体内の
酸性度を規定する重要な因子であり、通常ヒトの
)を取り上げる。
二酸化炭素は別名炭酸ガスと呼ばれるとおり、体内の
酸性度を規定する重要な因子であり、通常ヒトの ![]() は
40mmHg程度に保たれている。そして「なぜわれわれの
は
40mmHg程度に保たれている。そして「なぜわれわれの ![]() は
いつも40mmHgに保たれているのか」との問いに
対して、ホメオスタシスの原理は以下のような説明をする。
は
いつも40mmHgに保たれているのか」との問いに
対して、ホメオスタシスの原理は以下のような説明をする。
脳内には、化学受容体と呼ばれる ![]() のセンサが
あり、このセンサが現在の
のセンサが
あり、このセンサが現在の ![]() のレベルを常に監視している。
例えば代謝による二酸化炭素産生量が増えたりして
のレベルを常に監視している。
例えば代謝による二酸化炭素産生量が増えたりして ![]() が設定値(=40mmHg)
よりも高くなると、脳内の呼吸中枢が刺激され、換気量を
増やして余分な二酸化炭素を体外に排泄し、
が設定値(=40mmHg)
よりも高くなると、脳内の呼吸中枢が刺激され、換気量を
増やして余分な二酸化炭素を体外に排泄し、 ![]() を
減らそうとする。一方換気量を増やし過ぎて
を
減らそうとする。一方換気量を増やし過ぎて ![]() が設定値
を下回ってしまった場合は、換気を抑制して、
体内の二酸化炭素レベルを維持しようとする。
結局血液中の二酸化炭素レベルに変化があると、呼吸中枢が
その変化を打ち消すように働いて呼吸調節反射が起こってくる。
すなわち
が設定値
を下回ってしまった場合は、換気を抑制して、
体内の二酸化炭素レベルを維持しようとする。
結局血液中の二酸化炭素レベルに変化があると、呼吸中枢が
その変化を打ち消すように働いて呼吸調節反射が起こってくる。
すなわち ![]() は負のフィードバック機構によって調節
されている(図1A)。
は負のフィードバック機構によって調節
されている(図1A)。
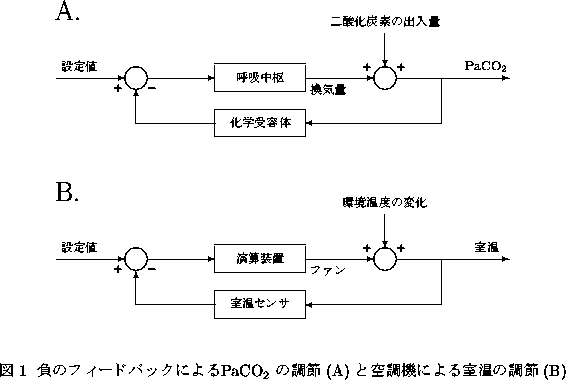
ところでこのような ![]() 調節機構は、少し考えれば
(最近の)室内空調機の動作原理と全く同じであることに
気付く(図1B)。すなわち、化学受容体が室温センサ
であり、換気量が温風あるいは冷風ファンにあたるし、
設定温度からのズレに応じてどの程度ファンを回すかの
決定も、最近の機械では「ニューロ〜」と呼吸中枢
(の神経細胞)を彷彿とさせるような演算装置が行っている。
調節機構は、少し考えれば
(最近の)室内空調機の動作原理と全く同じであることに
気付く(図1B)。すなわち、化学受容体が室温センサ
であり、換気量が温風あるいは冷風ファンにあたるし、
設定温度からのズレに応じてどの程度ファンを回すかの
決定も、最近の機械では「ニューロ〜」と呼吸中枢
(の神経細胞)を彷彿とさせるような演算装置が行っている。
したがって、このような自動調節機構を「生命現象の原理」
と呼ぶなら、そこには生体固有の構造は不要であり、
ヒトの ![]() 調節でも空調機による室温調節でも、
その内部での「(制御)情報の流れ」という
機能的側面のみが重要となる。これは大変な思考の簡略化で
あり、キャノン以降、ウィナー(N. Wiener)に引き継がれ、
「サイバネティクス」という新しい学問の原動力となっていった。
調節でも空調機による室温調節でも、
その内部での「(制御)情報の流れ」という
機能的側面のみが重要となる。これは大変な思考の簡略化で
あり、キャノン以降、ウィナー(N. Wiener)に引き継がれ、
「サイバネティクス」という新しい学問の原動力となっていった。
少々乱暴なようだが、今世紀に出版された生理学の
教科書の相当数は、上記のようなホメオスタシスの原理を中心に
構成されているといっても過言ではない。何しろ ![]() に
限らず、血圧でも体温でも、構造を離れて統一的に調節原理を
語れるのであるから、その魅力は大変なものである。さらに
この原理、特に負のフィードバックによる調節作用の概念は、
生理学を離れても、「苦あれば楽あり」というわれわれの
思考様式と奇妙にマッチするところもある。
に
限らず、血圧でも体温でも、構造を離れて統一的に調節原理を
語れるのであるから、その魅力は大変なものである。さらに
この原理、特に負のフィードバックによる調節作用の概念は、
生理学を離れても、「苦あれば楽あり」というわれわれの
思考様式と奇妙にマッチするところもある。
そんなわけで本書においても、次章以降ホメオスタシスの 原理を念頭において「からだの理」についての 理解を深めていただいて一向差し支えないのであるが、 少し変わった読み方をお望みの読者のために、最近の 話題にもいくらか触れておくことにしよう。
実はよく調べてみると、われわれの ![]() は一定(40mmHg)に
保たれてはいない。図2は、ヒトの安静時の
は一定(40mmHg)に
保たれてはいない。図2は、ヒトの安静時の ![]() を、その
推定値とされる肺内の二酸化炭素分圧によって60分間に
わたって示したものである。全体を平均してみれば
確かに
を、その
推定値とされる肺内の二酸化炭素分圧によって60分間に
わたって示したものである。全体を平均してみれば
確かに ![]() は40mmHgくらいに制御されているのだが、
その変化には大きな「うねり」が存在し、所々で40mmHgとは
大分離れていることがわかる。特に10〜15分のところでは、
かなり長期にわたって
は40mmHgくらいに制御されているのだが、
その変化には大きな「うねり」が存在し、所々で40mmHgとは
大分離れていることがわかる。特に10〜15分のところでは、
かなり長期にわたって ![]() が設定値より高くなっており、
このとき図1Aのフィードバック系が働いていれば、数秒の
うちに換気量を上昇させて
が設定値より高くなっており、
このとき図1Aのフィードバック系が働いていれば、数秒の
うちに換気量を上昇させて ![]() を低下させるはずである。
したがってこの場合、この時間帯に調節系が作動して
いないか(とりあえずあまり考えられない)、設定値自体が
42mmHg程度に上昇しているかのどちらかが起こっている
ことになる。
を低下させるはずである。
したがってこの場合、この時間帯に調節系が作動して
いないか(とりあえずあまり考えられない)、設定値自体が
42mmHg程度に上昇しているかのどちらかが起こっている
ことになる。
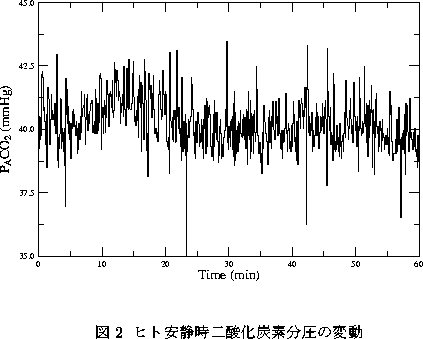
負のフィードバックによる調節は、通常設定値からの
ズレに対しては有効に働くが、設定値自体がズレる
ことについては何も語らない。そして、
「状態の変化→設定値の変化」と対応がつく場合は
まだマシなほうで(実はそんな単純な対応関係は
ないのだが)、図2のように設定値が時々刻々と変化するような場合は、
もはや手のつけようがない。実際、血圧や体温、心拍数の
経時的変化などを調べていると、「果たして設定値など
あるのか?」と思わず目を疑ってしまうことが少なくない。 ![]() 調節の
例でいえば、むしろ「きっちりと40mmHgに設定
していないのに、どうして平均的に40mmHg近辺に落ち着くのか」
と問う方がしっくりくるのである。
調節の
例でいえば、むしろ「きっちりと40mmHgに設定
していないのに、どうして平均的に40mmHg近辺に落ち着くのか」
と問う方がしっくりくるのである。
このように、生体の安定性は、ホメオスタシスすなわち 一定状態というよりも、むしろ一定の「動態」、あるいは ホメオダイナミクスとでも呼べるものかも知れない。 そして、このような生体の動的安定性がどのような原理によるものかは、 現在のところ全く知られていない。
また、少し考えてみれば分かるように、「なぜわれわれの ![]() は
いつも40mmHgに保たれているのか」という
問いに対する負のフィードバックによる説明は、
「なぜ〜保たれているのか」との説明にはなっているが、
「なぜ40mmHgなのか」という点には答えていない。
空調機の場合ならいざ知らず、「設定値が40mmHgだから」
というのでは、まるで禅問答である。
は
いつも40mmHgに保たれているのか」という
問いに対する負のフィードバックによる説明は、
「なぜ〜保たれているのか」との説明にはなっているが、
「なぜ40mmHgなのか」という点には答えていない。
空調機の場合ならいざ知らず、「設定値が40mmHgだから」
というのでは、まるで禅問答である。
血液中の二酸化炭素分圧は、換気量、代謝量はもとより、
体液の(酸の)緩衝剤の量などにより影響を受ける。動物の体重あたりの
換気量や代謝量は、からだのサイズが小さいほど大きく種によってまちまちで
あることが知られているが、それでもなお哺乳類の ![]() 調節系の
設定値は40mmHgであり、しかしながらカモでは30mmHg、
カエルでは10mmHg、ニジマスでは2mmHgとなっている。
したがって、「なぜ40mmHgなのか」という問いに真剣に
答えようとすれば、哺乳類の体液組成が、進化の過程で
どのようにできあがってきたのかまでを問わねばならいこと
になる。こういった問題を、生体の構造を離れた
フィードバック調節の図式で十分に説明できないことは
明白であろう。
調節系の
設定値は40mmHgであり、しかしながらカモでは30mmHg、
カエルでは10mmHg、ニジマスでは2mmHgとなっている。
したがって、「なぜ40mmHgなのか」という問いに真剣に
答えようとすれば、哺乳類の体液組成が、進化の過程で
どのようにできあがってきたのかまでを問わねばならいこと
になる。こういった問題を、生体の構造を離れた
フィードバック調節の図式で十分に説明できないことは
明白であろう。
ホメオスタシスのような説明能力の高い一般原理であっても 歯が立たないほど、「からだの理」は奥が深いのである。
(からだの理. 武藤芳照編. 丸善ブックス, より)
ホメオスタシス、あるいは生体調節の生理学についての 入門的図書としては、
ホメオダイナミクス(仮称)に関連する文献としては、
比較生理学(比較動物学)の入門的教科書としては、
からだの理
This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 96.1 (Feb 5, 1996) Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
The command line arguments were:
latex2html -split 0 jres_5.
The translation was initiated by Yoshiharu Yamamoto on 1998年06月06日 (土) 14時23分47秒 JST